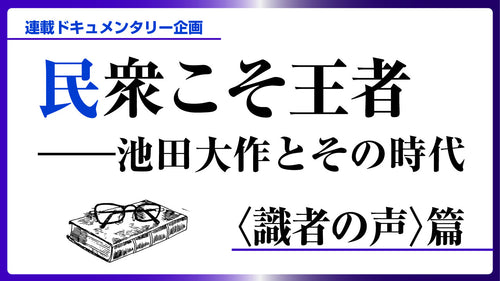『若親分、起つ』ためし読み
2024/10/04第一章 腹一文字
一
寛政五年(一七九三)、江戸は神楽坂毘沙門裏。
まもなく年の瀬を迎える。葭簀(よしず)囲いの隙間をぬって乾いた冷たい風が吹き込んでくる。
囲いのなかからは賑やかな三味線や笛太鼓の音が聞こえてくる。木戸銭を取って音曲やものまね、軽業、軽口噺を聞かせている。
寄席といって上方では生玉社(いくたましゃ)や坐摩社(ざましゃ)境内などでこのような興行がおこなわれているらしいが、江戸ではほかにはみかけない。
神楽坂はもとは武家屋敷や寺社がならんでいた。うわついた寄席のようなものはそぐわない土地柄のはずだがこのところは町家も増えている。寺の境内を借りて『大黒亭』と、名ばかりは立派な葭簀囲いの寄席には町人だけではなく近くの武家屋敷の侍が覆面をして現れたり、坊さまが手ぬぐいで頭を隠した格好で顔を出したりしてなかなか繁盛している。楽しいもの可笑しいものを見たり聞いたりしたいという人情は武家も坊さまも町人もかわりはないようだ。
高座の下手、紫に『大黒亭』と染め抜いた暖簾の向こうは芸人たちがたむろする楽屋になっている。
常吉(つねきち)は楽屋の一番奥、小さな陶製の手あぶりに身体を覆い被せて暖をとっている。
まだ若いのに常吉は寒がりだ。綿入れの丹前を着ているから背中が大きく膨らんでいる。
高座では芸人がじゃかじゃかとやたら派手に三味線をかき鳴らしながら軽口噺を続けている。
真冬にしては客の入りもよいが、芸はあまりうけてはいない。
万作(まんさく)という上方下りの芸人だ。大坂の地で名を馳せた米沢彦八(よねざわひこはち)の直弟子という触れ込みだが、常吉は「どうだかわかったものじゃねえ」と思っている。
万作はぺんぺんと糸を鳴らしてまたひとくさり、軽口噺を始める。
ある男が頼まれて棚をこしらえた。
「おまはんが吊ってくれたあの棚なぁ」
「へえ、なんぞありましたか」
「道具箱を載せたらすぐに落ちたヤないか」
「アァ、ものを載せたらあきませんがナ」
笑い声の代わりにひとりの客が大きなあくびをする。万作の軽口噺ではなく、あくびの大きさに笑いがおきる。
常吉は手あぶりにかじりついたまま顔を高座にあげた。
(万的の野郎……相変わらず客にうけねえでいやがる……)
公方(くぼう)さまのお膝元の江戸だ。なにによらず上方のものがありがたがられるが、上方の言葉だけは江戸では「生ッたれて聞こえやがン」というのだろうか、同じ軽口噺でも客のうけはよくない。
蝶という名の女芸人が常吉に湯飲みを差し出した。
「お寒うござんすねえ……葛湯を淹れやした。召し上がれ」
蝶は万作の女房だ。夫の不始末を詫びでもしているかのようだ。
「こいつぁかっちけねえ。いただくよ」
常吉は湯飲みを受け取った。火傷をしそうなほど熱い葛湯に息を吹きかけ啜る。
万作は客のあくびにも負けず高座を降りようとはしない。客の笑いをとるまでは決して高座を降りないと心に決めているかのようだ。
蝶は愛想笑いを浮かべながら、高座を降りない万作に露骨に嫌な顔をしているほかの芸人たちにも葛湯を振る舞っている。
葛はひと袋で何文するだろう。万作と蝶のふたりでも一日の稼ぎは知れている。苦しいなかから、夫に嫌な顔を向ける芸人たちの機嫌をとるための葛湯だ。
(万的みてえな奴でも夫婦となりゃ、また別なのかなぁ……わからねえものだ)
常吉は神楽坂肴町に親と弟と暮らしている。
常吉の父親は十手もち、目明かしだ。
神楽坂毘沙門裏の鐵(てつ)、といえば江戸の目明かしのなかでも名の通った男だ。
常吉も子供の時分は十手もちになろうと心に決めていた。
正規の十手は公儀(おかみ)から奉行所の与力同心といったお武家さまたちに下されるものだ。目明かしは正しくは十手もちとはいえないが、江戸の町で目にする十手もちはもっぱら目明かしたちだった。
末は目明かしに、と心に決めていた常吉だが二〇歳(はたち)を前にすっぱりと願いを捨てた。通常、目明かしはお上の御用だけでなくほかに生業をもっている。
常吉が父親の経営する『大黒亭』の楽屋に入り浸るようになってもう三年になる。くる日もくる日も、楽屋で芸人たちの軽口噺やら音曲噺やらものまねやら軽業を見るともなく聞くともなく過ごしている。
常吉は手あぶりに覆い被さっていた身体を起こした。うんと伸びをすると背筋が痛い。
どれ町内を一回りするか、と腰をあげかけたところに囲いの葭簀をめりめりと押しあげて楽屋をのぞき込んだ顔があった。
浅黒い顔が楽屋を見回している。男は常吉に目で合図を送ってよこした。
神楽坂毘沙門裏、鐵親分の手下の政五郎(まさごろう)だ。
年齢は三五、六歳。常吉にとっては叔父のような年格好だ。もっとも、少々苦手な叔父貴だが。
常吉は起ちあがった。町内を一回りして身体を伸ばそうかと思っていたところだからちょうどよい。
常吉は蝶に「ちょいと、出てくらぁ。あとを頼んだヨ」と言い置いて葭簀囲いを抜けた。
政五郎は常吉の先に立って早足で歩いている。どうせいつものように親爺からの小言だろうと思っていたが、どうも様子が違う。政五郎の早足は、なんだか他人目(ひとめ)をはばかっているかのようでもある。
常吉は小走りに政五郎に追いついた。
ちょうど毘沙門さまの山門のあたりだ。
政五郎は門の陰に身体を滑り込ませる。常吉も後に続いた。
「若……」
政五郎は乾いた声を震わせながら常吉に告げた。
「親分が……亡くなりやした」
二
常吉は政五郎の襟を摑んだ。
「なんだって……お父ッつあんが……死んだって……」
政五郎は常吉の手首を静かに引き離した。
「日本橋小舟町(こぶなちょう)の番所から知らせが参(めえ)りました。すぐにご一緒に……」
「死んだって……どうして……」
政五郎はさらにあたりをはばかるかのように声をひそめた。
「親分は昨夜(ゆんべ)もあのあたりを張っていなさったのですが…… 今朝方、倒れているとろが見つかった、と……詳しい話はまだわかりませんで……」
江戸中に名を馳せている目明かしだ。恨みをもっている悪い奴らも多い。
「悪党に刺されたのか、畜生め……」
常吉が子供の時分、父は盗賊の頭目を捕えるという大手柄をたてた。公儀から銀五枚のご褒美もいただいた。神楽坂毘沙門裏の鐵の名を高らしめた一件だ。
常吉は木切れで十手をこしらえ、捕り物ごっこをして遊んだ。ゆくゆくは本物の十手を手に、江戸の悪い奴らを片端からつかまえるのだと心に決めていた。
神楽坂は江戸のほかの町とは違い、武家と町人が境を接して暮らしている。武家といってもお大名の屋敷はなかったが、なかなか羽振りのよい旗本や御家人の屋敷がならんでいる。武家の若様ともなれば屋敷の広い庭で遊ぶものだが、そこは子供だ。門の外から同じくらいの子供たちが遊びに興じる声が聞こえてくるからたまらない。歴々の若様がこっそり屋敷を抜け出して常吉たちが遊んでいるところに混じったりもした。
なかに人見という旗本の子供もいた。屋敷に仕える用人の子供たちを家来として引き連れ、常吉たちの遊んでいる赤城明神の境内に姿をあらわす。
わがまま一杯に育った子供だ。家来の子供たちに命じて町人の子供を追い立てにかかる。家来たちは木の棒を刀のように振り回して町人たちを追いかけ回す。
常吉の遊び仲間には、大工の息子や魚屋の倅、鋳掛(いか)け屋の子など腕っ節も心根も強いものがそろっている。
が、お武家さまには逆らうものではないという知恵は、皆、心得ていた。
「人見典膳じゃ、どけ、どけぃ」と叫び、滅多矢鱈に棒きれを振り回し常吉たちを追い立てにかかる。偉いのかどうかもわからぬ家名だが、お侍が相手だ。町人たちはわあきゃあと悲鳴をあげ頭や尻に手をあてながら逃げまどう。侍の子たちは面白がってさらに追いかけ回す。
一緒になって逃げ回っていた常吉だったが、とうとうあまりの仕打ちに足を止め向き直った。
若様はひときわ立派な黒羽織に袴姿だ。
常吉にまともに顔を向けられ少しひるんだ様子だったが、すぐに虚勢を持ち直し鼻の頭をつんと上にもたげて言い放った。
「そなたは何者であるか。無礼を致すと捨て置かぬぞ」
若様の手は腰に差した短刀にかかっている。旗本の子だ、差し料は真刀だろうが抜く気遣いはない。
常吉は愛用の木の十手を握りしめた。
お武家さまは名を気にするから顔に傷でもつけたらさすがにことは面倒になるだろう、と常吉は思った。
常吉はものもいわず、ぐっと身を沈めると木の十手で若様の向こう臑(ずね)を思い切り払った。
「ぎゃあ」
若様は声をあげるとうずくまった。両手で常吉に打たれた向こう臑を押さえ、おいおいと泣いている。
お付きの子供たちは驚いて若様に駆け寄った。どうしてよいかわからぬ様子で泣いている若様を取り囲んでいる。なかには若様につられたかのように、同じようにおいおいと泣き出す子供もいる。
(なんでえ、意気地のねえ)
常吉は武家の子供たちに背を向けるとすたすたと赤城明神の境内を後にした。
家に戻ると父の鐵は長火鉢を前にして煙草を喫んでいた。
常吉は赤城明神での出来事を鐵に話した。
「よしわかった……相手は人見さまだな」
鐵は常吉を𠮟りもせずうなずき起ちあがった。
着物のうえに羽織だけをひっかけ出ていく。
しばらくすると鐵は戻ってきた。
「怖がらんでもいい……ただこれからぁ、むやみな真似をするんじゃねえョ、常」
鐵が戻ってしばらくすると、「御免。許せよ」という声とともに立派な侍が姿をあらわした。
侍は「人見典膳用人の某(なにがし)」と名乗ると、鐵に告げた。
「子供同士の諍(いさか)いゆえ、当家からはなにほどのこともなし」
にこりともせずに口上を述べると、侍は常吉にちらりと目を送り立ち去っていった。
「やっぱりお天道さまは見ていなさる。こっちが悪くなけりゃ、何ということもねえンだ……それにしても……」
鐵はやれやれという顔でかしこまっていた膝を崩し、掌を首筋にあてて汗をぬぐっている。
「お父ッつあんはすげえや……お武家さまがわざわざうちにくるなんざぁ、さすがは神楽坂毘沙門裏の鐵親分だ……」
道を急ぐ常吉の脳裏に、三年前の鐵とのやりとりがよみがえった。まもなく二〇歳になろうかというときだ。
鐵は常吉に言い放った。
「おめえみてえな了見じゃ、とうてい十手もちにはなれねえ。やめちめえな」
「なんだっておいらが目明かしになれねえんでえ」
「それがわからねえ奴には、とうてい目明かしは無理だ、って話だ」
「へん、無理というなら知らねえや。目明かしなんぞになるもんか。糞でも食らえ」
以来常吉は、大黒亭に入りびたりになった。
なぜ目明かしは無理だといわれたか、常吉にはわかっている。
鐵は寄席を経営するだけではなく、江戸の町のあちこちに貸家を所有している。だいたい、二〇歳にもなろうという常吉が日々ぶらぶらと寄席の楽屋で遊んでいられるのはなぜか。
そもそも子供の頃、赤城明神の境内で武家の子供を泣かせても無事に済んだにもそれ相応の事情がある。
目明かしという生業や世の中のからくりがわかってくるにつれて、常吉の心のなには嫌悪の思いがつのる一方だった。
目明かしは町奉行所の同心の、いわば私的な手足となって江戸の町を歩き回る。自ずと、それぞれが隠しておきたい秘密や恥部を目にしたり耳にしたりもする。
常吉は盆暮れになると、「親分さんにはいつもお世話になっております」と挨拶にくる大人たちの姿を目にしてきた。それぞれが携えてくる『手土産』がなんなのかも理解してくる。
常吉のたまりにたまった思いが口をついて出た。
「それじゃ、強請(ゆすり)たかりじゃねえか」
そうではないとは常吉もわかってはいる。そもそも子供の頃、武家の若様を泣かしておいて無事で済んだ理由(わけ)も、今となってははっきりしている。なにしろ侍が相手だ。
『神楽坂の鐵』という名や顔だけでことがすむはずがない。
大名旗本の屋敷では中間(ちゅうげん)という小者を多く使っている。中間のなかにはなかなか性質(たち)の悪いものも多い。甚だしいものは主家の威光をかさにきて、町の人たちに難癖をつけ金品をせびったりする。そうでなくとも屋敷のなかにある中間部屋で御法度の博打を開帳したりする。
目明かしは江戸町奉行所の御用をつとめるので武家屋敷には手出しはできないが、町方の事件や天下の御法度の博打となれば話は別だ。
鐵などは神楽坂飯田橋界隈のほぼすべての武家屋敷に利く顔をもっていた。常吉の一件もおそらく、先方に赴き話をつけたのだろう。あとからわざわざ用人もきて、「お構いなし」と告げたところは、常吉が泣かせた人見という旗本は鐵にかなりの厄介を負うていたのだろう。
わかってはいたが常吉の心の底には、おおきなわだかまりが渦を巻いたままだった。
「それじゃ、強請たかりじゃねえか」とは、常吉の偽らざる思いだった。
鐵から「おめえみてえな了見じゃ、とうてい十手もちにはなれねえ」と言い渡された常吉は以来、日がな一日『大黒亭』の楽屋にくすぶっていた。
(二〇歳を超えているのに……おいらは何をしているンだか……)
神楽坂から日本橋小舟町まで急ぐ。半時(一時間)と少しの道のりだ。
小舟町は名のとおり、江戸の町の水運をになう河岸(かし)がならんでいる。また下駄や雪駄などの履き物や傘をあきなう店などが並び昼は賑やかなところだ。
神楽坂や飯田橋一帯を縄張りにする鐵だが、なぜかこのところ、しきりに日本橋に出向いていた。
「こいつぁ見逃しにはできねえンだョ」というだけで子分の政五郎にも詳しくは語ってはいなかったという。
小舟町の番屋につくと、すでに町奉行所の同心は検屍(けんし)を済ませて引きあげていた。鐵の遺骸は筵をかけられて横たわっている。
常吉は筵をめくりあげ、鐵の遺骸と対面した。鐵は検屍のため下帯だけの姿になっていた。
身体中からは血の気が失せ、青黒い。鐵は目をつむり口を結んだ顔を真上に向けている。
腹には真一文字の傷が一本通っている。近所の医者が縫い合わせてくれていた傷口の端が赤黒くめくれあがっている。番屋のものに手伝ってもらい、鐵に着物を着せる。政五郎が立ち働いて車や筵を借りるなど鐵の遺骸を運ぶ算段をする。
人を雇って車を曳いてもらい、常吉たちは番所をあとにした。時おり冬の冷たい風が音をたてて吹きつけ、遺骸にかけた筵の端をめくりあげる。神楽坂肴町に戻ったときは、もう日の暮れ方になっていた。
三
神楽坂肴町の家には大勢がつめかけていた。
町内の人たちに混じって、付き合いのある目明かしたちも集まっている。鐵とは兄弟分として親しかった本所牛嶋の安(やす)親分は常吉の顔を見るなり目を潤ませた。
「常よぉ……おめえの親爺も、とんだことになっちまったなぁ……」
安は額のまんなかに大きな瘤のある、いかつい顔の持ち主だ。子供の時分の常吉は牛嶋のおじさんが怖くてたまらなかった。
ただ安は言葉遣いこそ乱暴だが心根はやさしい。常吉は安に猫のように襟首を摑まれ鐵の遺骸を収めた早桶のすぐ前に座らされた。
「ここはおっ母さんが……」と言いかけた常吉を、安はいつものように怖い顔をして𠮟りつける。
「べらぼうめ。通夜の席次の頭ぁ総領のおめえに決まってらぁ……おとなしくいうことを聞きゃがれ」
常吉の生母はすでに亡くなっている。鐵の後妻の絹はもとは左褄(ひだりづま)をとっていた芸者だ。
売れっ妓(こ)だっただけあって絹は肝が据わっている。夫の変死にも取り乱したりはせず、細かく立ち回って通夜客たちの相手をしている。
さすがの安も、気丈な絹の様子には苦笑した。
「姐さんも、そんなんじゃ手伝いにきたわっちらの働きどころがねえ……早桶の前(めえ)におさまってておくんなせえ」
「そうですかい……じゃ、兄さんのお言葉に甘えて……」
常吉の次には絹の産んだ弟の多吉郎、その次に絹が座った。
多吉郎は一七歳。ひょろひょろと痩せた体つきからして常吉とは違う。大の学問好きなところから生前の鐵は「多吉郎には御家人の株でも買ってやって学問をさせるか」といっていた。
多吉郎は無残な鐵の死に顔色もない。
常吉の隣でずっと頭を下げしゃくり上げている。
(目から鼻へ抜けるような奴だがまだ子供だ、無理もねえ……)
常吉は弟の頭を撫でてやりたい思いにかられた。
泣き続けている多吉郎の頭越しに絹と目が合う
座って落ち着くと改めて悲しみが湧いてきたのだろう、絹の目は少し赤い。絹は常吉にむかって小さく頷いた。
「常吉……ご苦労だったねえ」
「へえ、おっ母さん」
常吉も頷いた。
通夜の振る舞いは、近所の連中が手伝ってくれている。白い襷をかけてかいがいしく働いている若い娘は同じく神楽坂の箪笥町の八百屋の美代(みよ)だ。
美代は一八歳になる。幼いころから何かにつけて常吉にじゃれついてくるおちゃっぴいだが、こうして立ち働いてくれている姿はなんだか頼もしく見える。
絹もしみじみと呟いた。
「美代(み)ぃちゃんも、あんなにくるくる働いてくれて、ありがたいことだねぇ」
落ち着いたらきちんと礼をしなければならねえ……と思った常吉だが、(ほどほどにしておかねえと美代ぃ坊の奴ぁ、すぐつけあがるからなぁ……)と思い直す。
「どうも……とんだことでおます」
素頓狂な声とともに万作と蝶の夫婦も姿をあらわした。大黒亭にきていた芸人たちもぞろぞろとあとに続いている。
常吉は皆に声をかける。
「よくきてくれた……仏ぇ拝んだら、何にもねえが一杯(いっぺぇ)吞(や)ってってくんな」
芸人たちに酒が入った。
「どうも湿っぽくていけねえなぁ……お蝶さん、ひとつここはご陽気にお三味線(ぺんぺん)で景気をつけてくんなせえ」と調子にのった芸人がひと調子高い声を張りあげる。
「このとんちきめ……通夜で陽気もあるものか」と牛嶋の安が剣突を食らわせる。
賑やかな通夜になった。
常吉の隣で泣いていた多吉郎がようやく顔をあげた。
拳でぐいと洟(はな)をしごくと、吐き捨てるように呟いた。
「畜生め……お父ッつあんに逆恨みなんかしやがった悪党め……」
常吉は顔を前に向けたまま多吉郎に呟いた。
「逆恨みの悪党かどうかはわかったもんじゃねえぞ、多吉郎」
常吉は今度は多吉郎にまっすぐ顔を向け、告げた。
「腹の傷はただの一刀、真一文字だった……下手人は侍(さむれえ)だ、間違(まちげ)えねえ」
通夜酒に酔った芸人たちはなかなか尻をあげようとしない。万作などは先頭にたって騒いでいる。
「美代ィちゃん、あと二、三本つけてもってきてェナ」などと声を張りあげる。
蝶が「あんた、いい加減にするものだよ」と万作をたしなめるが、絹はうっすらと笑いを浮かべている。
「にぎやかなほうが仏も寂(さむ)しくねえだろう。遠慮しねえで呑ったらいい」
万作は「そら、お許しがでたデ」と声を張りあげる。調子にのった芸人たちの騒ぎに、牛嶋の安が「なにもがんばってでけえ声を出せ、ってんじゃねえや、とんちきめ……鐵は……鐵はなァ、ああみえて無闇な騒ぎは嫌(きれ)えなたちだったんだ」と睨みつける。当の安も茶碗酒を手から離さずあおっているから、もう朱泥(しゅでい)の仁王さまのような様子になっている。
真夜中近くになった。通夜客たちもそれぞれよりかかる壁や柱をみつけてこくりこくりと舟をこぎ始める。常吉の横でかしこまっていた多吉郎もこくりこくりとし始めたかと思うと、こてんと横倒しに寝入ってしまった。
にぎやかだった通夜が水をかけられたかのように静かになる。
眠気とたたかう常吉だが、鐵の腹を一文字に切り裂いた傷跡だけが妙な生々しさで目の前によみがえる。
鐵はなぜ、縄張りでもない日本橋で斬られるようなはめになったのだろうか。
勝手で眠気覚ましの茶を沸かしていた美代が顔をのぞかせた。顔が常吉を呼んでいる。
常吉は座を立ち、土間に降りた。
「こちらさんが……」
美代がむけた顔の先に、男がひとり立っている。
暗がりではっきりとはわからぬが、年齢は五〇歳ほどか。でっぷりと肥えた男だ。
男は両手を膝にあてると、常吉にむけて丁寧に腰をかがめた。
「手前……両替屋源右衛門(げんえもん)と申します」
深く柔らかいとろけそうな声だ。体つきと同じく福々しい顔だが、肉に埋もれて目のありかが分明ではない。眠った猫のような顔つきだ。
どうやら裕福なあきんどのようだ。鐵の知り合いとは思えぬが、常吉も腰をかがめて両替屋に挨拶をした。
「ようこそお越しで……狭(せめ)え家ですが、仏に手を合わせてやっておくんなせえ」
両替屋は変わらぬ柔らかい声で応じる。
「お取り込み中でございましょうから、手前はここから拝ませていただきます」
両替屋は羽織の袂から取りだした数珠を両手にかけると顔の前であわせた。数珠は水晶らしく、かすかな光を白く跳ね返す。
常吉は訊ねた。
「旦那は鐵とはどういう……」
両替屋は常吉の声が耳に入らなかったかのような様子で数珠をしまうと、「では、これで手前は」とふたたび膝に両手をあてて頭をさげた。
(なんでえ、この野郎は……死人の出た家の様子を見物にでもきやがったのか)
戸口の外に、両替屋の供をしてきたらしい男が立っている。藍色の着流しで腰に二本を差している侍だ。両替屋の用心棒でもしているのだろうか。
月明かりに侍の顔が浮かびあがった。
******
親爺・・・
あんたは何を見ちまったんだいーー
神楽坂で名を馳せた目明かしの鐵が謎の死を遂げる。 腹には横 一文字に斬られた傷。 のんべんだらりとした毎日を送っていた鐵 の息子の常吉が跡を継ぎ 「神楽坂の若親分」 となった。 鐵の 右腕だった腕利きの子分や一癖も二癖もある親分衆、仲間たち の手助けで常吉は父の死の真相を追っていく。 父の情婦とおぼ しき女の存在が浮かびあがったと思いきや、女の夫もやはり父と 同じように斬られて死んでいた。 事件はやがて大奥や公儀 中枢にまで及び、国を傾けかねない一大事が見え隠れし始める。
潮文庫『若親分、起つ』のご購入はコチラ

作家
伍代圭佑(ごだい・けいすけ)
生年出身、非公開。主な著書に、三部作となる『江戸留守居役 浦会』『江戸留守居役 浦会 火盗対浦会』『江戸留守居役 浦会 白河対浦会』(いずれも、ハヤカワ時代ミステリ文庫)。
X(旧Twitter)ID:@keisukegodai