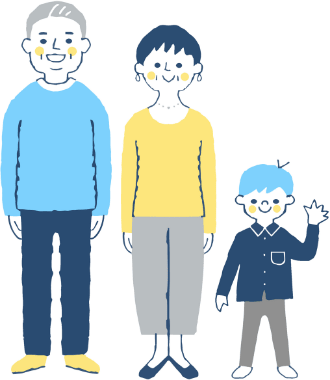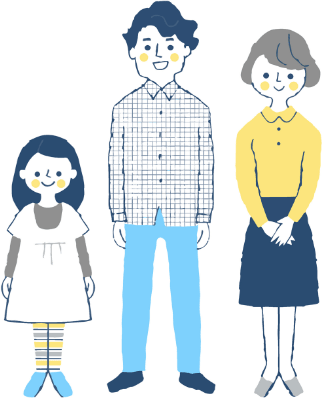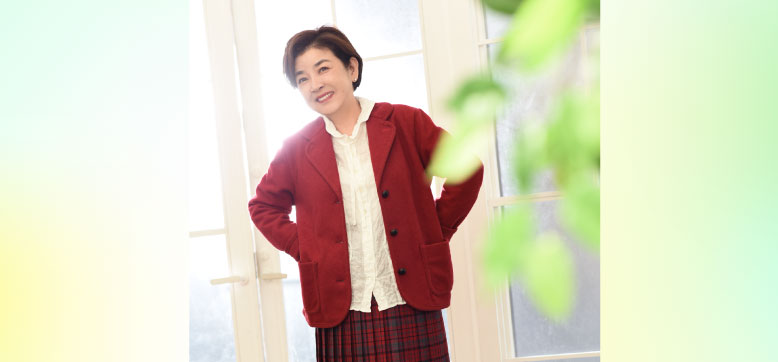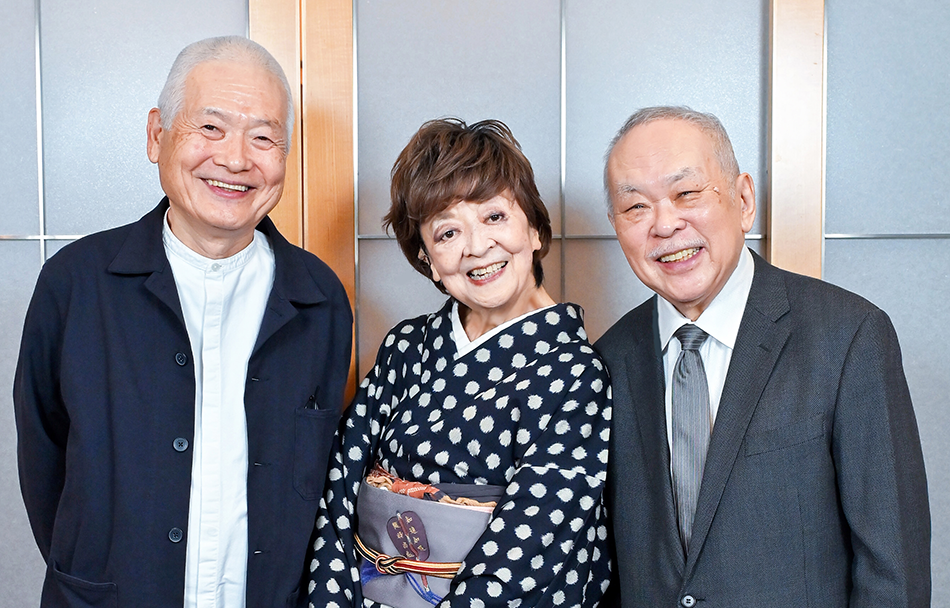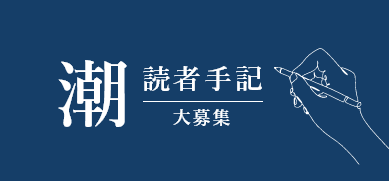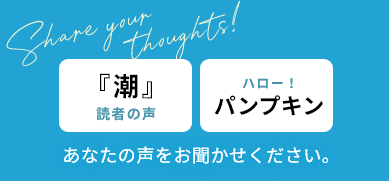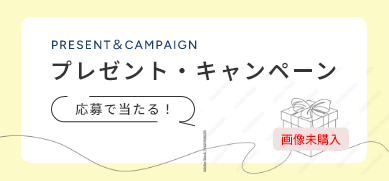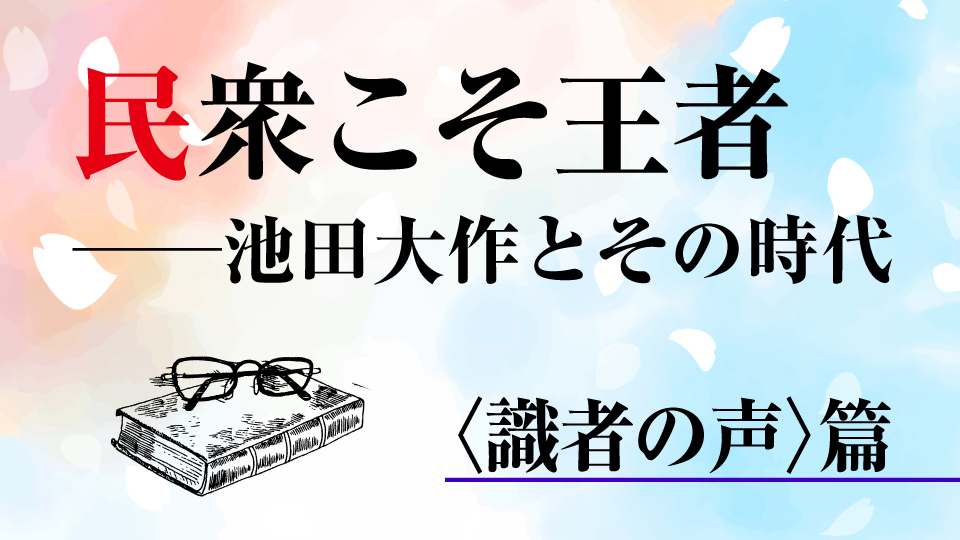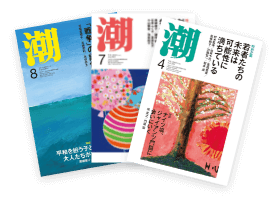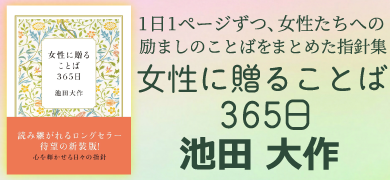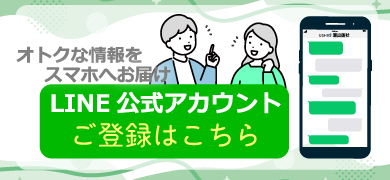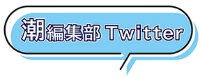新着コンテンツ
新着コンテンツ
-

- 社会
ベネズエラ・マドゥロ氏拘束が国際社会に植えつけた危険な"種"
-
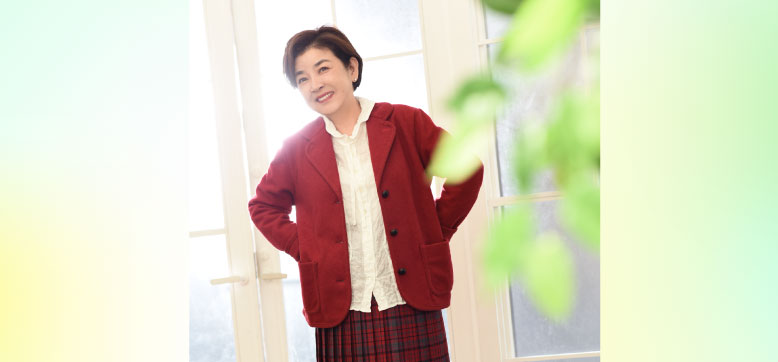
- エンタメ
【総集編が公開中】 岸本加世子さん ラジオ番組「負けない人生」を朗読して
-

- 創価学会
【先行配信】政治における「平成」が幕を下ろした果てに――解散総選挙と「中道」の誕生
-

- 生活 文化
世代が離れた相手と信頼関係を築くには――哲学から対話の扉を開くヒントを得る
-

- 読みどころ
パンプキン2026年3月号 読みどころ
-
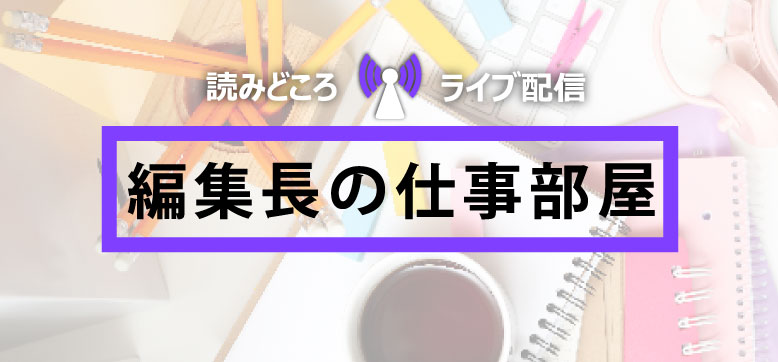
- 読みどころ
編集長の仕事部屋【2026年3月回】
-
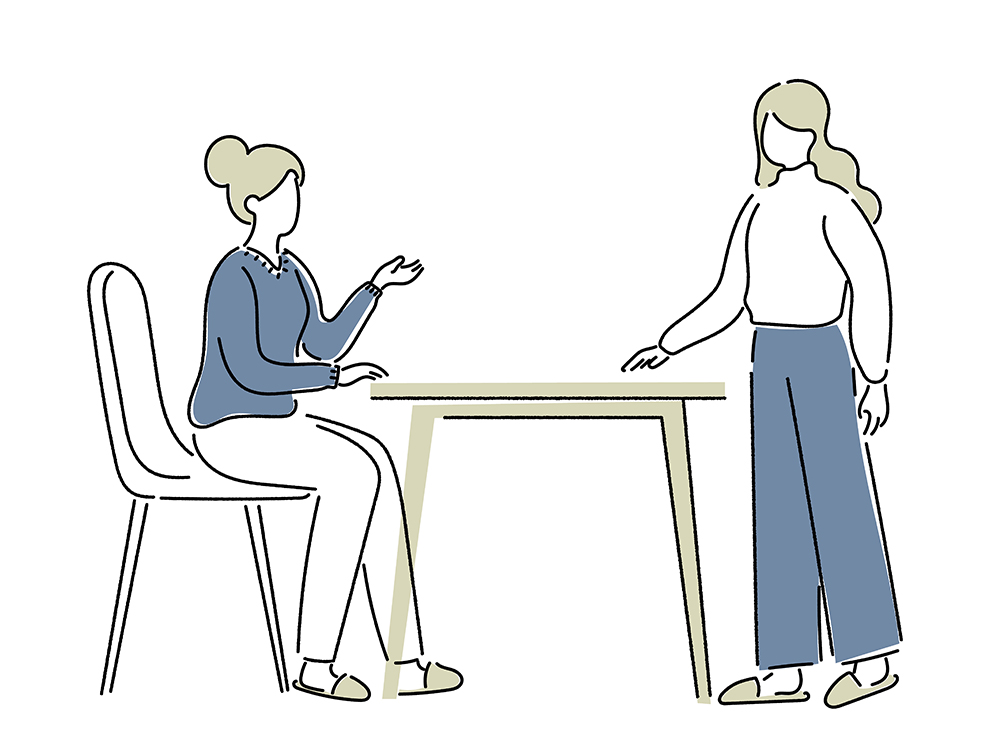
- 生活 文化
意見の違う知人と、どう話せばいいの?――哲学から対話の扉を開くヒントを得る
-

- 読みどころ
月刊「潮」2026年3月号 読みどころ
-

- 社会
それでも核兵器廃絶を諦めてはいけない――制限なき軍拡の時代への抵抗