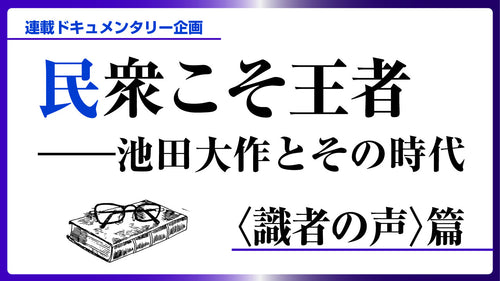月刊『潮』が見た60年(名語録編)
2023/03/311960(昭和35)年7月2日、月刊『潮』は産声をあげました。 以来六十星霜、通巻740号を超える歴史の中から、これまで誌面を彩った 有識者、文学者、ジャーナリスト、芸能、スポーツなど、各界の豪華な顔ぶれに再度ご登場いただきます。 名語録編では60年の歴史の中でも特筆すべき記事を抜粋しています。お楽しみください。

◆名語録編◆
脳でこころがどこまでわかるか
河合隼雄(文化庁長官・京都大学名誉教授) 茂木健一郎(脳科学者)
河合 それで、宗教と科学が接点を持つときにいちばん可能性があるのは、僕は仏教やないかと思うんです。一神教は、キリスト教にしてもイスラームにしても絶対神というのがありますよね。ところが仏教は絶対者というのを立てないでしょう。自他の認識から話が始まる。だから仏教がいちばん可能性があるんじゃないかなと。
茂木 人間は死んだらどうなるかとか、生きる苦しみということについて、ほかの宗教は答えを与えてしまうけれども、仏教というのは、ある意味で「生きるってしんどいね」という共感というか、問題を共有することからスタートするというところがありますよね。仏教の哲学で僕がいちばん好きなのはそういうところなんです。(『潮』2006年8月号より抜粋)
人を活かす「勝利の法則」
野村克也(東北楽天ゴールデンイーグルス監督)
私は「目的のない練習はするな」って言うんです。やらされてやる練習と自分からやる練習はおのずと効果が違うんだから。/球種を一つ増やすとか、投げるタイミングをちょっと変えてみるとか、角度を少しいじってみるとか。ほんのちょっとでいいんです、「小事が大事を生む」という格言もあるわけですから。私が見るのはそういうところですね。小さいことが大事で、小事をおろそかにする人は伸びていかない。名選手、一流選手はみんな繊細で、バッターで言えば、バットのグリップなんか、もう紙一枚ぐらいの太さ、細さにこだわるぐらい神経質なんです。二流の選手ほど鈍感なんですよ。(「潮」2009年3月号より抜粋)
※スポーツジャーナリスト・二宮清純氏との対談のなかで
「師を持つ人生」のすすめ
内田 樹(神戸女学院大学教授)
師弟関係とは、師と弟子の一回的な、固有の関係において生じるケミストリー(化学反応)であって、「万人にとって同じように素晴らしい師匠」がいるわけではないし、「どんな師匠にとっても教え甲斐のある弟子」がいるわけでもない。ある人にとってかけがえのない師が、べつのある人にとってはそうではなく、ある師匠にとっての愛弟子が他の師匠からは凡庸に見えるということは当然ある。どちらの評価が正しいということではない。師弟は一期一会だということである。ただ、誰にとってであれ、「師」たりうる人の条件は一つだけ決まっている。それはその師自身がかつて誰かの弟子であったということである。先生自身が師について、おのれの限界を超え、おのれの檻から逃れ出て、知性的・身体的なブレークスルーを経験したことがあるという事実、それが師たる人の条件である。 (『潮』2010年10月号より抜粋)
「中道の時代」と月刊『潮』の使命
山崎正和(劇作家、評論家)
「中道」を標榜する『潮』が健全なスタンスを堅持した雑誌であることは、いまさら言うまでもない。ただ、政治の場合もそうだが、中道という言葉の定義はなかなか難しく、例えば、公明党は中道を旗印に掲げ、与党の一角として政権の内側から自民党の、特に右寄りの人たちを牽制している。先の「安保法制」整備の際のスタンスを見ても、自民党内にあった、いささか右寄りの意見を抑える役割を果たし、中道政党ならではの調整力を発揮した。だが、いろいろな意見を真ん中に集めることだけが中道ではない。左右それぞれの「真ん中」というのは大切だけれど、それだけでは中道の定義として不充分である。私の考える中道というのは、政治の場合も雑誌編集の場合も同じだが、問題を提起するだけでよしとしない態度だ。「この問題が大変だ」ということを縷々主張したとしても、少なくともどこかに解決への道を示唆するのが中道だと私は考えている。 (『潮』2017年6月号より抜粋)
「令和」と万葉集
中西 進(国文学者、国際日本文化研究センター名誉教授)
「令和」の二文字は、『万葉集』にある以下の一節から「令」と「和」が取られました。〈初春の令月にして 気淑く風和ぎ 梅は鏡前の粉を披き 蘭は珮後の香を薫らす〉。これは大伴旅人ら三二首の「梅の花の歌」の序文です。「令月」とはもともとは陰暦の二月を指す言葉ですが、大伴旅人は日本の風土に照らして、一月と読み替えました。現代を生きるわたしたちにとっては「新しい時代が始まる初春の月」とでも言い換えられるでしょう。これまで日本のすべての元号は漢籍(中国の古典)をもとに考えられてきました。「令和」は歴史上初めて、漢籍ではなく国書(日本の古典)からつけられた元号です。そもそも元号は中国で皇帝の統治を表現したものとされています。その理念を二字に込めるのでしょう。すると漢籍の文字を、しかも儒教の経典から採用することは中国儒教の理念を日本の天皇が理念とすることになってしまいます。日本が中国から冊封(皇帝の命令書である冊書をもって爵位を与え、封建すること)を受けていた時代はそれもあるかもしれませんが、今や近代国家として日本は近隣の独立国ですから、日本は日本で政治の根本を定めることが当然でしょう。明治以降150年遅れましたが、やっと「元号冊封」から自立することができました。(『潮』2019年6月号より抜粋)
・肩書は基本的に掲載当時のものです。また、一部敬称を略しています。
・一部、現在では不適切な表現がありますが、時代背景を尊重し、そのまま引用しています。
・一部、中略した箇所は/で表記しています。
・表記については、編集部で現在の基準に変更、ルビを適宜振り、句読点を補った箇所があります。