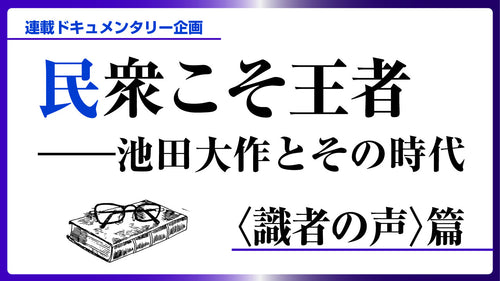月刊『潮』が見た60年 1976-1980
2023/03/31ロッキード事件と民主主義の反省
白鳥令(独協大学教授)
二日間にわたって行われた衆議院予算委員会における証人喚問で、小佐野賢治氏は最後まで「記憶がない」を繰り返し、児玉誉士夫氏ははじめから出頭せず、丸紅側の証人はみずからが被害者であることを強調して終始したのを見ていると、いくら予想されたこととはいえ、私も多くの国民と同様にどうしようもない無力感におそわれる。/事件の真相の究明は何よりも必要である。だが、事件の真相を明らかにし、関係者を処罰しただけでは問題は少しも解決しない。そのような解決は、今回の事件が生じた必然的な社会と政治の構造を隠蔽し、今後この種の事件を防止するのに役立つどころか、同種の事件がより巧妙なかたちで行われるのに手を貸す役割を果たすことになろう。(『潮』1976年4月号より抜粋)
不敬列伝
沢木耕太郎(ルポライター)
――昭和51年1月2日。快晴のもとで皇居の一般参賀は行われた。皇居前広場に並ぶ長い列に、ぼくもまたつき従っていた。午前11時に皇居内へ入ることができた。/それにしても、2年前と少しも変わっていないのは私服警官の数の膨大さだった。ジーンズの上下を着た参賀者は奇怪に見えるのか、ぼくの周りを5㍍から10㍍の距離に10人くらいの私服が取り囲んだ。バッグからカメラを取り出そうとすると、彼らは一様に緊張した。この実に些細な体験は、参賀者の数がいくら増えようと、ジーンズ姿や長髪の若者は依然として怪しまなくてはならない存在であるという一般参賀の「質」を教えてくれるとともに、天皇への「不敬」行為を公安当局がどれほど恐れているかも物語ってくれている。(『潮』1976年6月号より抜粋)
日本の新聞を考える
本田靖春(ジャーナリスト)
新聞を取り巻く状況は、以前とは大きく変化しているのに、いぜん新聞を「ジャーナリズムの王者」だと信じ切って、「言論の自由」という金看板に何の疑いも抱かない。新聞社の看板を表にかかげておけば、金ピカの「言論の自由」が玄関から転がり込んでくるわけではないのである。チャンピオン・ベルトは、飢えに耐え、渇きとたたかい、ジムワークに汗を流し、ロードワークに歯をくいしばり、立ちはだかる強者を残らずマットに沈めた最終的な勝利者だけに許されるものである。戦わない新聞に、だれが「ジャーナリズムの王者」の呼び名を贈るというのだろう。(『潮』1976年10月号より抜粋)
恐るべき「原発社会」がやってくる
鎌田慧(ルポライター)
100万㌔ワットの原発で建設総額1基3000億円。それが15年ほどで廃炉になる。日本のそこかしこの海岸線に、醜い巨大コンクリートの塊りが立ちつくす。やがて瀬戸内海岸に面した伊方では、ちょうど対岸の広島の原爆ドームと向かい合うかのようにし、無人の廃炉が列をつくって並ぶ。ここの原発反対のある主婦は、こういい放っている。「五十代の人なら、原子いうたらピーンとくるのよ。どない上手にいうてもろうたところで、わたしらには絶対なりません。戦争の恐ろしさが身にしみてますからなぁ」(『潮』1976年11月号より抜粋)
キャンディーズに祝杯を!
鈴木均(評論家)
私がキャンディーズの〝さよならキャンペーン〟にノリだしたのは〝あと34日!〟というフジの特番に感動してからである。その第2部で、西田敏行が花束をもってあらわれると、みるみるうちにランの顔がクシャクシャになり、涙がぽろぽろと頬をつたった。ミキに、スーにカメラが移動する。三人ともにベソをかきだした。3人とも西田を尊敬しているのだという。これは局がわの仕掛けで、彼女たちにとってはハプニングだった。涙のマジメさが私に伝わってきた。(『潮』1978年6月号より抜粋)
江川卓君への書状
小中陽太郎(作家)
人の噂も七十五日、というけれど、82日目に、実行委員会の決定が降り、小林は阪神、江川は4月7日に巨人入りと出て、ようやく世論も、半ば納得、半ばあきらめて、この事件も一段落、貴兄も矢沢コーチを相手に、トレーニングにはげんでいることでありましょう。ここらで、一体、江川騒ぎとは何だったのか、考えてみるのもムダではありますまい。とくに、日本人の心理構造がよくわかる事件でしたから。実は話はとびますが、わが日本アジア・アフリカ作家にも江川騒動は大いに影響があった。というのは、有力会員に、江川卓といって、有名なロシア文学者がいる。/この人、たまたま、野球選手と同姓同名だっただけに、脅迫電話が大変でした。「死ね」。なんで栃木県の江川の家が、東京にあると思うのかね。(『潮』1979年4月号より抜粋)
鄧穎超女史の12日間
吉田実(朝日新聞編集委員)
「サクラの季節に神戸の港を出て、天津に戻ってきました。――できれば、サクラの咲くころ、もう一度、日本を訪ねたい」。青年時代の一時期を日本に学んだ、生前の周恩来首相が、よく日本からの訪中代表団の人々に語っていた言葉である。その遺志を継いで、夫人の鄧穎超女史(中国全国人民代表大会常務委副委員長)が、わが国の国会に当たる全国人民代表大会(全人代)の代表団(団員11人、随員14人)を率いて、初めて来日した。4月8日、ちょうど、周首相が思いを寄せていたサクラの時候である。/この旅は、日中友好に大きな功績を残した周首相と革命の生涯をともにし、かつ終生変わらぬ伴侶だった鄧女史のものだったことに、かけがえのない意味があった。そして、この中に、公的にも私的にも、周首相と分ち難い「心の旅路」を見た思いがする。(『潮』1979年6月号より抜粋)
小説の劇化・映像化
池波正太郎(作家)
自分の小説が芝居や映画、またはテレビになるとき、私は、あまり、うるさい注文をつけぬほうだとおもっている。だが、現在も連載中の、たとえば〔鬼平犯科帳〕とか〔剣客商売〕とか〔仕掛人・藤枝梅安〕とかの場合は、作者の自分のみならず、読者のイメージもくずれてしまうことがあるので、脚本に目を通すし、意見もいう。ことに〔藤枝梅安〕は、大金で殺しを請負う男だけに、よほど、神経をつかって制作してもらわぬと、どうにもならなくなってくる。テレビでは緒形拳が演じ、好評だったが、私の書いた梅安ではなく、脚本も演出も血まみれの汚らしいものだったので、中止させた。しかし好評だというので、引きつづいて〔必殺仕置人〕というのをやりはじめたが、これは、私の関知するところではない。仕掛人と仕置人、一字ちがいで、私が創った名称をまねているわけだが、まことにあくどい事をするものだ。(『潮』1980年10月号より抜粋)
山口百恵―爆走と抵抗の2795日
加藤仁(ルポライター)
「スター誕生!」の決勝戦で山口百恵の大根足がホリプロダクション堀威夫社長の目にとまった。大根足ができるのはなぜか。まずよく食べるからであり、次によく眠るからである。健康な証拠だ。つねに健康であればこそハードスケジュールに耐え、いつも笑顔でファンに接することもできるし、スターとしての需要に応じられる。そう思って堀はスカウトした、とこれまで伝えられてきた。堀に会ってその点を確かめてみると、「あれは誤解されて伝わっているんですよ」と苦笑しながら、ドル箱スターの去った今、こう語る。「〝ホリプロ三人娘〟をつくるのがねらいでその員数を合わせるために入れたのです」(『潮』1980年12月号より抜粋)
月刊『潮』が見た60年 1971-1975年を読む
・肩書は基本的に掲載当時のものです。また、一部敬称を略しています。
・一部、現在では不適切な表現がありますが、時代背景を尊重し、そのまま引用しています。
・一部、中略した箇所は/で表記しています。
・表記については、編集部で現在の基準に変更、ルビを適宜振り、句読点を補った箇所があります。