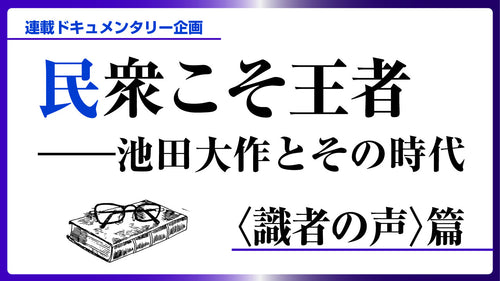月刊『潮』が見た60年 1971-1975
2023/03/31わが同志観
三島由紀夫(作家)
私がこうした自己の体験に根ざす実感に基づいて、同志愛、団結、連帯という時に、いつも感じざるを得ない躊躇は、「われわれ」という言い方である。なぜなら、「われわれ」という感覚には、欺瞞と自らの個人的行為における飛躍があり、その場合、必ずと言っていいほど、ある固定化したような装いを持つ〝人間と人間との関係〟への無原則、無前提の陶酔があるというのが私の持論である。(『潮』1971年2月号より抜粋)
寅さん生みの親もつらいよ
山田洋次(映画監督)
手塩にかけた「男はつらいよ・奮闘篇」の寅さんは、私の許を離れ、おなじみのチェックの背広を肩にひっかけて、またまた全国のスクリーンへと旅たった。今まで、いつも片思いで振られてばかりいた寅さんだが、今度は東北から上京してきた花子に、初めて惚れられる。さて、どんな泣き笑いが待ち受けているだろうか。寅さんは、こっけいで、そそっかしい男である。しかし、胸にジーンとくる温かい心をもっている。義理と人情に厚いのである。(『潮』1971年6月号より抜粋)
公害―この苦海の淵に立って
松田道雄(評論家) 石牟礼道子(作家)
松田 石牟礼さんの『苦海浄土』という本を拝見して、私がいちばん感じるのは、犠牲になった人たち一人一人の人間が、ひじょうにはっきりと書かれている。そのために、公害病というと、きわめて広範囲の、一般化した病気というふうに受けとめられている風潮があるけれども、じつは一人一人の人間が、それぞれが自分の人間としてのいちばん大事な部分を傷つけられていること、それがたいへん鮮明に書けていると思います。それはやはり、人間をていねいに観察するという石牟礼さんの厳しい目が、これは許されないほどひどい害だと、一人一人のもっとも大事な部分が、何とむごくこわされていくかを凝視している。だから読む人に問題がよくわかるんです。
石牟礼 隣はうちよりいいものを食っているとか、家のどこを改造したとか、つまり家族社会、地域社会では離れたところより、すぐ隣がいちばん比較の基準になりますね。あの水俣病のなかにどっぷり浸かっていますと、教養とか知性とか、一般的に肯定されているものをぜんぶ引っぺがしてしまっても、なおかつ人間の持っている原質のさまざまが見えてまいります。ほんとにつらいんですよ。お互い同士が助けあわなくてはどうにも生きていけない状況にあって、しかもなお引き裂けますから。(『潮』1971年12月号より抜粋)
日本人と軍隊と天皇
大岡昇平(作家) 司馬遼太郎(作家)
大岡 横井さん(注・横井庄一氏)は28年がんばったが、あれはふつうの人ではとてもできない。ひと月だってできないな。とくに、ぼくらインテリにはね。手に職のある人間の強みですね。
司馬 人類として例外の記録でしょうか。人類は一人では暮らせないというのが常識でしょうけど。横井さん、自分の手の技術に引きずられて生きていったんですなあ。精神とか意識とかというより、手がくるくると前へ前へと進んでゆくから、つい生きてしまったという面もあるんでしょうね。しかし、兵隊さんというのは、すごいですなあ。将校さんはだめですね。
大岡 現役の強さね。兵隊の眼から見ないと、日本の元軍隊の特質はわからない。(『潮』1972年4月号より抜粋)
それでも〝正常化〟に反対はできない
久野収(哲学者)
蒋介石の側にしても、日本は宣戦布告をせずに侵略をしているが、向こうは宣戦布告をするわけです。戦争でなく、事変だなどという理屈は、日本の内側だけで通せても、一歩外側へ出れば、誰も認めはしない。全く虚妄です。だから日本が宣戦布告せずに侵略戦争をやったという行動に対して、ものすごく責任を感じなければいけないということをいいたいのです。(『潮』1972年10月号より抜粋)
※中国文学者・竹内好氏との対談のなかで。
上野のパンダは週休二日制です
鮫島宗一(上野動物園・西園飼育係長)
ジャイアント・パンダが、上野動物園にやってくる――昨年の9月29日、日中国交正常化の共同声明が調印された席上、二階堂官房長官が記者会見で「中国人民から日本国民へ、パンダのオス、メスひとつがおくられます」と発表されて以来、私たち関係者は期待に胸をふくらませていた。/日本各地の大きな動物園が、ぞくぞくと受け入れの名のりをあげた。スモッグに汚染され、日に日に環境破壊がすすむ大都会の真ん中はパンダ飼育に適さないという声も高く、私たちは落ちつかない日々をおくっていた。そんなある日――正確にいうと10月20日――二階堂官房長官を通じて、正式に上野に決定の知らせがもたらされた。この決定に、動物園の関係者全員が色めきたったのは、いうまでもない。(『潮』1973年3月号より抜粋)
〝開発〟の大罪と住民運動の原点
色川大吉(東京経済大学教授)
いま日本全体でどれくらいの数の住民運動が起こっているだろうか。一説には、ホット・ラインに達しているものだけで3000件、それに近いものを合わせたら10000件はあろうといわれている。それらの住民運動のかかえている内容は複雑多様だが、しかし、この10000件という数字は、江戸時代全期の百姓一揆の件数を上まわる数で、民衆の直接的な運動としては、大変なものだといわざるをえない。(『潮』1973年9月号より抜粋)
金芝河(キム・ジハ)が語る金大中事件
太刀川正樹(ルポライター)
韓国の前大統領候補金大中(キム・デジュン)氏が8月初旬、東京のホテル・グランドパレスから、白昼、何者かの手によって拉致されてからすでに2か月たつ。ソウル市内の東橋洞(トンギョドン)にある自宅に戻って数日後から現在にいたるまで、金大中氏の消息はまったく不明である。内外の友人、報道関係者との接触も完全に遮断されており、彼がほんとうに健康であるのか生命の安全が保障されているかどうかも危ぶまれている。当初予想されていた金大中氏の早期再来日も可能性が薄れ、現在の〝幽閉〟状態は当分つづくものと思われる。(『潮』1973年11月号)
生還した息子、寛郎に贈る
小野田種次郎(小野田寛郎元少尉の父)
寛郎が羽田に着いたとき、世間の人は、私が息子にくらいついて泣く期待があったようです。/ある方が、私のもとにまいりまして、息子さんが羽田に着いたさいのテレビの総電力量は860万㌔ワットで、これは浅間山荘事件と美智子妃の結婚式のときの電力量を合わせたものに匹敵するといっておりました。私はその話を聞いてあらためて息子にくらいついて泣かなくてよかったと、しみじみと思いました。/こんないい方をしますと、せっかく息子のために盛大に出迎えてくださった方々に、申しわけない気もいたしますが、二度死亡通知を受け取り、今度は確実に息子の無事がわかり、今こうして自分たち夫婦が機を待つまでの間には、当事者にしかわからない、ことばには尽くしえない気持ちの整理があったからです。(『潮』1974年5月号より抜粋)
主人公と同化した読者に驚く
ちばてつや(漫画家)
力石が死んだときの反響は自分でも驚くほど大きかった。漫画の主人公が死んだのに、つまり、これはフィクションの世界だから、葬式なんて関係ないんだけど、力石の葬儀まで行うことになった。/劇画といえども恐いという気がします。その影響力のほどを考えると、やたらなことは描けないという気持ちがします。/フィクションの世界だとわかっているはずなんだけど、主人公に同化してしまっている。あるいは、矢吹ジョーにほれて、他の男性が好きになれない、という人もいる。現代には、どこか、自己の生を燃焼させるものがないのでしょうか。思わず、私も考えこんでしまいます。(『潮』1974年11月号より抜粋)
人間を複合汚染から救えるか
有吉佐和子(作家)
「複合汚染」というテーマは、最初『朝日新聞』には抵抗があり、そんなものを人が読むだろうか、という考えがあったらしいのですが、私は「読ませてみせます。書きたいものを書かせてください」とお願いしました。いまいちばん心外なのは、時代の先取りをする作家だといわれることで、複合汚染に関していえば、10年も20年も前から危機の現状を叫んでいた運動体というものがあったのですから。それは私も学びつつ読んでいたものの一人でしたが、ある時点で大きな疑問につきあたりました。これだけ重要な問題になぜ人々はもっと関心をもたないのかということです。外国人の友人からも、日本人はどうしてのんきにしているのだろう。汚染の問題について、あたかも来たときはしようがないのだという地震と同じようなあきらめ方をしている。これは防げる問題なのに、そういう考え方をなぜしないのかといわれました。(『潮』1975年9月号より抜粋)
※大阪市立大学教授・宮本憲一氏との対談のなかで。
実在した第三の原爆投下命令
柳田邦男(評論家)
なぜ私が3発目の原爆投下計画に関心を持ったか、/私はこの数年来、広島のあるドキュメントの執筆をしてきたのだが、その取材の過程で、広島、長崎への原爆投下は日本に対する警告を狙いとしたものであったのか、それとも戦略戦術の両面からどんどん使おうとしたものの単なる第1発と第2発だったのか、という基本的な問題について疑問をいだき、いろいろ調べていたからであった。原爆投下が日本の戦争指導者に与えた影響がいかに大きかったか、とりわけポツダム宣言受諾にさいしていかに大きな動機となったかということについては、すでに数々の記録や書物で明らかにされているが、同時に、一般国民に与えた心理的影響もきわめて甚大なものであった。(『潮』1975年9月号より抜粋)
わが友・児玉隆也の死
亀海昌次(グラフィックデザイナー)
児玉隆也は、死を怖れていた。それは、憤怒という感情と表裏一体をなしている死の怖れだった。女房子供は無事でいられると思うのか――に始まって、身のためにならないから手を引け、といった電話が、このところ、相次いでいた。その電話をとるたびに、やり切れないような憤りが、児玉の胸を重くさせた。だが、もっと別に考えておかなくてはならないことがあった。それは、脅迫電話にある「身のためにならない」ことが、起こりうる可能性についてであった。たとえば交通事故のかたちを装って――追突でもされると一巻の終わりだからなァと、考えたりしたのだった。田中金脈の記事が、連日、新聞にのりはじめたある日、児玉は大きな包みを持って池袋の喫茶店「K」に向かっていた。その包みは、『田中角栄研究――淋しき越山会の女王』の資料のすべてだった。田中政権が崩壊しないと、本当に俺は危ないかもしれない――という思いが、この資料をある人物に預ける動機になったのだった。(『潮』1975年10月号より抜粋)
・肩書は基本的に掲載当時のものです。また、一部敬称を略しています。
・一部、現在では不適切な表現がありますが、時代背景を尊重し、そのまま引用しています。
・一部、中略した箇所は/で表記しています。
・表記については、編集部で現在の基準に変更、ルビを適宜振り、句読点を補った箇所があります。