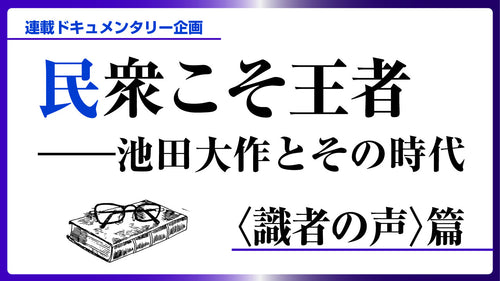月刊『潮』が見た60年 1966-1970
2023/03/31
「天皇家」の将来を考える
会田雄次(京都大学教授)
天皇は、国民の注視の中にあって、自らの行動によって、完全無私を実証しなければならない。そういう国民の期待に応えねばならない。私はそれを期待というより残酷で無慈悲な要求だと思う。超人的な努力を重ねねばならないからである。一般の説教家のように口先だけでごまかすわけにはいかない。日常座臥、どのような些事にも、その理想をもたねばならないからである。(『潮』1966年1月号より抜粋)
テレビ時代の思想
大宅壮一(評論家)
新聞においては、文字というもの、紙というものが、浸透するうえにおいて、妨げになっていたのですね。字を覚えなければならない。それから紙、ものを買わなければいけないということ、これが文化を大衆化するうえに妨げになった。ところがテレビができると、文盲率がいかに高くとも、ことばと視覚に訴えるでしょう。一種の動物実験みたいなものです。くり返しくり返し、しつこく刺激を与えれば……。スイッチ・マスコミだから、24時間ぶっ通しに一つのテレビを流すこともできるし、気に入らないのはテレビのスイッチを切ってしまうこともできる。政治のプレッシャーというのは、非常にかけやすいですね。それだけに悪用しようと思えば、いくらでも悪用できる、時の権力者が。(『潮』1966年6月号より抜粋)
※作家・安部公房氏との対談のなかで。
溝呂木老人とビートルズ
林雄二郎(経企庁経済研究所長)
大人の人たちがビートルズファンに対して、やれ彼らは白人コンプレックスの見本だとか、いやあれはイギリスの女王から勲章をもらった立派なイギリスの青年なんだから、日本の若ものたちが歓迎する気持ちもわからんではないとかいろんなことを言う人がいるが、私に言わせれば、いずれもトンチンカンもトンチンカン、まったく見当はずれの批評だと思う。私の感ずるところでは、要するにこれは理屈ではないのである。はっきり言えることは、この若い人たちにもっとも生きがいを感じさせる〝なにか〟がビートルズにあったのであろう。それは白人コンプレックスでもなければ、女王の勲章でもない。そんなことはぜんぜん関係がないのである。(『潮』1966年9月号より抜粋)
腐敗政治に怒る
石川達三(作家)
ここ10年ばかりのあいだに、いろいろな汚職があった。もしこれがフランスだったら、革命でも起きかねまじいことじゃないか。日本の民衆はじつにおとなしい。というより、無関心なのか、民衆自体が腐敗しているのか、ほんとうに怒りを燃え立たせることが少ない。汚職の記事が出ても、あアまたやりやがったというくらいで、だまって耐えている。まことに歯がゆい。それで、たとえばアメリカの原子力潜水艦が入港したといって、ワッと大騒ぎする。もっと身近な問題があるのに、あまり騒がない。/こういう状態じゃ、いつになったら腐れ縁を断ち切ることができるのか、怪しいと思うな。これを是正しようという力がないんだから。(『潮』1966年10月号より抜粋)
それはかつて“県”だった
吉村昭(作家)
取材をしている間、私は、何度も嗚咽のこみあげるのをおぼえた。斬り込みをした小学生の話、頭を刈り、タスキをかけ、そして爆雷を背にして戦車群に向かっていた娘たちの話。「なぜ、君たちは死んだのだ」と、私は、その都度胸の中で問いかけた。戦後、遺骨収拾がひそかにおこなわれたが、或る洞穴で落盤 した土を掘り起した時、完全に白骨化した少女の遺体が出てきた。その右手には、錆びた手 榴弾がにぎりしめられていた。その少女は、戦闘中も死の直前も、常に祖国のことを考えつづけていたにちがいない。日本人として、沖縄県民として、祖国を郷土を死守しようと願っていたはずである。しかし、こうした死の犠牲は、どのような形で報われたのか。それは、依然としてつづく異民族の支配であり、日本内地の人々のほとんど無視に近い態度であったのである。(『潮』1967年11月号より抜粋)
日本人の国家意識
高橋和巳(京都大学助教授)
ぼくたち学生時代、国家をこえる思想として、マルクス主義を学ぼうとしました。しかし、プロレタリアートの国際連帯というのも、20年たってみますと、結局は、ロシアが自分の祖国を守るための、周辺の国に要請していたような面があったことに気付くわけですね、ハンガリー事件とか、中ソ対立とかいうようなことでそういう幻想は破れてしまったでしょう。(『潮』1967年秋季号より抜粋)
※京都大学教授・貝塚茂樹氏との対談のなかで。
思索について
谷川徹三(哲学者)
トインビーもいまの未来社会の問題については、技術文明というものの将来に対して、ある不安を持っているわけです。宗教というものの大きな役割を信じているわけなのです。つまり、宗教というものは、人間と人間との関係をうまく調整するものとしてトインビーは考えている。こういう方向にもし宗教が今後も進んでいけば、そこから21世紀の世界の持っている、つまり科学技術の文明というものの持つ、さまざまな害悪を宗教が緩和することができる。そういう考えを持っているわけなのです。(『潮』1968年1月号より抜粋)
※物理学者・湯川秀樹氏との対談のなかで。
ベトナム和平のための提案
ロバート・ケネディ(米上院議員)
国際社会の歪みが、戦争を生む。しかし戦争の正当性をいかに主張しようとも、それは、たった一人の少年に加えられる苦痛と苦悩を消し去るものではない。ベトナム戦争は歴史を画する重大な出来事であり、多くの国の力と利害がかけられている。しかしそれはまた母と子が、理解の枠を超えた国から送られて来た機械の砲火による殺りくにおそれおののく空しい瞬間でもある。/そこでは、若者たちにも、1日として、平和のやすらぎは与えられず、家族たちは、常におそれの中で暮らしている。/我々が、ベトナム問題について、喋り、行動するとき、認識しておかねばならないのは、こうした残酷な事態の責任の一端がつねに我々にあるということである。国家としてだけではなく、個人として、私にも、貴方にも責任がある。(『潮』1968年2月号より抜粋)
イタイイタイ病に捧げる
萩野昇(萩野病院院長)
昭和32年、私は富山県医学会に鉱毒説を発表した。イタイイタイ病の原因は、環境調査をした結果、神通川に関係あると判断したのである。しかしすべての研究機関はこの川水を「白」といった。「鉱毒説を唱える学者がいるが、これは何ら根拠のないことである」と学会でたたかれた。私の苦難の時期が始まった。協力者もなく、ひとりさみしくたたかった。/昭和43年5月8日は記念さるべき日となった。厚生省から結論が出された。イタイイタイ病の原因はカドミウムであり、そのカドミウムは神岡鉱山の工場廃水から流れ出たものであると発表された。日本における〝公害病〟の第一号となったのだ。(『潮』1968年7月号より抜粋)
光りはあったのだ
竹内好(中国文学研究者)
9月8日の創価学会学生部総会で、会長池田大作氏が講演された。講演の内容は多岐にわたっているが、その中心となる最重要部分で、量的にも過半を占めるものは、いわゆる中国問題についての見解の表明である。いま、この部分だけについて、もとめに応じて感想を述べる。私は評論家を廃業したので、評論という形では何も語りたくない。しかし池田氏の発言は、たとい注文がなくても、感想を記しておきたい気がしていたので、たまたま提出された誌面を、よろこんでお借りすることになった。/池田氏の講演をよんで私は、池田氏が戦争の危機をひしひしと感じていられるのがわかった。ここに先憂の士がいる。私は悲観論を変えたわけではないが、一縷の光りを認めたことは告白したい。(『潮』1968年11月号より抜粋)
太田八重子さんの気持ちはわかる
美空ひばり(歌手)
昔は母と二人でよく泣いたものでした。でも結局、週刊誌は〝売らんかな〟ただそれだけではないでしょうか。だから、いまはそうした一部の週刊誌を無視しています。読んだこともありません。週刊誌を見たファンが心配してよく電話やお手紙をくださいますが、いつも「週刊誌を信じるか、美空ひばりを信じるか、二つに一つしかありません」とご返事しています。(『潮』1970年2月号より抜粋)
ファンから貰った4500万円
長嶋茂雄(プロ野球選手)
私の生き甲斐は、何といっても高いお金を払って観に来て下さる何百万というファンの方に喜んでもらうことに尽きます。「長嶋がんばれ!」の声を背に、ここぞという時に一発出たり、矢のようなライナーをしっかりつかんでアウトにし、ファンの心に強烈な歓びを刻み込むことができたときは、私自身涙が出るほど感激してしまいます。(『潮』1970年3月号より抜粋)
※掲載時の「長島」表記を「長嶋」に統一。
美智子なきわが家の十年
樺光子(故・樺美智子の母)
その渦中で生じた一つの死、それは名も知れず、ひっそりと咲きかけていた野の花のような一人の娘の死でした。けれど何と大ぜいの人の涙が小さな娘の上に流されたことでしたでしょう。それらの人々は、高級サラリーマンを除いた、働く階層の人々であったろうし、権力者と対立した民主主義者、宗教家、そして子を持つ親たち、そうした温かい心の持ち主であったでしょう。それはひたひたと押し寄せ、特になす術もなくいた意気地のない私に対して激励となってあらわれたのでした。そこから「私の十年間」は始まったのでした。/美智子の死の前日に、私との間に静かな話し合いが交わされました。最後に美智子は思いつめたようにいいました。「お母さんは私さえ家にいれば、それで満足に思うの? 私の友だちが沢山デモに行っても、私さえ行かなければそれでいいと思うの? そんなつまらないことを考えないで、どうぞお母さんも理想をもって生きてちょうだい」。その言葉を聞いたときの衝撃を、私は生涯忘れないだろうと思います。(『潮』1970年6月号より抜粋)
・肩書は基本的に掲載当時のものです。また、一部敬称を略しています。
・一部、現在では不適切な表現がありますが、時代背景を尊重し、そのまま引用しています。
・一部、中略した箇所は/で表記しています。
・表記については、編集部で現在の基準に変更、ルビを適宜振り、句読点を補った箇所があります。