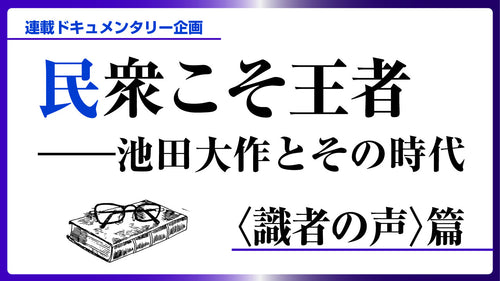ロシアとウクライナに届け!「百万本のバラ」に込めた想い(加藤登紀子さん)
2023/04/20ラトビア、ソ連、そして日本で歌い継がれてきた「百万本のバラ」。
ロシア語歌詞を日本語に訳し大切に歌い続けてきた加藤登紀子さんに、「百万本のバラ」が世界の多くの人々に愛される理由と、今こそ伝えたい平和への願いをお聞きしました。
(『潮』2023年5月号より転載。取材・文=関川 隆 著者近影=水島洋子)
********

ソ連で大ヒットした「百万本のバラ」
1989年11月、ベルリンの壁が撤去された。その年の大晦日、NHK紅白歌合戦で、加藤登紀子は真っ白なバラのドレスを着て「百万本のバラ」を歌っていた。「ようやく世界がひとつになれる」との喜びを込めて――。そして91年、独立運動が激化したソビエト連邦は崩壊した。しかしその後の世界は、決して諸手を挙げて喜べるものではなかった。
「とにかく一刻も早く戦争が終わってほしい……。それだけです」
ロシアとウクライナの戦争について聞くと加藤はそう語り、しばらくして言葉を継ついだ。「国と国のメンツをかけた戦いで泣き、苦しむのはいつも民衆です。今回の戦争の被害者はウクライナ人であり、ロシア人でもあります。ロシアとウクライナの国境は、為政者が長い歴史のなかでさまざまなかたちで引いてきました。でも私にとってそんな国境はどうでもよくて、ロシア人もウクライナ人もともに大切な友人です」
加藤は昨年、新曲に加えて「イマジン」「花はどこへ行った」などの反戦歌、代表曲「百万本のバラ」を収めたアルバム「果てなき大地の上に」をリリースし、売り上げをウクライナ支援のために寄付した。
さらに「百万本のバラ」という曲に込められたロシアとその周辺国の人々の思いに、ハルビンで生まれた自身の人生を重ね、歌の力や平和への思いを綴た『百万本のバラ物語』(光文社)を執筆した。「百万本のバラ」はもともと1980年代半なかばにソ連で大ヒットした曲だ。この曲を日本で耳にした加藤が日本語に訳し、持ち歌にした。貧しい絵かきが女優に恋をし、街中のバラを買い、100万本のバラで広場を埋め尽つくす。そんなロマンチックな熱愛、それも失恋の曲である。
この曲がなぜソ連で熱狂的に支持されたのか。ソ連の歴史においてどのような意味をもつのか。この曲を歌い始めたころ、加藤はよくわかっていなかったという。
「失恋だから悲しい歌のはずなのですが、歌うとなぜか会場が高揚感に包まれ、盛り上がるんですね。それがいつも不思議でした。でもそのうちこの歌には、たとえ失敗しても自分の思いをしっかり表現して伝えることが大事なんだという、ポジティブなメッセージが込められていることに気づきました」
ラトビアの子守唄にロシア語の歌詞がつく
「百万本のバラ」はもともと「マーラが与えた人生」という題のラトビアの子守唄だった。作詞したのはラトビアの反体制派詩人、レオンス・ブリエディス。マーラとは女神の名である。「神様あなたは、かけがえのない命を娘にくださいました。でも、どうしてすべての子供たちに幸せを運んでくることをお忘れになったのですか?」。そんな歌詞には、ラトビアを支配してきたソ連への抗議の念が込められている。
「作曲したのはソ連からの独立運動(1989年)を指揮し、後にラトビアの文化大臣を務めたライモンズ・パウルスです。私はあの独立運動で、自由を求める民衆が手をつないで戦車の前に立ちはだかり、広場を埋めている風景をテレビで見ました。その時、『百万本のバラ』の作曲者、パウルスの名を耳にして驚きました。そして今、目にしている光景こそが百万本のバラなんだと気づきました」
その後、ラトビアの文化大臣としてパウルスが来日。その歓迎会で加藤は、パウルスのピアノ演奏に合わせて「百万本のバラ」を歌った。彼女は、「百万本のバラ」がもともとラトビアの子守唄だったことをこの時初めて知ったという。
「かつてソ連の放送局では、ロシア語の歌しか放送できなかったんです。そこでラトビア語の歌の多くはロシア語に翻訳されました。そして『マーラが与えた人生』にロシア語の歌詞をつけたのが、アンドレイ・ボズネセンスキーという反体制派の詩人です。彼は後にゴルバチョフの右腕として、ペレストロイカを後押しした人物です」

音楽が弾圧されたスターリン時代
ボズネセンスキーはこの歌の歌詞を、フランスの女優に恋したジョージアの画家、ニコ・ピロスマニを主人公にした恋物語にしつらえた。
「ニコ・ピロスマニは大酒飲みの貧乏画家で、ピカソにも大きな影響を与えた人です。彼の故国であるジョージアもかつてソ連の一部でしたが、1991年に独立します。その後、ロシアから軍事侵攻を受けるなど、ウクライナと似た歴史を辿っています」
ボズネセンスキーによって愛の歌となった「百万本のバラ」をソ連で歌い、大ヒットさせたのが反骨のロックシンガー、アーラ・プガチョワだ。ソ連ではメッセージ性の強い歌を歌う歌手は迫害され、国外逃亡を余儀なくされることが多かった。しかし彼女は奇跡的に国内にとどまることができ、国民的歌手として圧倒的な支持を得ていた。
「そんな彼女も昨年ウクライナ戦争が始まると、反戦を唱えて出国しています。いずれにしろ『百万本のバラ』には、このようなソ連末期のさまざまな国の人々の祈り、願い、叫びが込められているんです。昔のソ連だったら、まっさきに禁止されていたでしょう。ゴルバチョフによる改革の流れのなかだったからこそ大ヒットし、ソ連全域に広がったのです」
かつてソ連では、スターリンが自由な芸術表現を厳しく弾圧した。西側諸国の音楽や、民謡以外の流行歌を歌うことは禁じられていたのだ。
「あそこまで厳しく音楽を弾圧した国、時代は珍しいと思います。裏を返せば、スターリンという権力者は、歌や音楽が人々を結びつけ、鼓舞し、自分たちの脅威になることをよく理解していたのでしょう。でもどんなに弾圧されても、旧ソ連の人々は歌や音楽を手放しませんでした。財産や土地を没収し、歌を禁止することはできる。でも心のなかで歌うことまで妨げることはできません。むしろ禁止された歌ほどよく歌われ、次世代へと受け継がれていったのです」
多国籍の人が共生するハルビンでの暮らし
「ロシア人やウクライナ人ほど、音楽や歌が好きな人たちはいない」
そう語る加藤は、満州引き揚げ者の森繁久彌が記したあるエピソードを話してくれた。日本が敗戦した後の満州にて、ソ連兵が略奪に入った家でチェロを見つける。ソ連兵は「音楽家の家を荒らすつもりはなかった」と詫び、「どうか一曲弾ひいてほしい」と懇願する。チェリストが一曲弾くと、その兵士は涙を流して喜んだ。その後、音楽を通じたソ連兵との交流が始まった。そんな話だ。
このエピソードを聞いてすぐに思い浮かんだのが、『百万本のバラ物語』にも登場する加藤の父、幸四郎だ。彼は1929年にハルビン学院に入学し、ロシア語を学ぶ。歌手志望で、音楽とお酒が大好きだった。ハルビンで大勢のロシア人の友人をつくり、日本に帰ってからはレコード会社で働く。さらに副業でロシアンレストラン「スンガリー」を経営し、日本とロシアの友好に大きく貢献した人物である。
加藤はそんな幸四郎と母・淑子の次女として、43年にハルビンで生まれた。2歳8カ月の時に日本に引き揚げたが、ハルビンを第二の故郷として生きた両親に育てられたことは、彼女の人生に決定的な影響を与えている。
ハルビンはもともとロシア皇帝のニコライ二世が、極東進出の足場として築いた街である。街の建設のためにウクライナ人、ポーランド人、ユダヤ人が強制的に移住させられた。その後、日露戦争に勝った日本が南満州鉄道の経営権などを得たため、多くの日本人が暮らすようになる。ロシア革命によって帝政ロシアが滅びると、多くのロシア人貴族がこの地に亡命した。
そのような複雑な国際情勢を背景に、多様な国籍の人々が共生していたハルビンでの暮らしについては、『百万本のバラ物語』に詳しく描かれている。そこには戦争や国に翻弄されながらも、国境や民族を越え、隣人としてともに助け合い、音楽やお酒を楽しむ、そんなたくましい庶民の姿があった。
〝荒海〟の父が開店したロシアンレストラン
なぜ加藤は、当時の記憶は残っていないハルビンでの両親の生活を、著書に活き活きと描けるのか。それは幸四郎がハルビンでの暮らしを再現すべく、新橋や新宿などで経営していたロシアンレストラン「スンガリー」での思い出があるからだ。
「私は中学の頃から、店に来るロシア人と家族のように過ごしていました。みなさん、さまざまな事情を抱えていて、立場の違いや対立もあったことでしょう。でも私がこの店で学んだことは、人はいい音楽とおいしいお酒、料理があればみんな笑顔になり、仲良くなれるということ。私は世界平和のためには『自由 平等 博愛』という抽象的な言葉より、『音楽 料理 酒』の三色旗を世界共通のシンボルとして掲げるべきだと思っています(笑)」
幸四郎がレストランを経営したのは、日本に亡命し、行くあてのないロシア人に仕事を与えるためだった。そんな幸四郎という人物の魅力的なエピソードも、『百万本のバラ物語』にはさまざま綴られている。
なかでも痛快なのが、1986年にキーウで予定していたコンサートを、チョルノービリ原発事故が起きたため、加藤が中止した時のこと。幸四郎は「お前はそんなつまらん奴やったんか! こんな時だからこそ行きます、となぜ言わぬ」と加藤を一喝する。さすがにコンサートは決行しなかったが、その時以来、加藤は今までにない覚悟で毎回の公演に臨むようになった。
「父は楽しいことが大好きで、やりたい放題やっていた人です。うちの家族の〝船長〟は母で、父はしょっちゅう荒れている海(笑)。何度も沈没しそうになったけど、我が家が何とか沈没せずに済んだのは、母のおかげです。レストランも父が勢いで始めたもののうまく回らず、結局は母の切り盛もりで何とか運営できていたんです」

世界中の人たちと歌う喜びをわかちあう
加藤の母、淑子の人柄がよく伝わるエピソードが『百万本のバラ物語』のなかにある。加藤が5歳、一家が板橋区で暮らしていた時のことだ。ある日、キティ台風で台所の屋根が吹き飛んでしまう。すると淑子は嘆くこともなく空を見上げ「トコ(登紀子)、見てごらん、ほら青空、気持ちいいよ!」と晴れやかな顔で言ったという。
「あの時の青空は、今も私の記憶に鮮明に残っています。我が家はみんな、コサックのような移動性気質なんです。ハルビンにいた時もずっと間借り生活で、家をもったことはありません。同時にハルビンで生まれた私には、どこか自分が純粋な日本人ではないような感覚があります。だから逆に日本的なものへの憧れやコンプレックスも、すごく強かったんです」
そんな加藤は、日本人歌手としては早い段階から外国でのコンサートを行っている。1968年に初めてソ連での演奏旅行を行い、ラトビア、レニングラード、ベラルーシなどをまわった。81年には中国の北京やハルビンでコンサートを開いた。
「いろんな国に行きましたが、ほとんどの国が一度は日本と戦争をしています。ハルビンやアジアの国々の人にとって、私は侵略者側の人間です。だからいつも私なりのやり方で謝罪し、和解したいとの思いで接してきました。その国の文化や音楽に敬意を持ち、その国の言葉で必ず歌うようにしました」
加藤はステージで歌うだけでなく、ときには公園やスラム街で、そこにいる人たちと、ともに歌う喜びをわかちあった。その経験から、歌は国境を越えて人と人の心を結びつけると確信している。
「第二次世界大戦末期、国を守るためにたくさんの日本人が亡くなりました。国は本来、人のためにあるはずなのに、戦争になれば国のために人の命が犠牲になる。それなら人と人が国境線を越えて、心をつないでいくしかない。そのために、歌は大きな力になるはずです」
できることを見つけ一歩でも前に進む
歌は国境を越える。国を追われ、強制的に移住させられ、アイデンティティーに深い傷を負った人たちも、自分たちの歌を絶対に手放さなかった。ハルビンで生まれた加藤にとって、世界中の歌を訳して歌い、現地の人とともに歌う行為は、自身のアイデンティティーを探す旅でもあったのだろう。
「国境は長い歴史のなかでひんぱんに変わっています。ロシアとウクライナが戦争しているといっても、そこで暮らす人たちは文化も宗教も民族もさまざまです。多様な宗教や民族、文化の人たちがときに衝突し、仲直りし、なんとかやってきたのが今の世界です。ロシア人とウクライナ人が人間同士、争う必要なんてまったくないんです」
もちろん加藤は、現実をただ楽観視しているわけではない。『百万本のバラ物語』のエピローグで、強い批判にさらされたゴルバチョフの晩年に触れているが、理想を掲げ、社会体制や時代の流れを変えることの難しさを、誰より痛感している。
「だからといって、できることは何もないと嘆くのではなく、今ここで自分にできることを見つけ、一歩でも前に進む。失敗を恐れず、夢や希望を絶対に諦めない。それが『百万本のバラ』に込められたメッセージです。人々を分断する力が世界に満ちている今だからこそ、私たちには人と人の心をつなぐ歌が、もっともっと必要です」
ハルビンで生まれ、ロシア人にもウクライナ人にも友人がいる加藤が、日本語によって新たな命を吹き込んだ「百万本のバラ」。この歌はこれからも国境を越えて、多くの人に歌われ続けていくことだろう。 (文中敬称略)
***********
シンガーソングライター
加藤登紀子(かとう・ときこ)
1943年ハルビン生まれ。65年、第2回日本アマチュアシャンソンコンクールに優勝し歌手デビュー。88年、90年にカーネギーホールで公演するなど海外での活動も多く、現在も国内外で活発にコンサート活動を続けている。
お知らせ
百万本のバラ物語(光文社)
2022年12月21日発売
定価:1,760円(税込み)
ISBN 978-4-334-95346-1
ノンフィクション、学芸
判型:AB判ソフト