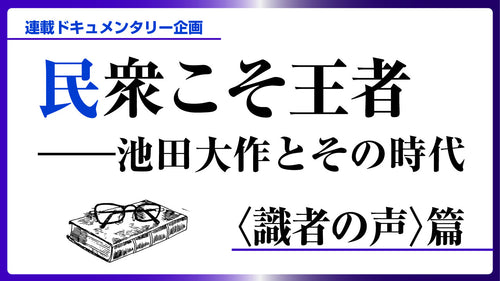連載小説「1+1」(ワン プラス ワン)
第2回 アゲマキの網焼きと缶チューハイ、凍らせたレモン添え
2023/07/20
大好評だった連載第1回に続いて、第2回目となる「アゲマキの網焼きと缶チューハイ、凍らせたレモン添え」も潮プラスで特別公開します。
「ペアリング(食べ物と飲み物の組み合わせ)」をモチーフにした直木賞作家・井上荒野さんによる、心に残る食の風景を描く掌編小説です。
(イラストレーション=進藤恵子)
***********************
***********************

沙百合が朝食を食べ終えた頃、泰三はのそのそと起き出してくる。定年後、シニア社員として八年間働いたが、それも終わって家にいるようになると、ほとんど何もしなくなった。最近は夜遅くまでパソコンに見入っていることが多い。
「おはよう」
と沙百合が声をかけると、泰三はふたりの息子──今年四十になる──が十代の頃そうだったように、顎だけで返事をした。今日も暑くなりそうだ。狭い庭に面した南の窓が、すでにじりじりと照りつけられている。
「よく起きられたわね」
沙百合はそう言ってみる。
「朝だからね」
という返事がある。泰三はカウンターの向こうのキッチンへ入っていき、コーヒーサーバーに出来上がっているコーヒーをカップに注ぎ、カゴの中からデニッシュを取り出して皿に載せた。勤めを終えてから、その程度のことは自分でするようになった。
「朝方まで起きてたわよね」
ダイニングテーブルで向かい合う。子供たちがそれぞれの家庭を持ってこの家を出ていってから、チェリーの一枚板のこのテーブルは、夫婦ふたりには大きすぎて、向かい合うたびに余白が気になってしまう。
「朝方は大げさだよ、ちゃんと寝たよ」
嘘ばっかり。沙百合は胸の中で言った。かつては息子の部屋だった二階の洋室が今は「書斎」ということになっていて、泰三は毎晩そこにこもっている。前夜、というか今日、彼が寝室に入ってきたのは空があかるくなってからだった。隣のベッドがいつまでたっても空っぽなのが気になって沙百合はうまく眠れなかったから、ちゃんと知っているのだ。
「甘いな、これ」
と泰三が言ったのはデニッシュのことだった。沙百合がパートで通っているベーカリーから売れ残りを持ち帰ってきたものだ。
「この前、惣菜パンを出したら、朝は甘いのが食べたいって言ってたじゃない」
「そうだっけ」
沙百合は、自分のカップとパン皿を持ってキッチンへ行った。必要以上に水流を強くして皿を洗う。認めたくないことだけれど、最近の泰三がきらいだった。
カフェは若者たちで大繁盛で、エアコンが稼働していてもじっとりと蒸し暑く、女三人はそれぞれに扇子で顔を扇いだ。
午後三時過ぎ。今日は俳句結社「水軍」の句会の日で、会の前に三人でお茶をするのが慣いだった。沙百合、春江、知世。全員が六十代後半で、定年退職した夫を持つという共通点がある。
「ユーチューブよ、それ」
コーヒーゼリーに垂直にスプーンを突き刺しながら、知世が言った。
「定年後に何していいかわからなくなって、ユーチューブにはまる男の人、多いらしいよ。ユーチューバーがね、炎上商法っていうの? あることないこと垂れ流してるんだって。それで陰謀論の信者になって、人格変わっちゃったりするんだって」
「陰謀論って?」
春江が聞く。
「陰謀論っていうのはつまり……年寄りだけが死ぬワクチンが開発されてるとか、食糧危機が来る前に人口を減らそうとして人工的に大地震を起こしてるとか……」
「何、それ」
春江が顔をしかめ、
「やめてよ」
と沙百合も苦笑した。うちの夫、最近夜通しパソコン見てるのよね、と沙百合が打ち明けたことから、そんな会話になったのだ。やっぱり言うんじゃなかった。
「そういう人もいるって話。あ、ほら。見て」
知世が店の入口のほうにふたりの視線を促した。十朱遥子と広渡拓郎、拓郎の娘の茜が連れ立って入ってくるところだった。見られていることに気づいた拓郎が手をひらひらと振り、遥子と茜も会釈した。沙百合たちも慌ててニッコリした。
「家族みたいになってる」
遥子たちが奥まったほうへ行き見えなくなると、知世がヒソヒソと言った。
「最近、急接近だよね、遥子さんと拓郎さん」
春江も言う。
「これで〝水軍〟も落ち着くんじゃないかしら」
沙百合はそう言った。最近の結社内は男女問わず、広渡拓郎の歓心を買う競争みたいなことになっていたからだ。自分たち三人もその競技者の中に入っていなかったわけではなかったけれど――。
「お似合いよね」
沙百合がそう続けると、「まあ、ね」「そうね」と、渋々というふうではあったがふたりも同意した。実際のところは、沙百合は羨ましさでいっぱいだった。広渡拓郎のことは魅力的な人だとは思うけれど、とくべつな感情は持ってはいない。ただ、さっき彼が遥子さんに向けていた眼差しや、それに応える遥子さんの微笑みなんかが、もう自分にはすっかり無縁のものになってしまったのだと、しみじみと寂しくなるのだった。
句会は午後四時から七時まで、コミュニティセンターの一室を借りて行われる。そのあとは希望者だけ、夕食と懇親を兼ねて居酒屋に繰り出す。沙百合はいつものように居酒屋にも参加して、いつもよりも多めに飲んだ。憂さ晴らしというやつだ。といっても少量だったが、アルコールには強くないのでいつもよりほろ酔いになって、家に戻ったのは十時前だった。
泰三はダイニングにいた。あら、めずらしいと沙百合は思ったが、夫の前にはノートパソコンがあった。何のことはない、沙百合がいないから、書斎のパソコンをダイニングに持ってきたというだけのことらしい。パソコンの横には食べ終えた食器があった。夕食は温めれば食べられるものを用意して出かけていた。それを食べながらパソコンを見ていたのか。ユーチューブで陰謀論を傾聴していたのか。沙百合は、自分の料理に泥のようなものをかけられた気分になった。さらに腹が立ったのは、沙百合の姿を見るなり、開いていたノートパソコンを泰三がパタンと閉じたことだった。
「何、見てたの?」
酔いに任せて――というか酔いのせいにして――、ずっと聞けずにいたことを沙百合は聞いた。
「いろいろ」
と泰三は、中学生男子の顔になって答えた。
「ユーチューブとか?」
「まあ、それもあるけど」
「私にも見せてくれる?」
「え? いや…沙百合が見ても面白くないよ」
見せてと言っても見せないわけか。泰三はノートパソコンの蓋の上に両肘を載せた。その動作で何かが決定したように思えた。陰謀論。でなければインターネット越しの恋人とか?
「ユーチューブ 落ちて登れぬ蟻地獄 」
「え?」
「私が作った句。今日の句会で即興で作ったの。わりと評判良かったのよ」
泰三は目を丸くした。必死で返答を考えているようだが何も出てこないらしい。沙百合はダイニングのドアを音高く閉めて、二階に上がった。
喧嘩というほどではなかったが、翌朝の気分は重かった。そんな気分になることは、四十数年間の結婚生活の中でめったになかった。そう、めったになかった、もしかしたらはじめてかもしれない――自分と泰三がずっと、喧嘩らしい喧嘩もない夫婦だったこと、でも今、こんな状態になっていることの両方が、沙百合を落ち込ませた。
「俺、ちょっと出かけてくるから。昼飯はいらない」
泰三はいつもよりさらに遅い時間に降りてきたと思ったら、そう言い捨てて出かけていった。これも今までにないことだった。どこへ、何をしに行くのか沙百合は怖くて聞けなかった。陰謀論を信じる仲間たちのところへ行くのか。あるいは女性に会いに行くのか。
何をしていても落ち着かなくて、沙百合はドラマを観ることにした。韓流ドラマ「愛の不時着」は知世や春江に熱烈に勧められて、泰三の留守中に少しずつこっそり観ている。
どうして「こっそり」なのかといえば、この歳になって恋愛ドラマにうっとりしていることを知られたくないからだった。なんだかあてつけがましいし、まだそういう欲があるのかと思われたくないから。考えてみれば私だって夫に対して、こんなふうに隠していることはあるわけだ。お互い様というよりは、結婚って―― 一緒に暮らした四十数年は何だったのだろうと、どうしたって考えてしまう。
ドラマには貝を焼く場面が登場した。屋外で、地面に大きな蛤のような二枚貝を並べ、ガソリンをかけて火をつけるという豪快な食べかた。貝殻の中に焼酎を注いでおいしそうに啜るヒロインを観て、沙百合が思い出したのは、恋人時代に泰三と行ったキャンプのことだった。
レンタカーにキャンプ用具一式を積んで、九州の下半分を巡った旅。そういう旅がふたりとも好きだった。あれはどこの浜辺だったのだろう──市場で安かったアゲマキという細長い二枚貝を、焚き火の網で焼きながら延々食べた。魚屋のおじさんに教わった通り、貝の殻が開いたら醬油と日本酒をちょっと垂らして、汁ごと啜り込んで食べるおいしさと言ったら! 貝の甘みと磯の香り、網に溢れた醬油の香ばしい香りも移って──。そして貝のお供は、当時出回りはじめた缶チューハイで、氷を詰め込んだアイスボックスの中できんきんに冷やしておいたのをコップに注ぎ、これもきんきんに凍らせておいた櫛形のレモンを浮かべて飲んだのだった。レモンを凍らせて焼酎に投じるのは前夜夕食をとった居酒屋で覚えた。しゃりしゃりしたレモンをときどき齧りながら飲むのが妙においしかったのだ。熱々の貝でほてった口中に冷たい缶チューハイが気持ちよく、貝の風味と混じり合った酒の後口が、また次の貝を呼び寄せた。おいしいね。うん、旨いな。手が止まらないことを何度でも笑い合った海辺の夜。
あんなときもあったのだ、と沙百合は思った。結婚してから子供たちを連れてキャンプに行ったことは何度かあったけれど、彼らが親に付き合ってくれなくなると、それきりになってしまった。
ドラマが終わる頃、「ただいまあ」という声とともに、玄関ドアが開く音がした。沙百合は急いでテレビの電源を切った。これじゃあ夫と変わらないわ。そう思ったが、泰三はテレビのことなど気にもならない様子で、「八月中か九月のはじめくらいで、三日間くらい時間作れる?」といきなり聞いた。なんだか目がギラギラーーいや、キラキラかも――している。
「え? 三日間? なんで?」
「キャンプに行かないか。前に、貝を焼いて食べた浜辺があったろう。あそこがどこだか、やっとわかったんだ。テントや寝袋なんかも、今日見に行って、注文してきた」
「キャンプ……?」
「長崎のどこかだってことは覚えてたんだけど、なかなか絞りこめなくて。どうしてもあの浜に行きたくてさ。ずっと探してたんだ。昨日の夜中に、絶対ここだってとこを見つけたんだ。あの居酒屋もまだあるんだよ。覚えてる? あの、レモンを凍らせてさ……」
「覚えてるわよ」
ぶっきらぼうな、怒鳴るみたいな言いかたになってしまった。あまりにもびっくりしているせいだ。まさにさっきまで自分が思い返していた光景のことを、泰三が嬉しげに喋っている。沙百合はまじまじと夫を見た。鼻の頭が赤いのは、一日キャンプ用品を探し歩いて日に焼けたせいだろうか。ずっと夫を見ていなかったような気がした。実際のところ、見ていなかったのかもしれない。泰三は変わってしまった、と思っていた。でも、今、目の前にいるのは、まごうことなき泰三だった。
「そんな理由で夜通しパソコンを見てたの?」
「そうだよ。ユーチューブで、キャンプしてる人の動画を探したりしてさ」
「なんで教えてくれなかったの?」
「びっくりさせようと思ってさ。びっくりしたろ?」
「びっくりしたわよ」
沙百合はまた怒鳴った。ぷんぷんしていないと泣けてきそうだったからだ。泰三はしてやったりという顔でニコニコしている。こんなサプライズを思いつくような人だったか。夫には、私の知らない部分がまだありそうだ。それはそんなに悪いことではないのかもしれない。
「老妻と も一度行きたしキャンプかな」
「なに、それ」
沙百合は思わず吹き出した。この句もずっと考えていたのだろうか。笑いながら、なぜかテレビの電源を入れてしまった。イケメンヒーローの顔がぱっと画面にあらわれる。ひとつ知ったから、ひとつ教えてあげよう。そんな気持ちになったのだった。

▶︎第一話はコチラ
****************
作家
井上荒野(いのうえ・あれの)
東京都生まれ。1989年「わたしのヌレエフ」でフェミナ賞、2008年『切羽へ』で直木賞、11年『そこへ行くな』で中央公論文芸賞、18年『その話は今日はやめておきましょう』で織田作之助賞受賞。著書に『リストランテアモーレ』『あなたならどうする』『あたしたち、海へ』『あちらにいる鬼』『荒野の胃袋』ほか多数。
作家
井上荒野(いのうえ・あれの)
東京都生まれ。1989年「わたしのヌレエフ」でフェミナ賞、2008年『切羽へ』で直木賞、11年『そこへ行くな』で中央公論文芸賞、18年『その話は今日はやめておきましょう』で織田作之助賞受賞。著書に『リストランテアモーレ』『あなたならどうする』『あたしたち、海へ』『あちらにいる鬼』『荒野の胃袋』ほか多数。