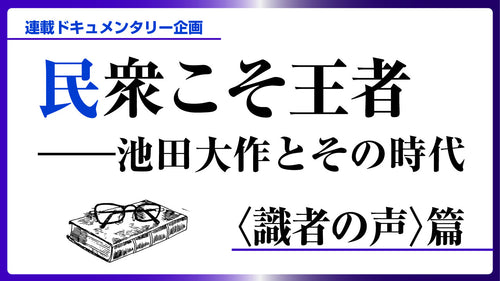連載小説「1+1」(ワン プラス ワン)
第1回 鱚のフライと白ビール
2023/06/20
「ペアリング(食べ物と飲み物の組み合わせ)」をモチーフに、 直木賞作家・井上荒野さんによる、心に残る食の風景を描く掌編小説が 7月号からスタートします。第1回は「鱚(きす)のフライと白ビール」です。
(イラストレーション=進藤恵子)
***********************

手土産は四国の海産物屋から取り寄せた海苔と酒盗にした。考えに考えた末にそうなった。拓郎の家への、はじめての訪問なのだ。気が利いていて、押し付けがましくはなく、まちがいなくおいしくて、先方のもてなしの邪魔にはならないものを持っていきたかった。
当日の朝十時に茜から電話がかかってきた。電話を切ったあとは、今日の訪問をとりやめることを考えていた。でも、結局行くことにした。拓郎は今夜の晩餐のために、早朝から東京湾で釣り船を借りると言っていた。まさかそれまで噓ではないだろう。彼はそういう男なのだ。女を──というより、かかわった相手を喜ばすために最大限のサービスを尽くす男。今後の関係がどうなるにせよ、これまでの関係を悪くしたくない。拓郎とは俳句結社「水軍」の同人同士だ。句会ではいつもやりあって、「喧嘩するほど仲がいいふたり」と見なされている。ふたりがいない場所では「できてる」と噂されているかもしれない。実際のところは、〝まだ〟できていない。だからこそ今日、こんなに悩ましいわけだった。
遥子は、溜息のような鼻息のようなものをひとつ吐き、着ていくものを考えはじめた。これも手土産同様に、考え抜いて昨夜までに決めてあったのだが、こういう事態になったとあっては、また一から考え直さなければならない。電話なんかくれなきゃよかったのにと、茜を恨めしく思った。
茜は拓郎の娘で、三十一歳になる。年齢をはっきり覚えているのは、遥子の息子と同い年だからだ。面識があるのは、二回に一度は拓郎が娘を句会に連れてくるから。小さな劇団の売れない女優だと父親は言い、本人は、しがないフリーターですというふうに自己紹介した。百合の花を思わせるすんなりと美しい娘。拓郎にはあまり似ていない。彼女が十歳のときに病気で亡くなった母親、つまり拓郎の亡き妻がそういう女性だったということだろう。
──遥子さん、電話するべきかどうか迷ったんだけど……。今日、父の家にいらっしゃるでしょう?
今朝の電話で、茜はそう切り出した。ええ、もちろんと遥子は答えた。今夜は拓郎の家で、彼と茜と遥子、三人で食事することになっている。
──あのね、私は行かないの。
──え?
今夜はバイトを入れているのだと茜は言った。今夜の会食はそもそも、茜のスケジュールとは無関係に決められたことだと。
──つまり、なんていうか……父は今日、遥子さんとふたりきりで過ごしたいって。でもそういうお誘いだと、遥子さんはきっと来ないから、私と三人での食事会ということにしておいてほしいって。当日は、急用ができたということにすればいいって。ごめんなさい、父に従うつもりでいたんですけど……こんなのはフェアじゃないって思えてきて。
ややファザコンの気味はあるとしても、茜は真面目で気立てがいい娘だった。だからこそ電話をくれたのだろう。でも、今日、自分は来ないことを伝えて、それでどうなると思っているのだろう。伝えるべきは伝えた、あとはどうなっても「自己責任」ということだろうか。もちろん遥子は、そんな気持ちを茜に吐露したりはしなかった。しょうがないお父さんね、お知らせありがとう、善処します。いい女ぶって、そう言った。
服を決めても──白い麻のシャツにグレイの巻きスカートふうのワイドパンツ、珊瑚のネックレスは迷った末につけないことにした。電話が来る前は白い麻のワンピースに、珊瑚のネックレスを合わせて行くつもりだった──まだ正午にもなっていなかった。拓郎の住まいは調布駅が最寄りだから、遥子が住む八王子からは京王線一本で行ける。約束は夜六時だから、ゆっくり行くとしたって四時半に出ればいい。考える時間はまだたっぷりあるというわけだった。
「水軍」の同人としては、遥子のほうが拓郎よりキャリアが長かった。二年前、主宰していた老齢の師が亡くなって、同人だけで運営していくことになった頃、拓郎はひょっこりとやってきた。そしてたちまち「水軍」の中心人物になった。それまで中心にいたのは遥子だったが、その座を攫われたことに怒りも不満も覚えなかった。ほかの同人たち同様に、遥子もまた拓郎に心を囚われてしまったから。チャーミングという言葉が拓郎ほど似合う人間はいない。男に対しても女に対しても彼はその魅力をふりまいたが、どこか舞台の上で演技しているようなところもあって、だからあるときを境に、彼が遥子の前でだけその舞台から降りて、ほかの同人に対するのとは違った足取りで近づいてきたと思えるようになったことは嬉しかった。
その嬉しさは自分でも意外だった。最初の結婚で、男にはこりごりしていたはずだったのに。離婚したのは十年前──五十になる少し前だった。疑ったり裏切られたり傷つけたり傷つけられたりすることにほとほと疲れて、そういうのはもう勘弁という気分がずっとあって、この十年、何度かあったそういう気配には近づきもしなかったのに。そう、私は拓郎に恋をしているのだ。遥子はあらためてそれを認めた。恋する相手がふたりきりの夜を計画している。それの何が悪いのだろう? どうして腹が立つのだろう?
ほとんど食欲が湧かず、昨夜の残りものを機械的に口に入れていると、電話が鳴り出した。スマートフォンではなく据え置きのほうで、これが鳴ることは最近はめったにない。この電話の番号は拓郎に知らせていないのに、彼からであるような気がして、遥子は緊張しながら受話器を取った。
「もしもし、母さん? 俺だけど」
遥子は一瞬、息を呑んだ。それから溜息とともに「あら、久しぶりじゃない」という声を押し出した。
「やばいことになったんだよ。三百万ほど用意できない? 彼女が妊娠してさ。その彼女っていうのがやばいやつらと繋がってるんだ。金払わないと、どうなるかわからないんだよ。三百無理なら、今あるだけでいいから。いくらくらい用意できる?……」
まくしたてるどこかの青年の声を、遥子はつまらない音楽のように聞いていた。こういう電話があることはもちろん知っていて、いつか自分のところにもかかってくるかもしれない、とは思っていた。でも、よりによって今日じゃなくてもいいだろう。
「拓郎、それであなたは今どこにいるの?」
遥子は電話の相手にそう聞いた。
「わからない。どこかのマンション。監禁されてるんだよ、俺」
「まあ、それは大変ね。私の息子の名前は拓郎じゃないけど」
電話は切れた。さすがに心臓がドキドキしていたが、おかげで自分の心の中がいくらかはっきりもした。なめるんじゃないわよ。そう思っているのだった。オレオレ詐欺の青年にも、拓郎にも。娘をだしにして呼び出して、ノコノコやってきたところを、ぱくりとやれると思っているのだろう。その程度の女だと。噓を吐かれたことがいやだった。噓を吐いて呼び出して、ふたりきりになっても、許してくれる女だろうと思われたことが。前の夫がそういう男だった。噓を一度許したら、安心して噓ばかり吐くようになった。ああいうのはもうこりごり。今また、そういう気分になっている。
空いている上り電車に座って揺られ、調布で降りると、前回の句会のときに拓郎から手渡されたメモ──彼はメールをほとんど使わない。電話、手書きのメモ、たまに手紙──に従って、バス乗り場を探した。七月のはじめで、日が落ちてくればいくらか涼しい風も吹いてくる。拓郎は、ここからバスで十分ほどの川沿いの団地に住んでいるらしい。彼はもともと出版社勤めで、会社員時代は目黒のマンションに住んでいたが、早期退職と同時にそこを売り払い、郊外の古い団地の一室を買ったそうだ。今はフリーの編集者として、作りたい本だけを作っているとか。まったく、いちいちが芝居がかっているというか、人生そのものが芝居みたいな男だ。
スーパーマーケットの前で、ミニスカートの娘がふたり、「いかがですかあ」「お試しくださあい」と声を張り上げている。新発売のビールのようだ。遥子も学生の頃、ああいうバイトをしたことがあった。やっぱりミニスカートをはかされて、今なら、ものを売るのにどうして売り子が足を出さなきゃならないんだと憤るところだけれど、あの頃は、よく褒められる長い足を見せびらかせるのが嬉しかった。そういうばかな娘だったから、前夫のような男に引っかかったのかもしれない。とはいえ、愚さは若さ、と言うこともできるだろう。フェミニズムなんて外国の〝おばさん〟たちの暇潰しだと思っていた。
遥子はふと思いついて、娘たちが売っているビールを買った。三百五十㎖の缶ビールを一ダース。手土産まったくなしというのも、何かを言い立ててしまいそうだったから。新発売のビールくらいがちょうどいい。「あなた好みの女の子が一生懸命売っていたから」とでも言い添えればいい。
バスを降りてから団地内で少し迷って、十七号棟の四〇三号室の呼び鈴を押したときには、六時を五分過ぎていた。ドタドタと駆ける足音が聞こえ、ドアが開いて、出迎えた拓郎は満面の笑みだった。
「よかったあ。来ないかと思った」
「ごめんなさい。出がけにいろいろあって……」
茜からの電話のことを言うべきなのかどうか、迷いながらそう言うと、拓郎は神妙な顔つきになった。
「知ってるよ。茜から僕にも電話があった。本当にごめん。姑息でごめん。でも、無体なことは絶対にしないから。そういうつもりじゃなかったんだ、ただふたりきりで過ごしたかっただけなんだ。本当だよ。なんなら窓もドアも全開でいい」
必死の訴えを、どこまで信じていいものか。でも、自分の心が信じようとしていることが遥子にはわかった。
「これ、お土産。新発売のビール」
意地のようなものもまだあって、ぶっきらぼうに手渡すと、「おっ、白ビールだね。これ飲んでみたかったんだ」と拓郎はまた破顔した。
「じゃあ鱚は、天ぷらじゃなくてフライだな」
「えっ、料理の予定まで変えなくたって」
「たいした変更じゃないから、大丈夫」
手伝いを固辞されて、遥子はキッチンと一続きの部屋のソファに座らされた。和室にカーペットを敷いて洋室ふうに設えているようだ。食前酒にどうぞと、小さなグラスに入った梅酒が置かれたテーブルは古い木製のトランクで、ソファはこれまた年代がありそうなカンタキルトで覆われている。壁一面の書棚に詰まっている本のどのくらいが、彼が手がけた本なのだろう。書棚がない壁には抽象画のリトグラフの額がふたつ。手作りと思しき背の低い食器棚越しに、キッチンで立ち働く拓郎の背中が見える。ディレッタントとは彼のような男のことを言うのだろう。
拓郎は遥子より三つ上の六十一歳だった。ディレッタントの六十一年、と遥子は考えた。手放したものと残したもの。そこに、五十八年ぶんのそういうものを持つ女が座っている。
「さあできた。こちらへどうぞー」
呼ばれて、遥子はダイニングへ赴いた。丸い木製のテーブルに、インドのブロックプリントの座布団をのせた木製の椅子が二脚。そのひとつに座り、拓郎と向かい合う。テーブルの上には大皿に山盛りの鱚のフライとグリーンサラダ、チーズやパテを添えたクラッカー、それに缶ビールがセットされている。
「来てくれて、本当にありがとう。乾杯」
缶を打ち合わせ、遥子はぐびりとビールを飲んだ。「白ビール」とさっき拓郎は言っていた。遥子は食べることにはたぶん彼と同じくらい熱心だが、酒類には詳しくない。新発売の白ビールは、軽い口当たりで、いい香りで、すいすい飲めそうだった。
「ほら、食べて。食べて。うまいぞう」
急かされながら、鱚のフライを口に運ぶ。揚げたてで、衣のサクッとした歯ごたえのあと、鱚の身がほろっとほどけた。おいしい。欲も得もなく感嘆の声が洩れた。
「うまい! 最高! 合うと思ったんだよね、白ビールに」
拓郎ははしゃいだ声を出し、白ビールをまたぐいと呷った。心底嬉しそうなその顔を見ていたら、遥子の心の強張りは緩んでいくようだった。
今度はフライにちょっとレモンを搾って、また食べて、また飲んだ。たしかに合う。白ビールも鱚も、ふわふわしていて。いや、ふわふわしているのは私の心だろうか。
「笑うところじゃないんだけどなあ」
拓郎が言った。今彼は、釣果の自慢をしているのだ。ちゃんと聞いていたけれど、それとはべつに、遥子は笑ってしまったのだった。つまらない男に引っかかって、離婚して、結社に入って、拓郎に出会って、なめるんじゃないわよと腹を立てて、オレオレ詐欺を初体験して、ミニスカートの娘たちからビールを買って、それで今私はここにいて、拓郎が揚げた熱々の鱚のフライと、それによく合う白ビールを飲んでいる。そう思えたら笑えてきたのだ。

▶第二話はコチラ
****************
作家
井上荒野(いのうえ・あれの)
東京都生まれ。1989年「わたしのヌレエフ」でフェミナ賞、2008年『切羽へ』で直木賞、11年『そこへ行くな』で中央公論文芸賞、18年『その話は今日はやめておきましょう』で織田作之助賞受賞。著書に『リストランテ アモーレ』『あなたならどうする』『あたしたち、海へ』『あちらにいる鬼』『荒野の胃袋』ほか多数。