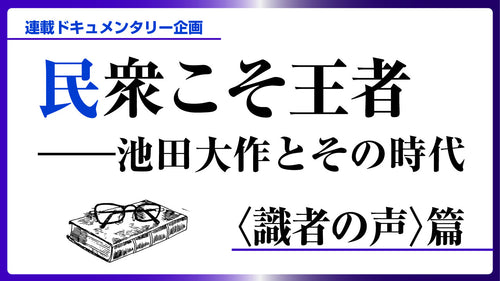潮文庫『覇王の神殿(ごうどの)』プロローグ試し読み
2023/09/20潮文庫『覇王の神殿』発売を記念して、プロローグを特別公開中!
理想の国造りにかけた蘇我馬子の生涯を描く!
この記事はネット記事としての可読性を保つことを目的に、読み仮名の量を最小限にしています。
文庫版『覇王の神殿』とは読み仮名をつける箇所が異なっている点をご了承ください。
プロローグ
──雨、か。
突然、大地を叩く雨音が迫ってきた。黒々とした雲の中から、腹底に響くような雷鳴も聞こえる。
──まさか、仏は怒っているのか。
大極殿の前庭には屋根がないため、そこに整列する武官や史(文官)たちの体も濡れ始めた。
誰もが不安そうに空を見上げ、小声で何事か話し合っている。海を渡ってきた三韓(高句麗・百済・新羅)の使者たちもそれは同じで、恨めしそうに空を眺めている。
遠方に目をやると、甘樫丘はかろうじて見えているが、その右手にあるはずの耳成山と香具山は、霧に閉ざされて山麓しか見えない。
──果たしてうまくいくのか。
不安が頭をもたげてきた。長槍を持つ手が震え、頭巾から垂れる雨が視界を遮る。そうしたことが、さらに不安を募らせる。
足を滑らせて転倒し、武官たちに取り押さえられる己の姿が頭をよぎる。
──やはり、やめよう。
その時、中臣鎌足の言葉が脳裏によみがえった。
「入鹿は厩戸王子を父とする山背大兄王さえも滅ぼしたのです。蘇我氏の血縁に連なっていないあなた様を殺すことに、何の躊躇がありましょう」
そして鎌足はこう続けた。
「殺らなければ、殺られるだけです」
中大兄王子は、自らの心に芽生えつつある不安や怯懦を捻じ伏せるべく、蘇我入鹿への憎悪をかき立てようとした。
──入鹿よ、そなたは飛鳥宮を見下ろす甘樫丘に巨大な邸を築き、大王(後の天皇)とその一族にしか許されない「八佾(やつら)の舞」を舞わせて祖先の祭祀を行った。また大王だけが使役できる部曲(かきべ)を無断で徴用し、「今来の双墓(いまきのならびはか)」を造営した。これらが謀反の証しでなくて何であろう。
「八佾の舞」とは、大王の一族にだけ許された古代中国の雅楽の編成で、「今来の双墓」とは、蝦夷と入鹿が造営した生前墓のことだ。
──しかしそうしたことは、些細なことにすぎない。
入鹿の最大の罪は、厩戸王子の血脈を受け継ぐ山背大兄王の一族を滅ぼしたことにある。
──これぞ臣下にあるまじき行為!
中大兄は大きく息を吸うと、共に大極殿の脇殿の陰に隠れる佐伯子麻呂と葛城稚犬養網田を見た。二人は韓人の衣装を着けており、手にしている長剣は、韓人の朝貢品の中に隠しておいたものだ。
──鎌足はどこにいる。
儀式が始まるや、鎌足は配下の者たちを使い、飛鳥宮の十二の門すべてを閉ざす予定になっていた。おそらく手抜かりはないのだろうが、鎌足の姿が見えないだけで不安になる。
瓦で葺かれた大極殿の屋根を、激しく雨が叩く。それでほかの物音がかき消されることに、中大兄は気づいた。
──足音が消せるなら、警固の武官たちが気づくのも遅れる。やはり、やるべきだ。
決意が次第に凝固してくる。
やがて十人ほどの群臣を従えた大臣(おおまえつきみ)の蘇我入鹿が姿を現した。
群臣とは、大夫(政府高官)や国造(豪族)たちのことを言う。
──何と憎々しい姿か。
入鹿は紫冠をかぶり、紫色の朝服を着ている。腰の上に回した長紐は鮮やかな朱色で、紫主体の装束を引き締めている。
紫冠は冠位十二階で定められた五冠を超越したもので、蘇我氏の族長位にある者だけがかぶれることになっている。蘇我氏だけが群臣の中で特別な存在だということを、強く主張するために設けられたものだ。
傲慢さをあらわにして周囲を睥睨した入鹿は、すでに整列している三韓の使者たちに軽く目礼し、恭しく歩を進めた。雨をものともしないその悠然とした姿は、この国の実質的支配者が誰かを、三韓の使者たちに知らしめようとしているかのようだ。
その時、俳優(わざおぎ)と呼ばれる道化役を兼ねる案内役が現れ、入鹿に何か話しかけた。
この俳優には鎌足の息が掛かっており、「三韓の使者が無剣で儀式を行うことを望んでいる」と告げているはずだ。しかし入鹿は首を左右に振り、腰に手を当てて拒否の姿勢を示した。これまでは儀式で帯剣を外すことなどなかったので、そうした異例を嫌っているに違いない。
一方、入鹿の背後にいる蘇我倉山田石川麻呂は帯剣を外し、俳優に手渡した。
入鹿が石川麻呂に何か問うと、石川麻呂が答えている。おそらく「三韓では儀式で帯剣を外すことが多いと聞きます。此度は三韓の使者を迎えた大事な儀式なので、かの者たちの望みを容れましょう」と言っているのだろう。
石川麻呂は入鹿の従兄弟にあたり、一族の重鎮として入鹿からも一目置かれていた。だが石川麻呂は蘇我氏の族長の座に就きたいという野望を持ち、鎌足の誘いに一も二もなく乗ってきた。
──外せ。外してくれ。
中大兄は心から念じた。
石川麻呂が背後に向かって何か言うと、付き従ってきた者たちも帯剣を外して俳優に渡している。それを見ていた入鹿は、致し方なさそうに帯剣に手を掛けた。
それでも躊躇していると、俳優が何か戯れ言を言った。それが入鹿の緊張を解いたのか、笑みを浮かべて帯に手を掛けると、止め紐を解いて帯剣を外した。
──これでよい!
中大兄は心中、快哉を叫んだ。
自邸内で寝ている時でさえ、剣を肌身離さず持っていると噂される入鹿である。渡来人から剣の稽古をつけてもらっているとも聞く。そんな入鹿を討つには、まずその剣を奪う必要があった。そのために練りに練った秘策がこれなのだ。
入鹿が俳優に帯剣を渡す。それを確かめた中大兄は、額から垂れる雨混じりの汗を拭い、再び入鹿の動きを注視した。
剣を抱えて去っていく俳優の背を不安げに見ていた入鹿だったが、やがて群臣を従え、縦に整列する三韓の使者の隣に並んだ。入鹿は大臣なので、整列した者たちよりも一歩前に出る形になる。続いて石川麻呂が進み出ると、入鹿の前に立った。石川麻呂は、「三韓の表文(ふみ)」と呼ばれる上表文を読唱することになっている。
今回の儀式は、三韓すなわち高句麗・百済・新羅三国が、大和国(日本)の仲立ちにより和睦を結ぶという誓約を皇極大王の前で誓うというものだ。
──入鹿よ、そなたは、この和睦を成立させることに心血を注いできた。しかもそれによって絶対的な権勢(権力)を築き得たと思っているはずだ。だが、それは違う。
入鹿の偉大な業績に心が折れそうになるのを堪え、中大兄は入鹿の政策が間違っていると思い込もうとした。
──三韓の和睦をまとめることで、そなたは大和国を含めて四国の頂点に立ったつもりでいるのだろう。そして群臣の力を結集して唐を討ち、この世の王になるという大それた野望を果たそうとしているのだ。
中大兄は、鎌足が語った入鹿討伐の大義に必死にすがり付こうとした。
「このまま入鹿の思い通りにさせておけば、ゆくゆくは唐と戦うことになり、間違いなく大敗を喫します。さすればこの国は唐の一部になり、われらの多くが農奴とされます」
鎌足は半島の争乱に関与しないことこそ、この国を守ることだと信じていた。
その時、突然、「大王の出御(しゅつぎょ)」という史の高らかな声が聞こえた。続いて大極殿の奥から供の従女(女官・侍女)を従えた皇極が姿を現すと、石川麻呂を除く全員が拝跪の姿勢を取った。
拝跪の姿勢とは、左膝をついて両手を組み、頭を下げることだ。
──母上、お目を汚すことになりますが、ご容赦下さい。
中大兄は心中で皇極に詫びた。
佐伯子麻呂と犬養網田が入鹿を討った後、中大兄は大極殿の五級(ごしな)の階に駆け上り、この襲撃が正当なものだと皇極の前で宣言するのだ。
皇極が常と変わらぬ優雅な身のこなしで玉座に着く。その頭上には屋根があるので、濡れ鼠となった居並ぶ者たちとの対比が鮮やかだ。
位階に合わせた色とりどりの朝服を着た百を超える史と武官が、三韓の使者たちと共に大極殿の前庭に拝跪する光景は、まさに壮観の一語に尽きた。しかし誰もが、この雨に堪えきれなくなっており、一刻も早く儀式を終わらせてほしいと願っているに違いない。
──いよいよだな。
刻一刻と迫る勝負の時に、中大兄の心は身震いしていた。
やがて石川麻呂は「三韓の表文」の読唱を始めた。
その時、ふと傍らを見ると、子麻呂と網田が震えているのに気づいた。
「しっかりしろ」
中大兄は小声で叱責したが、二人は心ここにあらずといった有様だ。
──何か落ち着かせる方法はないか。
その時、中大兄は水を持ってきたことに気づいた。
「これを飲め」
「は、はい」
まず子麻呂に渡したが、子麻呂はそれを飲むと、すぐに吐き出してしまった。
──此奴らはあてにできぬ。
二人が刺客の用をなさないのではないかという危惧がわき上がる。
「心を強く持て。必ずうまくいく」
中大兄の言葉にうなずく二人だが、その顔色は蒼白だ。
その時、石川麻呂の読唱が乱れているのに気づいた。遠目から見ても、手が震えているのが分かる。事前の打ち合わせでは、読唱が終わった直後に襲い掛かる手はずになっていたが、入鹿に不審に思われては終わりだ。入鹿を見ると、射るような眼光で石川麻呂を見つめている。
石川麻呂の声がさらに乱れる。いかに大王の前とはいえ、これだけ緊張するのはおかしい。
次の瞬間、石川麻呂が上表文の束を落とした。慌ててそれらを拾い集める石川麻呂を手助けするかのように入鹿は近づくと、その耳元で何事かを囁いた。おそらく「何ゆえ震えおののく」と問うたに違いない。首を左右に振りつつ石川麻呂は何か言ったが、その挙動はぎくしゃくしている。それを見た入鹿の顔が、さらに険しいものに変わる。
──もはや猶予はない。
だが頼みの子麻呂と網田は、とても入鹿を討てるような状態にない。
──やはりだめだ。今日はやめよう。
弱気の虫が騒ぎ始めた。
──だが、ここでやめたらどうなる。この儀式によって入鹿の功績が母上に認められれば、それに反対することは反逆に等しいことになる。
つまりこの儀式の後で入鹿を殺すことは、皇極の意向を否定することにつながる。
──儀式を続けさせてはならない!
鎌足の言葉が脳裏によみがえる。
「蘇我氏は悪しき者たちです。彼奴らを滅ぼさねば、大王家は名ばかりとなり、すべての権勢は蘇我氏のものとなるでしょう」
──この国を入鹿のものにしてたまるか!
中大兄は槍を握り直すと言った。
「私に続け」
「えっ」
「当初の段取りでは、そなたらが入鹿を討った後、私が大王の前に進み出で、この襲撃の正当性を説くつもりでいた。だが、そなたらでは入鹿を討てぬ。私が最初の一撃を浴びせるので、それに続け」
二人が顔を見合わせる。
「分かったか」
「は、はい」
──入鹿め!
中大兄は憎悪の塊と化そうとした。
石川麻呂の読唱はさらに上ずり、入鹿の不審は頂点に達していた。群臣の中には、小声で何事か囁き合っている者もいる。
──これからすることは、この国のためなのだ!
長槍を捨てた中大兄は剣を抜いた。直感的に接近戦になると思ったのだ。
──どうとでもなれ!
大きく息を吸い込むと、中大兄が物陰から飛び出した。二人がそれに続く。整列した者たちの先頭までは二十間(約三十六メートル)ほどある。その距離を誰にも邪魔されずに駆け抜けねばならない。
横殴りの雨が吹き付ける。すでに周囲は暗くなり、雷鳴も頭上で鳴り続けている。
砂利を踏む音に驚いたのか、そこにいる者たちが一斉にこちらに顔を向けた。だが何が起ころうとしているのかまでは分からないのだろう。武官たちも拝跪したまま動かない。
雨滴が顔に掛かり、驚く者たちの顔が次々と後方に去っていく。砂利に足を取られ、速く走れないのがもどかしい。それでも中大兄は懸命に走った。
異変に入鹿も気づいたようだ。しかし拝跪の姿勢のまま肩越しにこちらを見ているだけだ。おそらく、国家的儀式の場で襲撃されるとは考えてもいないのだ。
「蘇我入鹿、覚悟せい!」
言葉が逬った次の瞬間、天が割れたかと思うほどの雷鳴が轟き、青白い光が大極殿を照らした。
ようやく入鹿の顔に恐怖の色が浮かんだ。同時に居並んだ者たちが算を乱して逃げていく。だが入鹿は大臣という自らの地位を思い出したのか、その場から動かず、ゆっくりと立ち上がると腰に手をやった。だが、そこに帯剣がないのに気づき、顔色が変わった。
慌てて逃げ出そうとする入鹿の肩に中大兄の長剣が振り下ろされる。
──しまった!
最初の一撃は冠を叩き落としただけだった。入鹿が背を見せると同時に、中大兄は再び剣を振り上げた。
「死ね!」
今度は手応えがあった。入鹿の袍の左肩から腰に掛けて裂け目が走ると、鮮血が逬る。
「何をする!」
振り向いた入鹿の顔は、怒りとも恐怖ともつかない凄まじい形相になっていた。
「なにゆえ──、なにゆえかような狼藉をいたすか!」
皇極の庇護を求めるかのように、入鹿は大極殿の方に逃れようとした。
皇極が立ち上がるのが一瞬、視界の端に捉えられた。
その時、背後から中大兄を追い抜いていった子麻呂が入鹿の足に斬りつけた。事前の打ち合わせでは、入鹿の動きを止めるため、第一撃は足と決めていたのだ。
入鹿は「おおっ!」という声を発すると、その場に転がった。それでも五級の階にたどり着くと、それを這うように上った。
そこに網田の一撃が振り下ろされる。
「ぎゃー!」
入鹿が鮮血にまみれながら振り向く。
その形相に恐れをなしたのか、子麻呂と網田は剣を構えたまま後ずさった。
「どけ!」
二人を左右に分けた中大兄は剣を振り下ろした。だが、鈍い音がして剣が折れた。腰骨に当ててしまったのだ。
その時、入鹿が玉座にいる皇極に向かって叫んだ。
「臣、罪を知らず。大王、何ゆえ私が、かような目に遭わねばならぬのですか!」
その言葉にかぶせるように、背後から入鹿の襟首を摑んだ中大兄が喚く。
「大王、この者の罪は明らか。この者は──」
中大兄は背後を見渡しながら大声で告げた。
「大王の座を狙っております!」
「何を言うか。大王の座に就けるのは大王の血脈のみ。それを心得ぬ入鹿とお思いか!」
「黙れ! そなたが大王の王統を廃絶させようと企んでおることは、誰もが知っている!」
中大兄が背後にいる二人に剣を渡すよう合図する。だが二人は足がすくんで階を上れない。
「どうした。早くしろ!」
彼らの身分では、大極殿の階を上るという行為が畏れ多くてできないのだ。
だが、これで入鹿に隙を与えてしまった。入鹿は懸命に皇極に懇願した。
「大王、私に叛意などないことは、大王が最もよくご存じのはず!」
皇極は啞然として中大兄と入鹿を交互に見ていた。この一件を起こしたのが自分の息子でなければ、すぐにでも捕らえるよう命じたに違いない。
──だが私は大王の子なのだ。
事ここに至れば、中大兄はその立場にすがるしかない。
「母上、どうかご聖断を!」
中大兄は、皇極のことをあえて「母上」と呼んだ。
その時、背後で「放せ!」という声がしたので振り向くと、子麻呂と網田が駆けつけてきた武官たちに取り押さえられている。
──しまった。
これにより、中大兄は武器を手にすることができなくなった。
続く皇極の言葉次第で、中大兄も捕らえられる。
──ここで母上が「この者たちを捕らえよ」と仰せになれば、私は配流となり、二度と飛鳥には戻れまい。もちろん王位に就くことも叶わなくなる。残された子麻呂と網田は入鹿の手で殺される。鎌足も同じだ。いや、配流地への護送途中に私も殺されるだろう。
そうなれば蘇我氏の支配は続き、その権力は大王一族を上回っていくに違いない。
「大王、私が何をしたというのです!」
入鹿が哀願する。
「母上、この者は大王の地位を簒奪しようとしております!」
その時、ようやく皇極が呟いた。
「朕は与り知らぬ」
皇極は玉座から立ち上がると、奥へと向かった。
「お待ちあれ。お待ち下さい!」
追いすがろうとする入鹿の背を踏みつけて振り向くと、武官たちの背後に鎌足の顔が見えた。
武官たちはどうしてよいか分からないのか、子麻呂と網田を押さえつけたまま、左右を見回している。
──誰かの下知を待っているのだ。
「皆の者、この者たちを捕らえろ!」
入鹿もそれに気づいたのか、肩越しに振り向いて命じる。だが入鹿の声は弱々しく、雨の音にかき消された。
「鎌足、これへ!」
「はっ」と言うや、鎌足が武官たちをかき分け、階の下に馳せ参じた。
「剣を渡せ」
「はい」
鎌足は腰の帯剣を外すと、それを厳かに捧げ持ち、入鹿を踏みつける中大兄に献上した。
「入鹿、覚悟しろ!」
再び雷鳴が轟き、閃光が入鹿の顔を青く照らす。
「よせ、何をする。わしを殺せば、国内は混乱し、この国は唐に蹂躙されるぞ」
「そんなことはない!」
「わしを殺しても、わが父蝦夷が健在である限り、そなたらは滅ぼされる。今ならまだ間に合う。そうだ、そなたを王位に就けると約束しよう!」
「何を言うか。これまで大王の威を借り、この国を支配してきたことを、いかに弁明するのか」
「弁明だと。わしには弁明などない。わしは仏意に従い、この国のために一身を捧げてきたのだ!」
「それは仏意ではない。そなたの邪悪な心のなせる業だ!」
「わしには邪悪な心などない。わしの心にあるのは──」
口から血を吐き出しつつ入鹿が叫ぶ。
「この国のことだけだ」
「いや、違う! そなたは己のことしか考えておらぬ。今こそ裁きを受けよ!」
中大兄が剣を振り上げる。
「何と愚かな。わしを殺せば、この国は滅ぶぞ」
「滅ぶものか。これが仏意だ!」
中大兄が入鹿の背に剣を突き立てた。
「あっ、く、く、ぐあー!」
入鹿の断末魔の叫びが耳朶を震わせる。
「逆臣、蘇我入鹿を討ち取りました!」
中大兄が誰もいない玉座に向かって叫ぶ。
「おう!」という声に振り向くと、鎌足たちが弓や剣を掲げて声を上げている。子麻呂と網田も、いつの間にか解放されていた。
入鹿が殺されたことで、流れが一瞬にして変わったのだ。
入鹿の顔をのぞき込むと、すでに息絶えたのか、瞳を閉じて微動だにしない。その顔に浮かんでいた無念の形相も和らいできている。
──天寿国への道を歩んでおるのだな。
息絶えた入鹿の背から剣を抜き取った中大兄は、それを天にかざした。
いつの間にか雨雲は去り、耳成山の上空に掛かる雲間から光が差してきていた。
「あれを見よ!」
中大兄が耳成山の方角を指すと、その場にいた者たちの顔も一斉にそちらを向いた。
「あの光こそ、わが行為が仏意であることの証しだ! これは新しき世の到来だ。われらは新しき国家を造るのだ」
「おお──」というどよめきとともに、群臣や武官が平伏する。
中大兄の掲げる剣に太陽光が反射する。
──私は勝った。勝ったのだ。
「うおー!」
中大兄が勝利の雄叫びを上げると、そこにいた者たちも快哉を叫んだ。
皇極四年(六四五)六月、飛鳥の地には光が溢れていた。
かくして乙巳の変は成功し、大和国の舵取りは中大兄と中臣鎌足に託された。大化の改新である。しかしその政治方針は、それまで政権を担っていた蘇我氏のものと一線を画しているとは言い難く、蘇我氏に集中していた権勢を、中大兄と鎌足が奪ったに等しいものだった。
では誰が、その大方針を打ち立てたのか。
この物語は、大化の改新の前代を生き、この国のカタチを作った一人の男の苦闘の足跡をたどったものである。
(プロローグ終わり)
発売を記念して直筆サイン本を5名の方にプレゼント!
ご応募はコチラから

『覇王の神殿』ご購入はコチラから
******
作家
伊東潤(いとう・じゅん)
1960年、神奈川県横浜市生まれ。早稲田大学卒業。『国を蹴った男』(講談社)で「第34回吉川英治文学新人賞」、『巨鯨の海』(光文社)で「第4回山田風太郎賞」と「第1回高校生直木賞」、『峠越え』(講談社)で「第20回中山義秀文学賞」、『義烈千秋 天狗党西へ』(新潮社)で「第2回歴史時代作家クラブ賞(作品賞)」、『黒南風の海――加藤清正「文禄・慶長の役」異聞』(PHP研究所)で「本屋が選ぶ時代小説大賞2011」を受賞。近刊に『浪華燃ゆ』(講談社)がある。