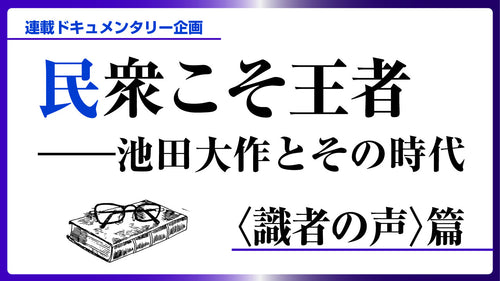潮文庫『裁判官 三淵嘉子の生涯』ためし読み
2024/04/012024年4月1日からスタートするNHK朝ドラ「虎に翼」で注目を集める、女性初の弁護士(のちに裁判官)・三淵嘉子(旧姓 武藤嘉子)。
小説「裁判官 三淵嘉子の生涯」(潮文庫)から冒頭部分を特別公開。
(サムネイル画像:©starline/Freepik)
******
第一章 武藤家の食卓
1
武藤嘉子(むとうよしこ)は大正三(一九一四)年十一月に新嘉坡(シンガポール)で生まれた。
その日はからりと晴れて暑かったという。産室の窓からは底抜けに青い空と、堂々とした入道雲が見えたらしい。
常夏の国は、町のいたるところに蘭が咲いている。年中夏で蒸し暑く、四季がないから、花が途絶えることがない。次から次へ蕾がほころび、町のそこかしこで鮮かな紅色の花があっけらかんと咲きほこり、湿った熱風は甘い香りを帯びているのだとか。
暑いお国柄、味が濃くて油っぽい食べものが多く、母の信子も初めは閉口したそうだ。しかし、それもいっときのこと、気候に体が慣れてくると、土地のものがおいしく感じられるようになる。ことに鶏肉と玉葱を出汁で炊いた鶏飯(けいはん)はいたく気に入り、夫婦で屋台へ通いつめたという。
ときおり無性に食べたくてたまらなくなって、日本でも作ってみるのだが、気候が違うせいか、あの味を再現することができなくて残念だと、母の信子は今でも懐かしむ。シンガポールの鶏飯は本当においしかった。嘉子たちにも食べさせてやりたい、と。いつもは厳しいけど、鶏飯の話をしているときの母は何だかちょっぴり可愛い。
六人姉妹の末っ子で、早くに実父を亡くし、伯父夫婦のもとへ引き取られ、気を使いながら育った信子にとって、夫の貞雄と共に故郷を離れ、二人きりで過ごした新婚時代はよほど楽しい日々だったらしい。それゆえ鶏飯の味は格別なのだ。
嘉子が生まれた日のことを、貞雄は日記に書いている。
『産声が太くて立派。行く末が楽しみ。めでたし』
よほど嬉しかったのか、字の横には鉛筆で鯛の絵まで添えてある。
初子だけに難産で、出産には一昼夜かかったが、嘉子は生まれ落ちた途端、待ちかねたように元気な産声を上げた。と、これは信子に聞いた話。
「嘉」は「良いこと」「めでたいこと」をあらわす縁起のいい字だ。
新嘉坡で生まれたから嘉子。どうか娘の人生が良いことやめでたいことに恵まれるようにと、両親の祈りがこもっている。
それから十七年が経った。武藤家は東京に居を構えている。
台湾銀行へ勤める貞雄の赴任地がシンガポールからニューヨークへ異動となり、大正五(一九一六)年に弟の一郎が生まれたのを機に、信子は息子と娘を連れて日本へ帰国した。いったん香川県の伯父夫婦のもとへ身を寄せたものの、大正九(一九二〇)年に貞雄が東京支店へ異動になり、帰国が叶ったのを機にふたたび香川の家を出て、今は麻布笄(あざぶこうがい)町に借りた敷地百五十坪の武家屋敷で一家七人仲良く暮らしている。
昭和六(一九三一)年十月。
嘉子は家族揃って朝食の膳についていた。
上座に貞雄、その隣に信子。下座には、誕生日が来ると満十七になる嘉子を筆頭に、四人の弟――上から順に一郎、輝彦、晟造(せいぞう)、泰夫が並ぶ。さらにここへ書生が加わることも多く、茶の間として使っている座敷はいつも賑やかだ。
窓からは清々しい日射しが差し込み、座敷には炊き立てのご飯とおみおつけのにおいが満ちている。
女の幸せは温かな家庭に宿る。
明治二十五(一八九二)年の生まれで、良妻賢母こそ女の目指す道と信じている信子は、毎朝女中と同じ時刻に起床し、家族全員の食事をととのえる。貞雄も子どもたちに合わせて七時に起きてくる。
大島に葡萄柄の刺繡の入った帯を締めた信子は、女中の先頭に立ち、甲斐甲斐しく世話を焼いている。嫁入り前、香川の伯父宅にいた頃からの習慣だそうだ。
伯父は借家をいくつも有している金持ちだが、伯母の性格はきつかった。養女となった後、信子は辛い娘時代を過ごしたらしい。そのため、信子は自分の作った家族に対する思い入れが強い。
武藤家では食事のたびに大きな釜で十合の飯を炊く。膳にのるのはご飯におみおつけ、漬け物に干物といった純和風の食事で、季節の果物が添えられている。今朝は梨だ。
いつも騒がしい弟たちが、今朝は揃っておとなしい。一様にうつむきがちで、もそもそと居心地悪そうに食べている。心なしか「お代わり」の声も小さく、茶碗を差し出す手も遠慮がちだ。
弟たちが神妙にしているのは、信子がすこぶる不機嫌だからだ。
見るからにピリピリとして、全身から棘を出している。香川の祖母――信子の伯母の駒子は確かにきつい性格だが、実は信子とちょっと似ている。特に怒り方が。眉間にくっきり縦皺を寄せ、無言で圧を放つところなどそっくりだ。弟たちは触らぬ神に祟りなしとばかりに、そそくさと食事を終えると我先に部屋から逃げていった。巻き添えを食うのは真っ平というわけだ。
「ママ、お代わり」
嘉子はいつも通りに茶碗を差し出した。
信子は応えない。素知らぬ顔でご飯を食べている。なるほど。親の言いつけに従わない娘の世話はしたくないわけだ。ならば、と自分でお代わりをよそおうと、腰を上げかけたら、信子がすごい目で睨んできた。
「駄目ですからね」
「お代わりしたら駄目なの?」
「ご飯の話じゃないわよ。わかってるくせに、とぼけるのは止しなさい」
もちろん、わかっている。とぼけているのではなく、話し合う気がないだけだ。もう嘉子の決意は固まっている。
「すぐに入学手続きを取り消していただきなさい。法律の勉強なんて絶対に許しませんからね。お嫁にいけなくなりますよ」
「ごちそうさま」
嘉子はお代わりを諦めて箸を置き、両手を合わせた。いい加減慣れてきたが、朝から説教されるとげんなりする。
「待ちなさい、嘉子。話は終わっておりません」
「帰ったら聞きます。今日は日直で、早く登校しないといけないの」
革鞄を手に立ち上がり、そそくさと部屋を出ていこうとしたところへ、ぴしりと鋭い声が飛ぶ。
「噓おっしゃい。そうやって逃げるつもりね」
ばれたか。
敷居際でふみとどまり、しぶしぶ膳の前に戻る。
信子がこめかみに青筋を立てている隣で、貞雄は何食わぬ顔で食後の梨をはんでいる。
どうにかしてよ、パパ。
目顔で助けを求めると、貞雄は四角い顎を引いた。後は任せなさいというふうに、丸眼鏡の弦をちょっと持ち上げてみせる。
「おい、知ってるか?」
貞雄はのんびりと信子に話しかけた。
「後にしてください。嘉子と話しているんですから」
「今度浅草にできる松屋には、屋上に遊園地ができるんだってな。観覧車やゴンドラもあるというから、ずいぶん本格的じゃないか」
「知ってますよ」
一家の大黒柱の貞雄をそう無下にもできず、信子はうるさそうな顔をしつつ返事をした。明治十九(一八八六)年生まれの六つ年上で、伯父夫婦の武藤姓を継ぐために婿養子へ来てくれた貞雄のことは、いくら怒っているときでも無下にはできないのだ。
「遊園地の他に動物園もあるんですってね。晟造や泰夫は行きたがっていますよ」
「連れていってやるといい。しかし、初日はすごい人出になるだろうな」
「そうですとも。行くなら、うんと早起きして出かけないと。――これ、嘉子!」
信子の目が離れた隙を縫い、嘉子は部屋を飛び出した。
「じゃあ、行ってまいります」
「女が法律なんて、絶対に許しませんからね!」
尖った声が背を追いかけてきたが、振り向かなかった。のんびりお小言を聞いている暇はない。急がないと女学校に遅刻する。玄関で靴を履いていると、慌てて女中が小走りに来て、弁当を渡された。
数寄屋(すきや)門を出て裏手に走り、市電へ滑り込む。混み合う車内で吊革を持ち、嘉子はふう、と息をついた。間に合って良かった。後はゴットンガッタンと揺られ、信濃町(しなのまち)で省線に乗り換えてお茶の水まで行けばいい。
市電の停留所が目と鼻の先のところにあるせいで、今日に限らず、いつも家を出るのはギリギリの駆け込みセーフ。今頃家では夫婦喧嘩になっているかもしれないけど、知らない。信子のことは貞雄に任せた。何しろ、明治大学専門部女子部へ入ることを勧めてきたのは貞雄なのだから。
先月下旬、信子が法事で数日間丸亀へ帰省したときのことだ。
ちょうど四人の弟たちも、書生たちもみな出払っており、めずらしく家には嘉子と貞雄の二人きりだった。
部屋で本を読んでいたら、書斎に呼ばれた。めったに足を踏み入れることのない十畳間で、貞雄はシンガポール式の、練乳と砂糖たっぷりのコーヒーを飲んでおり、嘉子にはココアとビスケットが用意してあった。
武藤家では物心ついた頃より〈パパ、ママ〉で、おやつにも外国のお菓子が出てくる。丸亀の祖父母には不興だけれど、お茶の水の同級生にもそういうお宅はめずらしくないみたいだ。
忙しい貞雄と差し向かいで話をする機会は多くない。弟や書生が家を空けているときを狙って呼ばれたからには、何か訊きたいことがあるのだと思っていたら、果たして将来の計画を問われた。
「女学校を出たらどうする」
嘉子は翌春に卒業を控えている。
同級生の中には、既に縁談の決まった者もいる。嘉子の通っている東京女子高等師範学校附属高等女学校、通称お茶の水高女は良家の子女が集まる学校として名高く、嘉子自身も卒業後は花嫁修業をするものと思っていた。
しかし、こうして問うからには、貞雄には別の腹案があるわけだ。
「勉強を続けたらどうだ。成績優秀な嘉子が女学校で止めてしまうのはもったいない」
願ってもない申し出に驚いていると、
「それとも、お茶やお花の稽古をしたいかね」
違うだろうに、という顔で言う。父親だけによくわかっている。
「いいの?」
「ああ。その気があるなら、上の学校へ進みなさい」
「それって、ママが反対するような学校でしょう」
「勘が良いな」
やっぱり。そうだと思った。そうでなければ、信子が家を空けている隙を狙って、そんな話を持ちかけてくるわけがない。
「ママが反対するのが心配かね」
試すように、貞雄が顔を覗き込む。
「だったら止すか? 別にいいぞ。パパは構わん。嘉子の人生だ、好きにすればいい。女学校を出たらせいぜいお稽古に励み、可愛いお嫁さんになりなさい」
「意地悪ねえ」
口を尖らせると、貞雄はにっと笑った。
頰が盛り上がり、丸眼鏡の縁にくっつく。銀行では大勢の部下を従えているけれど、家ではちっとも偉ぶらない家庭人だ。
「それで? どこへ入れとおっしゃるの」
「何を学びたいかによる。嘉子、お前は将来どんな仕事につきたいんだ。ああ、お嫁さん、というのはなしだぞ」
釘を刺され、はたと考える。
仕事。考えたことがなかった。勉強は好きだが、それは学生の間のこと。悔しいことに、貞雄の言う通り、お嫁さんになるとしか考えていなかった。
「考えたことなかったか」
悔しいが、その通りだ。勉強は好きだが、女は学校を出たら家庭に入るのが当たり前。自分も信子のようにお嫁さんになって、家庭を守るとばかり思っていた。
「そうか。しかし、嘉子はお嫁さんに向かないだろう」
嘉子はむっとした。
「どういう意味? これでも付け文をされたことくらいあるのよ」
といっても女学校の後輩からだけど。他者から思いを寄せられたことに変わりはないはず。お嫁さんに向かないなんて、いくら父親でも失礼ではないか。
娘の不興を買ったらしいと気づいた貞雄が、
「早合点するな」
と苦笑いした。
「嫁にいけないと言っているんじゃない。嘉子なら、どんな男もよりどりみどりだ。まあ、パパとしてはあんまり早く嫁いでほしくはないがね。おっと、こんなことを言うと、ママが角を生やして怒るか」
貞雄は頭を搔きつつ、「話が逸れたな」とつぶやく。
「お嫁にはいくわよ、そのうち」
「いくのか」
自分で言ったくせに、貞雄は悄気(しょげ)た声を出した。
「やあね、まだ縁談の話も来ないうちから。今はお仕事の話でしょう」
「そうだったな。進学するなら、将来どんな仕事をするか考えて、専攻を選びなさいと言いたかったんだ」
「そういうこと。行き遅れを案じているわけではないと、よくわかりました」
「さよう、さよう」
二度言うと、ごまかしているみたいに聞こえるが、まあいい。
「つまりパパは、結婚しても仕事を続けろとおっしゃりたいのね」
「理解が早いな」
貞雄は丸眼鏡の奥の目を引き締めた。
「パパはね、女もきちんと自立したほうがいいと思う。みんなと同じように家庭に入って、普通のお嫁さんにならなくてもいいんだ。さっきも言ったが、そんな生き方は嘉子には向かない。すぐに飽きて退屈するのが目に見えておる」
女学校の古居先生が聞いたら、血相を変えそうな話だ。
若い頃から勤め先の台湾銀行で海外赴任していた貞雄は、明治十九年生まれの男にしてはめずらしく、極めて民主的な考えを持っている。シンガポールの次に赴任したニューヨークには、男と肩を並べて働く女が大勢いたそうで、嘉子も幼い頃から男女は同等だと教えられてきた。
「仕事を持ち、結婚しても続けなさい。専門職がいい。誰かの補佐をするのではなく、自分の足で立ち、責任を引き受ける仕事につくんだ。政治や経済のわかる大人になって、男と肩を並べて働くのは面白いぞ」
世間には、女学生の娘にこんなことを言う父親はいない。有り体にいえば常識から外れている。
「仕事に男も女もない、でしょ?」
これが貞雄の口癖だ。物心ついた頃から繰り返し聞いているから、頭に染みついている。
「当たり前だ」
「でも、実際には男女平等ではないでしょう。仕事以前に教育もそうだわ。女が入れる大学自体、ほとんどないのはどういうこと?」
「それは法律がおかしいんだ。将来どんな仕事につきたいか、そのために必要な知識を得るのが高等教育の目的であって、もとより男女差を設けるのが間違っている。将来、すなわち、どう生きるかだろう。生きるのに男も女もない。誰しもが一個の人間なんだ」
次第に貞雄の語調が熱を帯びてきた。
「高い教育を受けて仕事を持ちなさい。己の目で社会を見て、自分の頭で物事を判断できるようになるには、高等教育を受けるのが最短の道だ。嘉子の嘆き通り、今はまだ女を受け入れている大学は稀だが。まあ、いずれ増えるにしても、指をくわえて待っているのはつまらん」
「そうでしょうけど」
つい口が尖る。
実際、男女同等なのは小学校まで。女は中学校に進めず、女学校に入るしかない。いくら成績が良くても、女の嘉子が入れるのは専門学校だけ。国がそういう考えなのは事実だ。
貞雄は真顔になった。
「不平を唱えても変わらない。で、どうする。進学するか? それとも、どうせ女だからと拗ねて家庭に入って、亭主の三歩後ろをついていくか? 想像がつかないがね。どちらかといえば、嘉子は三歩後ろをついていくどころか、さっさと亭主を追い越して前を歩きたがる性分だろう。――おい、そんな顔をするな。褒めているんだから。ともかく、嘉子は普通のお嫁さんになるな」
ますます古居先生には聞かせられない。
良家の子女が集まるお茶の水高女では、女はいずれ家庭の主婦におさまるものとされている。名門の女学校だけに生徒はみな優秀だが、進学を希望する者は少数派だ。早ければ在校中に縁談がまとまり、順々に結婚していく。
「高等学校で専門的な知識を身につければ、ものを考えるときの基礎ができる。そうすれば畑違いの話を見聞きしたときにも、自分の持っている知識を使って嚙みくだき、理解できるようになる。学校のお勉強をしているうちはピンと来ないかもしれんが」
「そんなことないわ。パパのおっしゃる意味はわかります」
「ほう、わかるか」
「もちろん」
長女として、物心ついたときより貞雄の薫陶を受けてきた。小学校から常に優等生で通してきた嘉子は、勉強で知識が身につく喜びも、学ぶ意義も承知しているつもりだ。女学生だからと、甘く見られては癪に障る。
「つまり、自分の言葉を持てということでしょう。自分で考えて、おかしいと思ったときは、きちんと声を上げなさいということだわ。──たとえパパがおっしゃることでも」
「その通りだ。よくわかっているじゃないか」
「パパの教育がよろしいものですから」
「で、嘉子は何になりたい」
いくら貞雄が男と女は同等だと言おうと、世間に仕事を持つ女は稀だ。
せいぜい師範学校を出て教師になるか、医者になるか。
現実的な話として、女がつける専門職といえばそれくらいだ。
弟たちの勉強を見てきたから、たぶん教師には向いている。数学が得意だから、医者にもなれそうだ。
でも――、とやはり思ってしまう。
実社会では、女が専門職の資格を持つのは、親や夫に万一のことがあったときのための備えであり、積極的に外へ出て自立するための手段ではない。そこが貞雄のいたニューヨークとは異なる。
「パパ、さっそくだけど抗議します」
「何だね」
「どうして女は弁護士になれないの?」
「嘉子は弁護士になりたいのか」
「ええ、そうよ。法律を武器に喧嘩ができるなんて面白そうだもの」
貞雄が苦笑いする。
「あら、違った?」
「間違いではないな。喧嘩という言い方にはいささか語弊があるが。――それで? 抗議の内容を聞こうじゃないか」
「常々パパは仕事に男も女もないとおっしゃるけれど、法律で女は弁護士になれないと決まっているでしょう。そんな矛盾がまかり通っているのはおかしいわ」
もっと言うなら、さっきの「男と肩を並べて働く」もそうだ。
男と女が同等なら、わざわざそんな言い回しをすることもない。それこそ社会が女を男の下に置いている証左だろう。
「ふむ」
貞雄は立ち上がり、窓際に据えた机に向かった。新聞を手に戻ってくる。
「読んでみなさい」
今日の新聞ではない。
こんな古い日付のものをどうして取っておいたのだろうと、訝しく思いながらざっと目を通し、嘉子は息を吞んだ。
法改正の記事だった。次の国会で弁護士法が改正される見通しだと書いてある。
それまで弁護士になれるのは成年の男子のみと法で定められていた。弁護士法第二条第一項に「弁護士たらんと欲する者は……日本臣民にして民法上の能力を有する成年以上の男子たること」と規定されているからだ。法改正により、この条項から「男子」が削除され、「帝国臣民にして成年者たること」になる。
新聞から目を上げ、貞雄を見た。
「どういうことか、わかるな?」
「ええ――」
我知らず頰が熱くなる。
己の無知を恥じる気持ちと、興奮が半々――いや、興奮のほうがずっと大きい。
成年男子と規定した条項が削除、つまり性別を問われなくなるわけだ。成年に達していればよし。そういうことだ。
「わたしも弁護士になれるのね」
「試験に受かればな」
「受かるわよ」
むっとして言い返す。
自慢のようだが、嘉子は試験が得意だ。お茶の水高女へ入るときも二十倍の倍率を突破し、入った後も優秀な成績を取っている。男に生まれていたなら、貞雄の出た東京帝国大学を目指していたはずだ。
「そうだな」
貞雄はうなずき、
「お前の頭がいいのはパパだって百も承知だ。しかし、そう簡単ではない。脅かすわけじゃないが、司法科試験は難関だ。帝大法学部の連中でも半分は落ちる。女学校の勉強とは比べものにならん」
法学部卒の貞雄だけに説得力がある。
が、それで怯む嘉子ではない。
「上等だわ。受けて立ちます」
壁は高いほうがいい。むしろ低い壁は容易に越せてしまうからつまらない。難関と聞き、却(かえ)って闘志が燃えてきた。
「よし。それでこそパパの娘だ」
貞雄は満足そうに目尻へ皺を寄せた。しめしめ、と言いたげな表情だ。ひょっとすると、嘉子の闘志を搔き立てるために、わざと脅しをかけたのかもしれない。
あらためて新聞の日付を見る。貞雄は嘉子に読ませるつもりで、手許に取っておいたのだろう。あるいは、嘉子が自分で法改正の記事を見つけ、質問をしてくるのを待っていたのか。
「新聞を読みなさい」
「――はい」
「弁護士法に改正の動きがあることは、しばらく前から新聞で取り上げられていた。目を通していれば、恥ずかしい思いをしなかったはずだ」
耳が痛い。後者だった。貞雄は、嘉子が法改正に自ら気づくことを期待していたのだ。
こんなに堂々と記事が出ているのに、見当違いな怒りをぶつけたことが情けない。
「明日から、いえ今日から、わたしも新聞を読みます」
「そうしなさい。新聞を読めば、社会の動きがつかめる。三面には目を覆いたくなるようなひどい事件も載っているが、それもまた社会だ。生きていれば避けて通れん。まして弁護士になりたいなら尚更だ」
貞雄の言う通りだ。
弁護士になれば傷害事件や殺人事件を扱うことになる。警察の捜査記録や現場写真を目にすることも多いだろうから、今のうちに新聞で免疫をつけておいたほうがいい。
ああ、悔しい。これまで知らずに諦めていたことが。女は弁護士になれないと思い込んでいた。法律で決まっているなら仕方ないと、受け入れていた。そういう諦めのいい自分が情けない。それでは自分の頭でものを考えているとは言えない。
「ねえ、パパ。世の中って変わるのね」
「世の中は日々動いているからな」
「良い時代に生まれたのね、わたし」
少し前だったら、どんなに頑張っても女は弁護士にはなれなかった。声を上げた人のおかげだ。誰かが女のために頑張り、世の中が法改正に動いた。
「ああ。何であれ変わっていく。良いことも悪いことも、全部な。弁護士法の改正も変化の一つだ。きっとこれから、女が社会へ出ていく門がどんどん開いていく。だから、嘉子――」
貞雄はぐっと首を前に出した。
「社会が矛盾を許しても、簡単に諦めないことだ」
さっきの問いの答えだ。女が弁護士になれないのはおかしい、と嘉子が不服を唱えたことに対して、貞雄が己の考えを述べている。
「やりたいことがあるなら門を叩きなさい。人より達者なその口で大いに文句をつけるといい。喧嘩になれば嘉子は強いからな。いずれ道は開けるはずだ。――何だ、その顔は」
「いいえ、別に」
「さっきの繰り返しだが、褒めているつもりなんだ。いくら成績が良くても家庭向きの娘だったら、進学しろとは言わんよ。そうか、嘉子は弁護士になるのか。良い仕事を見つけたな」
自ずと卒業後の進路が決まった。
高等試験令による司法科試験を受けるには、高等学校または文部省の指定する専門学校に入らねばならない。それらの学校に入り、在学中もしくは卒業生となって試験を受けるよう、改正弁護士法で定められている。
まずは、法律を学べる高等学校か専門学校に入る必要がある。
といっても、日本で女子に門戸を開いている大学はわずかだ。
国立では九州帝国大学と東北帝国大学、私立では同志社が特定の女子専門学校の卒業生に限り、入学を認めているのみである。東京には、女子の入学を認めている国立大学はない。
唯一女が入れるのは、私立の明治大学だけ。
昭和四(一九二九)年、明治大学に女子部ができた。
弁護士法が改正されることを察した大学が、女子が司法科試験を受けられるよう、法律専門学校を作ったのだ。女子部を卒業すれば、明治大学法学部への入学を認められる。それでようやく司法科試験を受けるための資格が手に入る。法学部で法律を学び、在学中あるいは卒業生の資格を得て、司法科試験に臨み、合格すれば弁護士になれる。
長い道のりだ。貞雄が脅すくらいだから、試験も相当に難しいのだろう。それでもなお、胸が躍る。
早くも、まぶたの裏に書類の詰まった風呂敷を抱え、颯爽と裁判所へ入っていく己の姿が見えるようだ。
女中がコーヒーのお代わりを運んできた。話している間に冷めてしまったからと、貞雄が命じたのだ。
「お前も飲んでみるか」
その日、嘉子は初めてコーヒーを飲んだ。眠れなくなるから駄目、と禁じられていた大人の飲み物である。
「うまいか?」
「ええ、とっても」
興奮しているせいか、味はあまりよくわからなかった。とにかく舌が火傷しそうに熱かったのを憶えている。
手回しのいい貞雄は、明治大学女子部の入学手続きの書類も用意していた。信子が法事で家を留守にしている間に、話を決めてしまうつもりだったのだろう。
何のことはない。貞雄は端から嘉子を弁護士にする気だったのだ。
その話し合いをするために弟たちを出かけさせ、馴染みの書生たちにも出入りを遠慮してほしいと申し伝えていたと、後から聞いた。さすがニューヨーク帰りの銀行マンは目下の者を動かすのが上手い。
嘉子は貞雄に乗せられ、女学校で成績証明など必要なものをととのえると、翌週にも明治大学女子部の入学手続きを済ませてしまった。
それが先月のこと。
法事を済ませて丸亀から戻ってきた信子は、古居先生からの注進で、嘉子が明治大学女子部へ入ると知り、絶句した。
以来、ひと月に亘って反対し続けている。それが信子の不機嫌の理由だ。
もう入学手続きは済んでいるというのに、取り消しなさいとしつこい。
法律を勉強するような娘は怖がられて、嫁の貰い手がなくなる。お茶の水高女を卒業した切符があれば、どんな家にも胸を張って嫁げるのにもったいない、と。
そうだろうか。
嘉子にしてみれば、法改正の機運に乗らないほうがもったいないことだと思う。縁談の数が減っても、どうということはない。いざとなったら、結婚相手も自分で見つければいいのだから。
信子の言い分には承服できない。家庭の主婦だから、世の中が見えないのだ。法律が変わることも信子は知らない。要するに頭が古いのだ。社会へ出て働いている貞雄とは違う。
そんなふうに反発心を抱え、鼻息荒く登校したのだが、意外にも女学校の友だちは信子と同じ反応を示した。
******
続きが気になる方はこちらもご覧ください。
嘉子は、明治大学専門部女子部で学び、日本初の女性弁護士の一人となる。
世間からも注目をされていたが、戦争に突入する時代に弁護士となった嘉子は、
活躍の場を得られないまま終戦を迎える。
戦争で全てを失った彼女に残されたのは、かつて学んだ法律の知識だけだった。
多くの困難を乗り越え、念願の裁判官に就任した嘉子と彼女を慕う仲間たちは、
苦境から抜け出せない人々を救うために、政治の力だけでは解決できない
問題に向き合っていく。

潮文庫『裁判官 三淵嘉子の生涯』伊多波碧著、定価:880円(税込)、発行年月:2024年3月、判型/造本:文庫判/272ページ
商品詳細はコチラ
******
作家
伊多波碧(いたば・みどり)
新潟県生まれ。信州大学卒業。2001年、作家デビュー。05年、文庫書下ろし小説『紫陽花寺』を刊行。23年、『名残の飯』シリーズで第12回日本歴史時代作家協会賞シリーズ賞を受賞。著書に『恋は曲者 もののけ若様探索帖』『リスタート!』『父のおともで文楽へ』など多数。