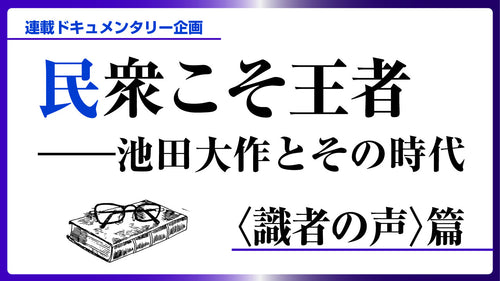新連載小説「ナースツリー」第1話
2024/07/19創価大学看護学部を舞台のモデルにした新連載小説「ナースツリー」
広大な敷地に自然を色濃く残したキャンパスで学ぶ大学四年生の高階優美。命と向き合う現場にまさに飛び込もうとする中で彼女は葛藤をかかえる……。
第1回連載の内容を特別配信します。
(月刊『パンプキン』2024年8月号より転載)
高階琴美(たかしな ことみ)…優美の妹で、潰瘍性大腸炎を患う。
藤巻信也(ふじまき しんや)…文学部の大学院生。
早瀬千帆(はやせ ちほ)…看護学部の同期生。
黒田咲良(くろだ さくら)…看護学部の同期生で、大学の裏手に住む。
夏
ペダルをこぐ足に力をこめる。長い急な上り坂の頂上は見えていた。荒い息を吐き、立ちこぎで右に左に上体を揺らしながら、木漏れ日のなかを進む。蝉のせきたてるような鳴き声が、桜並木のそこかしこで響いている。
真夏の強い陽射しを浴びた二階建ての学生アパートの前を通り、キムチチゲののぼりの立つ食堂を過ぎ、揺らめくアスファルトの路面を見つめながら、渾身の力で足を踏みしめる。
坂を上りきるまで自転車を降りてはいけないと、高階優美はかたくなに決めていた。
妹の琴美は生きるためのペダルを必死でこいでいる。だからわたしもこぎつづけなければならない。わたしの挑戦が終われば琴美も自身の病に負けてしまうかもしれない。
不合理と言われるかもしれないが、それはどうしても譲れない優美の誓いだった。
優美がひとり暮らしをしている駅裏のアパートから滝山大学までは、丘陵の二つの峠を越えなければたどりつかない。
すでに三十分以上を、電動アシストのない自転車で上っては下りをくりかえし、これが最後の、そしていちばん長い坂だった。
生垣の向こうに、大学と隣接する美術館の水色の屋根が見えた。あと少しなのに、膝が震えて力がこもらず、ペダルがなかなか回転してくれない。けれど降りるわけにはいかない、と自分自身に強く言いきかせる。
闘病する琴美の、ベッドに横たわる細い身体。
窓の外を見つめる憂いをおびた横顔。
琴美のように懸命に病と闘う人の力になりたいと、看護の道を志し、鳥取県から上京して、滝山大学に増設された看護学部に、一期生として入学した。
あれから三年三か月。理想ばかりが膨らむけれど、その大きさに比例するように不安や劣等感も優美の気持ちを圧迫するようになっていた。
自分に負けてはいけないという思いが、ペダルを踏む優美をあと押しする。琴美の面影を心のなかでかき抱き、腹の底に力をこめると、一気に坂を上りきった。
よろめくように自転車を降りる。荒い息を吐いていると、汗が胸元を流れ落ちる。木々の葉から放出される新鮮な香りが、ゆるやかな流れとなって、頬を通り過ぎた。
大きなアリが虫の死骸を運んでいる。そのアリがタイヤの前を横切り、植え込みへと消えていくのを見送るあいだに、充分な酸素が身体をめぐり、呼吸が整ってきた。
優美は前かごに押し込んだリュックに目をやった。
分厚い参考書がゆるく開いたファスナーの間からはみ出ようとしている。どこへ行くにも必ず持ち歩く参考書。
都内の実家から大学に通う早瀬千帆の家で、入学した年のゴールデンウィークにそのカバーを一緒に作った。アイロンを借り、裁縫用接着剤を使って、トロピカル柄の生地で作り上げたのだった。
あのころは、理想的なナース像だけを追い求めて、まっすぐに進んでいけると思い込んでいた。けれど学べば学ぶほど、現実は厳しいと思い知らされた。
無邪気にスタートしたあの日からたったの二か月。七月に迎えた最初の実習で、甘い考えはあと形もなく吹き飛ばされた。
身につけなければならない技術は気が遠くなるほど多く、立ち止まって物事を考える余裕がないほど、看護の現場は複雑で過酷に見えた。
そして四年生になったいま、手作りのカバーを作ったあのころのことは、はるか彼方の昔に思えた。
講義や実習を重ねるたびに分厚くなっていった参考書みたいに、葛藤や失意や不安が、前向きな気持ちのうえに重く積みかさなっていった。
何度これを捨ててしまおうと思ったことか。
でも、捨てることはできず、四年目のいまもこうして持ち歩いている。

どこからかざわめきが聞こえた。尋常ではない、切羽詰まった調子をはらんでいるようにも感じられた。
視線を周囲に泳がせる。声のほうへ向かった。
中央分離帯になっている植え込みで向日葵が鮮やかな大輪の花を咲かせている。こんなところに向日葵が、と思った瞬間、悲鳴に近い叫び声がした。見ると、美術館の前の看板の下に、人だかりがあった。
「大丈夫ですか」
「救急車、救急車」
言葉がはっきりと聞こえた。
五、六人の学生がだれかを取り囲んでいる。
ハーフパンツにスニーカーを履いた男子学生。サンダル履きの女子学生。二人の足の隙間から、横たわっている灰色の洋服が見えた。
まさか。自分がこんな場面に居合わせるなんて。内心激しく動揺しながらも、優美は急いで人の輪に近づく。
「看護学部の学生です。あけてください」
かきわけて輪のなかに入ると、グレーのスラックスを穿き、口ひげを生やした高齢者が仰向けに倒れていた。
優美はとっさにしゃがむと、スラックスのベルトをゆるめた。
「大丈夫ですか」
優美が声をかけても返事がない。顔面は蒼白だった。
「救急車は呼びましたか」
取り巻いている数人の学生に向かって問いかけると、テニスラケットを持った女子学生が「呼びました」と不安気に答えた。
優美は脈を取り、呼吸を確認する。倒れた人は苦しそうにうなると、突然激しく嘔吐した。
学生たちの間からどよめきが起きる。優美は身体に手をかけ、すばやく横向きにし、背中をさすった。
「大丈夫ですからね。がんばってください」
「痛い……頭が」
唇から、声が絞り出される。
優美は嘔吐がおさまるのを見はからって、リュックからハンカチを取り出し、吐しゃ物で汚れた口をぬぐった。頭痛と嘔吐……くも膜下出血かもしれないと思う。
倒れた人がかぶっていたのだろう、しゃれたパナマ帽が道に転がり、美術館の入り口に向かうスロープのあたりで止まっていた。
「救急車がきたら場所がわかるように誘導してください」
優美が指示すると、すぐに二人の男子学生が取り巻きの輪から動いた。
二人の後ろにいた男性の、陰りのある青白い顔が、優美の視界に突然入り込んだ。優美はなぜだかわからず動揺し、その男性に不思議な懐かしさと、強く惹きつけられる思いを抱いた。
その気持ちをあえて深追いしないために、倒れた人に声をかける。
「すぐ救急車がきますからね。がんばってくださいね」
手をしっかりと握り、呼びかけた。
看護において、人の手がいかに大きな力を発揮するかを、つね日ごろから学んでいた。心をこめて、さすったり握ったりするだけで、苦痛を緩和することができるのだと。心拍が整い、血圧が安定するのだと。
いままさに、その学びを実践するときなのだと思った。
大学へ向かう自転車の数は次第に多くなっていた。
「自転車がぶつからないように交通整理もしてください」
優美が声を張り上げると、救急車の誘導に立った二人がすぐさま大声で「了解です」と応答してくれた。
手はかすかに震えはじめていた。顔からはさらに血の気が失せ、白さを増し、蝋人形のように見えた。
優美は気づかわしげに、転がったままになっているパナマ帽を見た。が、すぐに苦しげなかすれ声が耳に飛び込み、視線を戻す。
「もうすぐですよ、すぐに救急車がきますからね」
焦りと祈りの入り混じった、これまで経験したことのない切迫した気持ちで声をかけ、背中をさする。
なす術もなく苦痛に歪んだ顔をじっと見ていると、乾いた唇が何かを言おうとしてかすかに動いた。
「なにか……」
優美は口元に耳をよせる。
「タスマニアに……」
声は小さかったが、それでもかろうじて聞き取れた。
優美の手に伝わる倒れた人の手の震えはさらに大きくなった。
救急車が一刻も早く到着しますように、この方を救えますように、間に合いますように。
心で強く願いながら、大丈夫ですよ、がんばってください、あと少し、しっかりしてくださいね、と思いつく限りの言葉を投げかけつづける。
サイレンの音が小さく聞こえ、それはすぐに近づいてきた。男子学生が、救急車のなかに聞こえもしないのに「ここです」と声を張り上げる。
サイレンを止めた白い車両が停車する。救急隊員が、ストレッチャーを持って駆けつける。
救急隊員に呼吸、意識、嘔吐などの状況を説明し、連絡先を伝えた。
そのとき、優美の目の前にパナマ帽が差し出された。顔を上げると、さっきの男性が相変わらず心配とも憂いともつかない表情をたたえて優美を見ていた。優美はパナマ帽を受け取り、会釈を返す。
扉を閉める直前、「この方の帽子です。たぶん、大事な……」と言いながら隊員にパナマ帽を手渡した。
のどが渇いたので、メインタワーへ向かった。

十三階建てのメインタワーは大学の敷地内の一角、小高い丘の上にどっしりと腰を据え、大学全体を見守っているような佇まいの建物だった。その最上階は、食事や喫茶ができるエリアになっている。
優美は窓に向かったカウンター席に、水滴のしたたるアイスティーを置いて座った。ふと真下を見ると人影が粒のように見えて、身がすくんだ。あわてて視線を遠くへ向ける。
入道雲が紺碧の空に浮かんでいる。
滝山大学は、一般の車道もはさんで約三十万坪にもおよぶ、雑木林を多く残した広大な敷地を有していた。
その敷地内は、大きく四つのエリアに分かれていた。
敷地のほぼ中央部に、十五階建てのグローバルタワーがそびえ立っている。
正門からグローバルタワーまでの間に、理工学部棟、中央図書館、古代ギリシャの殿堂を思わせる大講堂が並ぶ。
車道をはさんで反対側に女子短大、一階に学生食堂の入る大教育棟、売店を備える学生ホール、柔剣道場などがあった。
大講堂裏の坂を下ったところには、自然豊かな池と女子寮も擁していた。優美も一年生のときは、この寮で仲間とともに暮らした。
北側を走る新街道に面した滝山門から入ると、すぐ右手にグラウンドがある。
トラックの直走路部分に四階建ての看護学部棟が、コーナー部分に学生自治会やクラブの部室などがある五階建ての学生センターが建っている。
そこからつづく小高い丘の部分に、いま優美がいるメインタワーがある。
メインタワーの正面玄関を出ると、前方に新世紀橋があり、一般道をまたいで、その先の総合体育館や野球場、テニスコートなどのスポーツ施設エリアへとつながっている。
さらに、メインタワーから西側に道を上がっていくと、奥まった先に男子学生の寮が点在していた。
多摩丘陵の自然を色濃く残した敷地内は、新入生を迎える季節には木蓮、花桃、レンギョウ、雪柳、ミツバツツジなどがそこここで咲き薫り、雑木林のなかからは鶯やホトトギスの鳴き声が軽やかに響き渡る。
桜はやがて葉桜となり、木々の緑が人々に憩いを与えるための濃い影を作りだす。
季節はゆるやかに秋へと移りかわり、一日の寒暖差が大きくなるころには楓が燃えるように色づき、池のほとりでは山茶花(さざんか)が咲き、モズが高い木の梢で甲高い鳴き声を放つ。
そして、年が明け試験が終わると大学は春休みに入り、閑散とした構内が、ときにはまっ白な雪で覆われたりもした。
随所に点在する広場には、トルストイやマリー・キュリーなどの像が、学生たちを導こうとするかのように泰然と佇んでいた。
この広い敷地を縦横に駆け抜けながら青春を過ごして、いよいよ看護の世界へ飛び出そうとしている。友人たちと交わした会話、笑顔、熱い思い。命の底に宝はたくさん積ませてもらった。
でもまだ心は決めきれていない……と優美は苦々しく思った。
(つづく)
作家
絹谷朱美(きぬたに・あけみ)
鳥取県生まれ。創価大学卒業。2014年「四重奏」で第17回長塚節文学賞短編小説部門大賞受賞。18年「光路」で第4回林芙美子文学賞佳作受賞。大学図書館のスタッフとして勤務するかたわら、執筆活動に臨んでいる。