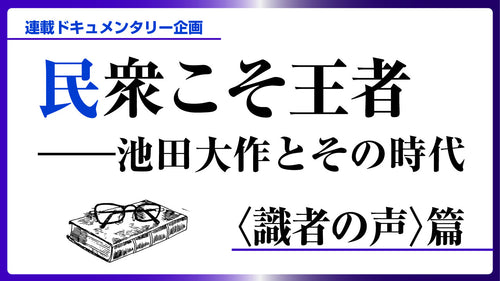天井はサラリとすり抜けるのが〝サワコ流〟(鎌田實×阿川佐和子)
2024/10/04鎌田先生の診察を受けるような気分
その日、僕はいささか緊張していた。インタビューのプロフェッショナルに対してインタビューをすることになったからだ。
〝その人〟は週刊誌で30年以上にわたって人の話を聞くことを仕事にしており、著書の『聞く力』(文藝春秋)は大ベストセラーになっている。〝その人〟とは阿川佐和子さんだ。
お会いする1週間前からは、阿川さんの著書を熟読する日々を送り、すっかりサワコ・ワールドに浸ることになった。阿川さんからは過去に何度かインタビューを受けたことこそあるものの、その逆は今回が初めてだ。僕も少し緊張していたが、それはどうやら阿川さんのほうも同じだった。「ちょっと心配。なんだか鎌田先生の診察を受けるような気分です」――。インタビューはそんな阿川さんの一言からスタートした。
阿川さんの本をまとめて読んでみて気が付いたのだけど、彼女の文章にはいつも〝ひと捻り〟がある。エッセーを書き始めたのはテレビの仕事を始めた1980年代のこと。大文士 ・阿川弘之の娘ともなれば、若いころから名文を書いていたのだろうと思いきや、話を聞くとどうもそうではなかったようだ。本人の言葉を借りると、若いころの阿川さんは「小説家の娘のくせに漢字は読めないし、書けない。常識も知らない。世界のことが何も分からない。新聞も分からない」という感じだったそうだ。
父から教わった基本中の基本
父娘の貴重なエピソードがある。1983年に阿川さんはある雑誌から原稿執筆の依頼を受ける。父親について原稿用紙7枚を埋める仕事だった。依頼書を父親に見せると「ふーん、俺のいまの連載よりも原稿料がいい。なんなんだこれは」と、むっとした様子だった。
立派なことを書ける気がせずに断るつもりだったが、大作家よりも素人の原稿料が高いことが面白くて、友人にその話をした。すると「立派な文章なんて誰も望んでないんだから書いてみたら?」と背中を押され、それが決め手となって書くことにしたそうだ。
原稿にはいつも友だちに話していた父親の悪口を書いた。ところが原稿を提出するために家を出るタイミングで、運悪く父親に見つかり、原稿のチェックを受けることになる。意外にも、内容のことには触れられなかった。タイトルや氏名を書く位置などの原稿用紙の書き方や、語尾や「てにをは」の重複など、作文の基本中の基本に対する指摘だけだったのだ。
「『だった』が3回続くと『機関銃じゃないんだから』、『に』が重複すると『ニイニイゼミじゃないんだから』って。ただ、ある程度直したら『これ以上直すと、俺の文章になってしまうから、適当に清書して持っていきなさい』と。
内容について指摘しなかったのは、自分も散々家族のことを書いてたから、負い目があったんじゃないですかね。私たち家族は本当に酷い目に遭ってましたから」
父の添削は、阿川さんが雑誌で連載を持つようになってからも続いた。「流行り言葉を使うとすぐに腐る」「作文に慣れてきたら筆に流されるから気を付けろ」「常に目上の人がお読みになると思って書け」――。指摘はいつも具体的だった。
阿川さんがスランプに陥ったときのこと。書くことがなくなり、担当編集者からはっきりと「最近の阿川さんの文章は面白くないですね」と言われ、すっかり落ち込んでいた。そのとき、弘之さんからは意外な言葉をかけられたそうだ。「そういうことはある。書けなくなることはある。野球だって、好打者でも3割3分だ」と。
父の文章に関するさまざまな指摘は、いまも阿川さんの耳朶に残っている。僕が「弘之さんの指摘が阿川佐和子の文章をつくってるんだね」と言うと、彼女は肯定も否定もせず、こう言って笑った。
「目上の方に読まれたら、呆れられることばかり書いてますけどね」
現場で言われた「無能な頷き役」
阿川さんの人柄やキャリアを見ていると、ガラスの天井を〝破ってきた〟というよりも、スルッと〝すり抜けてきた〟といったほうが適切な気がしている。
もともとテレビの仕事をするつもりはなかったそう。父親と一緒に写った写真を見たプロデューサーから声がかかり、1981年に報道・情報ワイド番組のリポーターとしてデビューする。そこから約10年間は、情報番組のアシスタントやキャスターなどの仕事が続く。
「初めてテレビの仕事を持ちかけられたとき、何も知らない私に何が務まるのかってプロデューサーに申し上げたんです。するとその方は『座っていれば結構です』って。私、男尊女卑の父親に育てられていますから、『もっと一人前の人として扱ってほしい』なんてさらさら思わなかったんです」
ところが、いざ仕事をしてみると、いまで言うパワハラの嵐に辟易する。現場では毎日のように怒鳴られ、「無能な頷き役」と揶揄する声も耳に入ってきた。
「親の七光りで仕事を始めたこともあるし、とにかく何度も辞めたいと思いましたよ。だけど、一つの番組が終わったら、また次の番組からお声がけいただいたり、文章を書いてみると連載の打診があって編集長が男前だったから受けてしまったり、とにかく恵まれているとしか言いようがない」
仕事に関して自分の意志はほとんどなかった。時は男女雇用機会均等法の施行(1986年)もあって、女性の自立が促された時代である。それでも、自発的にやりたいことは特に見つからず、父親やプロデューサーからは「専門を持て」と何度も説教を食らった。
「でも、『女は馬鹿だ』って言われて育ってきてますからね。馬鹿のまんま安穏と生きているほうが楽だったんです」
本人はそんなふうに言うけれど、自分で売り込まずとも仕事が次々に舞い込んでくるというのは、阿川さんの魅力に皆が引き込まれているからだろう。その魅力の1つが、いい意味で肩の力が抜けた阿川さんの空気感だと僕は思う。まさに、ガラスの天井を破るのではなく、スルッとすり抜けていく軽やかさだ。
スルッとすり抜けるガラスの天井
ガラスの天井をスルッとすり抜ける軽やかさ。そんな阿川さんの空気感がよく表れたエピソードがある。
それは「ビートたけしのTVタックル」でのできごとだ。
石原慎太郎さんや三宅久之さんらと激論を交わしていた田嶋陽子さんが「大体、あんたらが女を馬鹿にするからだ!」などと憤激する場面があった。田嶋さんはあまりの怒りに目に涙を浮かべて、「私はもう帰る!」と収録中にもかかわらず席を立った。
隣に座っていた阿川さんは慌てて田嶋さんの机にあった資料などをまとめて、手渡そうとする。すると田嶋さんは「本当に帰ってほしいのか! アンタは育ちが悪い!」と言って、受け取った資料で阿川さんの頭を引っ叩いたのだ。
「別に帰っていただきたかったわけじゃなくて、お帰りになるっておっしゃるんだもん。だから、ただ荷物をまとめて差し上げたんですけどね。育ちが悪いというのは、おっしゃるとおりですけど(笑)」
おそらく田嶋さんは男性出演者らの女性蔑視とも取れるものの見方に怒っていたのだろう。そして、その分厚い壁を破ろうと声を荒らげたわけだ。そのすぐ隣で、いとも簡単にスルッと壁をすり抜けてしまうのが阿川さんなのである。
恨みつらみを笑いに昇華する
阿川さんも世間に蔓延る男尊女卑とまったく対峙していないわけではない。著書の『強父論』(きょうふろん・文藝春秋)に代表されるように、父親に対する恨みつらみを笑いに昇華しながら書き綴ることで、見事に彼女自身の逞しさを表現している。
いわく、父・弘之さんにとって妻は第一の使用人、娘は第二の使用人だったそうだ。阿川さんは、中学・高校は卓球部、大学はテニス部に所属していたため、休日に練習や試合で家を空けることがあった。試合会場に父親から電話がかかってきて、「すぐに帰ってこい」と言われることもままあったという。
「とにかく君主制なんです。家に帰ったところで何か用事があるわけではない。『控えてろ』と。『おい』と言ったときに『はい』って出てくる娘が理想だったんです」
生前の弘之さんは妻と娘に厳命した。文士が逝くと妻子に対して「1冊書きましょう」という話が必ず来るが、絶対に受けるな。身内が故人を讃えることほどみっともない話はない――。
弘之さんが亡くなったあと、案の定、編集者が阿川さんのところにやってきた。父親から言われたことを伝えて断ろうとすると、編集者は言う。「讃えなければいいんじゃないですか」と。
「なるほど、それはありだなと思いましたね。それで父の悪口だけを綴ったのが『強父論』なんです。よく『なんだかんだ言って、阿川さんはお父さまのことを愛してらっしゃる』なんて言われるんですけど、それはちょっと過大な解釈なんです。率直に思っているのは、父ほどネタになる人材はいないということ。思い出すたびに腹が立つし、本当に酷い目に遭ったんだけど、その1つ1つがネタになるんです。素晴らしい体験や感動的な経験を書いたって、読者の皆さんは喜んでくれませんからね」
阿川さんがあるイベントに参加したときのこと。遠藤周作の息子の龍之介さんと、北杜夫の娘の斎藤由香さん、それから矢代静一の娘の朝子さんが集い、父親の思い出を語るというイベントだった。出てくるのは決まって酷い目に遭った思い出話。結局、酷い目自慢の会になった。
「あるときに父から『遠藤周作や北杜夫の家と比べれば、うちはまだましだよ』と言われてね。母も私も納得したんです。その話をイベントですると、遠藤龍之介さんが『うちも同じことを言ってた。北さんや阿川さんの家よりはましだよ』なんて言うんです。もう笑っちゃいましたよ。みんな同じことを言ってたんです」
先にも触れたけれど、阿川さんのすごいところは、弘之さんに対する恨みつらみを、ただ単に書き綴るのではなく、笑いに昇華するところだと僕は思う。これは誰にでもできる芸当ではない。

40歳を目前に〝全取っ換え〟
かつては仕事に対して受け身だった阿川さんが、突き抜けた瞬間はいつだったのだろう。僕が注目したのは、40歳になる直前に経験した1年間のアメリカ遊学だ。40歳が見えてくる時期というのは、普通であれば腰を据えることを考えるはずだ。なぜ阿川さんは遊学をしたのだろうか。
「そもそも女性キャスターの仕事に一生懸命になれない自分がいたり、犠牲者のお宅に押しかけて、遺族にマイクを向けて話を聞く仕事に疑問を感じていたりして、一度、テレビの世界から離れてみようと思ったんです。ただ、理由がないと仕事を辞めさせてもらえない。それでアメリカへ行くことにしました」
スーツを着る必要もなければ、ばっちり化粧をする必要もないワシントンでの生活。春夏はレギンスにTシャツ、秋冬はレギンスにセーターを着て、ラフに暮らした。特に印象に残っているのは、とあるホームパーティーでの出来事だ。1人のおじさんが阿川さんに尋ねてきた。佐和子は何をしにアメリカに来たのか。キャスターの仕事が合わないと思ったから〝全取っ換え〟をするつもりで来た。そう言うと、おじさんは阿川さんのことを褒め讃えてくれたそうだ。
「日本では『40歳を前にして何を考えてるんだ』と言われたんですけど、そのおじさんはこう言うんです。『それは素晴らしいことだ。人生はいくつになってからでも、全取っ換えが必要なんだ。取り換えたいときに取り換えればいい』って。名前すら覚えていないおじさんだけど、なんかその言葉を聞いたときに涙が出そうになってね。
1年間のアメリカ生活を経て帰国をすると、少しだけ景色が変わっていた。一番大きかったのは、仕事が楽しくなったことだそうだ。『週刊文春』の長期連載「阿川佐和子のこの人に会いたい」が始まったのは、ちょうどアメリカから帰ってきた直後のことだった。
いまの阿川さんを知る人は、冒頭に紹介した彼女自身が若いころの自分について語った言葉をにわかには信じられないはずだ。
「小説家の娘のくせに漢字は読めないし、書けない。常識も知らない。世界のことが何も分からない。新聞も分からない」
長い目で見たときに、これほど〝全取っ換え〟に成功した人も珍しいのではないだろうか。
阿川さんには、実に面白い最近の話もうかがったので、次回も彼女のことを書こうと思う。
(対談の続きは、月刊『潮』2024年11月号をご覧ください)
************************
医師・作家
鎌田 實(かまた・みのる)
1948年東京都生まれ。東京医科歯科大学医学部卒業。74年に長野県の諏訪中央病院に赴任。88年、同病院の院長に就任。2005年より名誉院長。著書に『シン・がんばらない』(小社刊)など多数。
【ゲスト】
エッセイスト・作家
阿川佐和子(あがわ・さわこ)
1953年東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒。テレビでは「ビートたけしのTVタックル」の進行役、また2017年に放送のドラマ「陸王」などで女優として活躍。著書に『聞く力』『レシピの役には立ちません』など多数。