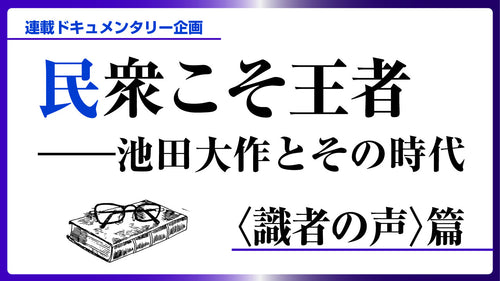小さな神たちの祭り ためし読み
2025/03/05千葉雄大さん主演で大きな話題となった同名ドラマを作者である内館牧子さん自らの手で書き下ろした小説。
文庫版発売を記念して冒頭部分を抜粋してご紹介します。
******
第一章
外国にいた日本人が成田空港に降り立つと、感じるそうだ。
「日本は醤油の匂いがする」
それは「帰って来た……」と思わせるのだろう。
仙台は杜の匂いがする。
街の真ん中を涼やかな広瀬川が流れ、定禅寺通りの並木は行きかう人々を緑に染める。青葉山や八木山の杜は深く、都はその匂いをさせている。
谷川晃(あきら)は、仙台から二六キロほど南の町、亘理町(わたりちょう)で生まれ育った。
亘理は東は太平洋の黒潮に、西は阿武隈高地、北は阿武隈川に囲まれた美しい町だ。仙台から常磐線でわずか三〇分ほどに位置しているが、表情はまた全然違う。
太平洋沿岸部ということで、海産物の宝庫である。さらに、いちごの産地として、その名は全国に轟く。
町の至るところに栽培ハウスが並ぶ。
亘理に帰って来た人は、きっと感じるだろう。
「亘理はいちごの匂いがする」
谷川家もいちご農家で、家族総出で作っている。
二〇一一年三月十一日、晃は洗面所の鏡をにらみ、整髪料で懸命にヘアスタイルをきめていた。
四月から東京で大学生になる。今日はアパートの契約をしたり、新生活の雑務をしたりで東京に行く。日帰りだ。
「雑務」と言っても、実は何もない。
契約を済ませたら沢村純と東京を歩くのだ。二人は幼稚園からの幼馴染みで、同じ帝都文理大学に合格した。これから住む東京を、二人でバカ話をしながら歩くのは、考えただけで心が弾む。
今、東京と地方都市の差はほとんどない。だが、誰か一人にでも「田舎くせえ」と思われたくない。ヘアはきめねばならない。
ふと窓の外を見て思わず声が出た。
「いい天気だなァ」
空はよく晴れている。だが、寒暖計は二・一度。寒い。
隣人の山田トシが、マフラーを何枚も巻いて道を掃いているのが見える。登校する小学生たちに声をかけている。いつもの風景だ。
「おはよう! 車に気ぃつげさいよ」
トシは八十を過ぎているだろう。晃が生まれる前から毎日、道を掃いている。
「ついでだァ」と隣近所の前もだ。
小学生の頃は、晃もよく声をかけられた。
「アキちゃん、右見で左見で渡んだよ」
晃は洗面所の窓を少し開けた。春浅い風が吹き込んでくる。二・一度のどこが春なのだと、そう思うのは他所者だ。
北国の人間にはわかる。三月十一日ともなれば、光にも風にもすでに春の子供がいる。
「よしッ。こんなもンか」
全身をチェックしていると、弟の航(わたる)が入って来た。
「なァ、兄貴。やっぱり俺も東京、一緒に行く」
四月には亘理農化学高校の二年生になる。
「航、しつこいんだよ。今日は沢村と一緒に、やることいろいろあるって言ったろ」
「だから、俺、絶対に兄貴たちの邪魔しないって。一人で中古屋回って、KEYTALKのレアなCD探したいんだよ」
「だったら別の日に一人で行け」
「言ったろ。大学に入る兄貴のモロモロを、下働きしなきゃなんなくて……って言うと、学校休みやすいって」
「すぐ春休みだろうが。いつでも一人で行ける」
「どうしてもダメかよ」
「ダメ。最終の新幹線で帰るから、ホント、時間ないんだって。やること多くて、分刻みなんだよ」
航は後手に持っていた細長い箱を出した。
「入学祝い、買ってある」
「オッ! 気がきくなァ。サンキュー」
晃が笑顔で手を出すなり、細長い箱はサッと引っ込められた。
「やろうと思ったけど、やらねえ。俺が使う」
航は、
「連れてってくれたっていいのになァ」
と、恨みがましく言い残すと、細長い箱を手に洗面所を出て行った。
実は晃はよくわかっていた。何かを買ってやらねばならないのは、自分の方なのだ。東京の大学で好きに生きられるのも、航がいればこそである。
晃はいちご農家を継ぐ気は、まったくなかった。ハウス栽培とはいえ、自然相手の仕事だ。一家総出で、腰をかがめて育て続けても、いい結果が出るとは限らない。
ならば将来、自分は何をやりたいのか。晃に考えはない。ただ、東京で多くの経験をして、世界を相手にする何かがやりたい。今は具体的にはないが、必ず何か見つかるはずだ。そう思っていた。
父の広太郎は、長男の晃が家業を嫌い、認めていないことはわかっていた。それは家業の否定であり、気持ちのいいものではなかったが、自分の人生は自分が決める。そういう時代なのだと納得していた。
そんな中、次男の航が、
「俺、ジイチャンと親父の跡継ぐ。三代目になる」
と宣言したのである。まだ中学一年生だった。
広太郎は、
「無理すっこどね。晃も航も好きなごどやれ」
と幾度も言った。
息子二人の父親として、一人にだけ好きなことをさせる気はなかった。
航は勉強もスポーツも万能だった。中学の担任は、仙台で一番の進学校にも合格確実だと、家を訪ねて来たほどだ。しかし航は聞く耳を持たなかった。
「俺、亘理のいちごを世界ブランドにしたいんです。隣のクラスの山本や池田や、何人もがそう言ってます。すごくやり甲斐があります」
そう言って、地元の亘理農化学高校に入学した。山本や池田や、同じ中学から一〇人もが行った。
祖父の行雄も広太郎も、表立ってはそれを喜ばなかった。おそらく、フラフラしている長男の手前もあった。だが、内心ではどれほど嬉しかったことか。晃はできのいい弟に対し、そして将来を見据えている十五歳に対し、何がしかの劣等感を持つことはあった。
だが、そんな弟のおかげで、自由に生きられる。今となっては、その方がありがたかった。どう考えても大学入学を機に、何かお礼をするのは兄の方なのだ。
合格した帝都文理大は二流私大だが、東京で暮らすことは間違いなく大きな実りをもたらす。何の根拠もないが、晃は確信していた。東京でなら、多くの出会いもある。職種も多いし、人脈も広がる。
ヘアをきめた晃が居間に入って行くと、家族そろって朝食の最中だった。祖母の良子も、母のクミも家業の働き手だ。
「晃、航のこど、連れでってやれ。一人で動くって語(かだ)ってんだす」
漬け物に手を伸ばしながらクミが言うと、良子も同意した。
「んだよ。兄ちゃんが東京の人になる前めぇに、兄弟で旅したいんださ。わがってやれ」
航が放り出した細長い箱が、こたつの上にあった。本人は無言で食べている。
「みんなそう言うけどさァ、ホント、俺と沢村、やることいっぱいあるんだって」
行雄が音をたてて味噌汁を飲み、とりなした。
「ま、十六にもなる弟を一人連れてだったて、負担になるわけねぇけど、やるごどいっぺあって日帰りだべ」
「そうなんだよ。航、四月になったら兄ちゃんのとこに泊めてやるから、いくらでも来い」
航はうなずき、笑顔を見せた。
「うん、俺もさ、兄貴が沢村と二人で東京を回りたい気持ち、わかるからさ」
「お前、さすがだな。親父、こういう次男が跡継いでくれるのは、心強いよなァ」
広太郎は納豆をかきまぜ、答えなかった。
「航はこうやって人の気持ちもわかるしさ、いちご農家のリーダーになれるよ。ご先祖様にも顔が立つ。な、ジイチャン」
かつて、谷川家は代々続く米農家で稲作をやっていたが、天候に影響されて収入が安定しない。いちごは、稲作よりは収入が安定している。そう言われており、周囲は、ハウス栽培のいちご農家に転向し始めていた。
谷川家もついに、行雄の代で稲作をやめた。先祖からの稲田は、いちごのハウスに変わった。
やがて、行雄は長男の広太郎に仕事を任せ、自分は繁忙期だけ手伝うようになった。そして、道楽のような兼業を始めた。
タクシー運転手である。若い時から車の運転が好きで好きで、念願の仕事だった。
以来、知人が営む「常南タクシー」に所属し、楽しげに客を乗せている。
それまで黙々と納豆メシをかっこんでいた広太郎が、突然、箸を置いた。
「晃、東京で少しでもイヤな目に遭ったら、ケツまぐってすぐ帰(けえ)って来い」
みんなが同時に笑った。それはそうだ。
「まくるも何も、俺、日帰りだよ」
広太郎の目は笑っていなかった。
「今から心に留めておげ。東京は一人勝ちとか何とか、いい気になりやがってろくたなどごでねぇ。晃、わがってるな。今からケツまぐる稽古しとげ」
さらに笑う家族をよそに、広太郎はニコリともしなかった。
朝食を終え、晃はバックパックを背負って外に出た。
浅い春の光と風を、体いっぱいに吸い込む。
谷川家の屋敷は、古いが大きい。庭も広い。庭の隅にはまだ蕾つぼみも固い桜の木が、空に向かって枝を伸ばしていた。その根元に「小太郎」と書かれた犬小屋がある。
小太郎は元捨て犬の雑種だが、リコウな上に愛らしい。推定十歳か。
小太郎は良子に抱かれ、広太郎、クミ、航と一緒に見送りがてら庭に出ていた。
クミが桜の木を見上げ、
「今日は三月十一日がァ。あど一か月もすっと桜だねぇ」
と言うと、晃も見上げた。
「バアチャン、桜が咲くと必ず歌うのな」
良子は応えるように歌い出した。
「どうしておなかがへるのかな。けんかをするとへるのかな」
航がぼやいた。
「俺なんか、それが桜の歌だとずっと思ってたもんな」
晃が笑った。
「俺だって、そうだよ。桜が咲くと必ず歌うんだもんよ」
門の外でクラクションが鳴った。行雄がタクシーの運転席から降りて来た。
「そろそろ行ぐど」
行雄も桜の木を見上げた。
「すぐだな。どうしておなかがへるのかな」
家族のみんながこの歌に行き着く。
六人と一匹がそろって見上げる空は、早くも霞んでいるようだ。
いい朝だった。
この後、午後二時四六分に、関東大震災や阪神・淡路大震災を超える大地震と、一〇メートルもの巨大津波に襲われることは、誰も予想だにしなかった。
タクシーの助手席に乗り込むと、晃は窓を開けて叫んだ。
「カーチャーン、今晩カレーにしてッ。最終で帰るから、俺の分取っといて」
「オッケー。晃の好きなチョコレートだのインスタントコーヒーだの、隠し味つけて作(つぐ)っとくから、気をつけて行ぎなァ」
走り出して振り返ると、四人と一匹はまだ見送っていた。
「ジイチャン、見てみな。笑っちゃうよな。みんな、まだ手振ってるよ」
これが四人と一匹を見る最後になった。
晃を送り届けて帰宅した行雄も含め、谷川家は晃だけを残して全員が津波の犠牲になった。小太郎もだ。
タクシーの中で、晃は軽口を叩いた。
「な、ジイチャン、このオーバーな見送りが東京に引っ越す日ならわかるよ。今日は日帰りで、夜にはカレー食ってんのによ」
「今日は日帰りでもな、お前めぇが東京に行ぐ日がいよいよ近づいてきた気がすんだよ。そりゃ寂しいべ」
少し胸に響いたが、それを隠して力強く言った。
「いい加減、子離れしてもらわないとなァ。航っていう頼もしいヤツがいるんだし」
「そうは言っても、六人家族プラス小太郎で賑やかにやってきて、一人減るんだ、寂しいべ」
夏休みや年末はもちろんのこと、できるだけ帰ると言ってるのに寂しがる。だが、家族とはそういうものだろうと、晃も思った。
もっとも晃にしても、東京の新生活にはときめくが、家族のいない生活と思うと少ししんみりする。
「沢村の家、回っか?」
「いや、いい。あいつとは仙台の新幹線ホームで会うことになってんだ」
沢村は親戚の結婚式のため、昨夜から一家で仙台に泊まっていた。
「晃、花見には帰(けえ)って来いよ」
行雄が公園沿いの桜並木にハンドルを切った。
「うん。バアチャンの『どうしておなかがへるのかな』を聴きに帰るよ」
「たぶん、良子は初めて花見やった日、腹減ってたんだべな」
見慣れた亘理の風景が、今朝は特に輝いて見えた。たぶん、四月からの新生活に心躍っているからだろう。行雄の「超」がつく安全運転にも、腹が立たなかった。
東京に着くなり、晃と沢村はアパートの契約を済ませた。
大学の一、二年生は世田谷区経堂キャンパスに通う。二人は別々のアパートだが、同じ経堂駅だ。最低家賃の一間なのに、六万円もする。さすが東京だ。
契約が終わると、あとは何の用もない。二人は新宿を弾んで歩き、都庁の展望室にのぼった。
地上四五階、二〇二メートルの眼下に大東京が広がる。東京タワーもスカイツリーも見える。一面にタワービルが林立し、高速道路が縦横無尽に走っている。
それは亘理とは対照的な風景だった。気温も高いのだろう。空は本当に春霞がかかっているようだった。
「俺ら、東京に何回も来てるし、今さらどうってことないけど、ここの住人になるんだと思うと……」
沢村が景色を見たまま言った。
「うん、また違うよな」
「やっぱりすごいよ、東京」
その後、二人はおし黙って、どこまでも続くビル群を眺めていた。
突然、沢村が言った。
「昼メシ、学食で食おうよ」
「春休みだよ。開いてるか、大学」
「開いてるよ。中学じゃないんだからさ」
新宿から戻って来ると、言葉通り、大学の正門は開け放されていた。多数の男女学生が出入りしている。
二人は「帝都文理大學」と旧字で彫られた正門を見上げた。その奥に、クラシックで歴史を感じさせる時計台が見える。
「晃、何か伝統大学って感じするよな」
「うん。二流だけどな」
「言うなって」
社会というところ、人生というもの、先々にどんなことが起こるかわからない。
二流大を出た人間が、ハーバード大卒に勝つことだってありうるのだ。
人生は先々の予測がつかない。だから諦めてはならない。
まさかこの後、予測もしない大地震と大津波が家族を襲うとも思わず、晃は今後の人生が開ける予感がしていた。
そして、東京の私大に行かせてくれた両親を思った。中腰になり続けていちごを作り、その金で大学に行かせてくれる。
航の笑顔も浮かんだ。
――航、来月は兄ちゃんとこ、泊めてやるからな。
学生食堂は、地図によるとキャンパスの東側にある。さほど広くもないキャンパスだが、迷った。やはり大学は違う。
通り過ぎた女子学生に聞くと、細い指で一角を示した。この程度の顔は日本中にいる。だが、何だか垢抜けて見える。
学食はおしゃれなカフェのようだった。天井近くまでガラス張りで、明るい。中央部分は吹き抜けになっている。
サークルか何かで登校しているのか、相当数の男女学生がいた。外のウッドデッキに出て、飲んだり食べたりしている学生も少なくはない。
亘理ほどではないが、東京も風はまだ冷たい。それでも外に並んだテーブルを囲む学生たちの、マフラーの巻き方やスタジャンの着方がカッコよく思える。
――俺も帰省する時は垢抜けてやる。やっぱり東京の水で洗われると違うねえ……とか言わせたりな。想像するだけでいい気分だ。
トレイにラーメンを載せた晃と、カレーを載せた沢村は窓側のテーブルについた。
棚に設置されたテレビは、音声を絞ってあるが、午後のワイドショーを映していた。
画面の上部に「2:42」と、時刻が表示されている。
「沢村、このラーメンうまいわッ! 二五〇円でこの味はたいしたもんだ」
「お前、カレーが好きなのに、今日はラーメンかよ」
「うん。今日、カーチャンがカレー作っとくって。帰ったら食うから」
「それでか。なァ、この学食で朝メシも食えるんだってよ。貼り紙があった」
「俺も見た。洋定食、和定食。一人暮らしでも困んないな」
「な。大学ってすげえな」
その時だった。
学生たちの携帯電話から、緊急地震速報のアラームが鳴った。誰もがあわてて確かめている最中、突然、激しい揺れに襲われた。
学生たちが身構えると、揺れはさらに大きくなった。ショーケースやテーブルが音をたてて倒れ、天井の蛍光灯が次々に落下した。
「地震だッ」
「もぐれッ!」
あちこちで声がして、晃と沢村もテーブルの下にもぐり込んだ。テーブルの脚をつかんでいても、経験したことのない揺れに、姿勢が保てない。
見えないが、何かが次々に落ち、倒れているらしい。激しい音が学食に鳴り響き、あちこちで女子学生の悲鳴が起きた。
それが二分ほど続き、おさまった。
学食内は静まり返っている。
晃も沢村もテーブルの下から出られなかった。衝撃なのか、余震への恐怖なのか。たぶんその両方だろう。
やがて、学生たちがソロソロとテーブルの下から出てきた。晃と沢村も目を見かわし、出た。
その惨状に、どの学生も黙って突っ立っている。壁のあちこちがはがれ、大破した窓もあり、天井が落ちているところもある。テーブルの下にもぐらなかったら、晃も沢村も大量のガラスの破片をかぶっていただろう。
「地震か?」
「たぶん……」
二人はすぐに携帯電話を取り出した。だが、まったくつながらない。
ほとんどの学生も同じことをやっており、
「つながらない」
「震度いくつだ⁉」
などと騒いでいる。しかし、誰の携帯もスマートフォンもつながっていないようだ。
すると、学生の一人が大声で叫んだ。
「震源地、東北の太平洋側ッ。気象庁は岩手、宮城、福島に大津波警報を発表ッ」
彼が叫ぶ先に、テレビがあった。テレビは棚から落下するすんでのところでとどまり、斜めになっている。緊急ニュースを伝えるキャスターが、東北地方の地図を示した。
岩手、宮城、福島が大変なことになっている。晃も沢村も、ぼんやりとそう考えるだけで、頭も時間も止まっているようだった。
(ためし読み本文ここまで)
******
3 11を忘れない――。
感動のTVドラマを作者・内館牧子自らの筆で書き下ろした小説版が文庫で登場!
巻末にはドラマで主役を演じた俳優・千葉雄大氏 感動の解説を掲載!
潮文庫『小さな神たちの祭り』ご購入はコチラ。
作家
内館牧子(うちだて・まきこ)
1948 年秋田県生まれ。武蔵野美術大学造形学部卒業。三菱重工業に入社後、13 年半のOL生活を経て、88 年に脚本家デビュー。テレビドラマの脚本にNHK では大河ドラマ「毛利元就」連続テレビ小説「ひらり」「私の青空」、民放では「都合のいい女」「白虎隊」「塀の中の中学校」「小さな神たちの祭り」など多数。93 年「ひらり」で橋田賞大賞、2011 年「塀の中の中学校」でモンテカルロ・テレビ祭にて最優秀作品賞など三冠を獲得。21 年「小さな神たちの祭り」でアジアテレビジョンアワード最優秀作品賞受賞。
近著に『終わった人』『すぐ死ぬんだから』『老害の人』『迷惑な終活』『大相撲の不思議』(小社刊)『牧子、還暦過ぎてチューボーに入る』(小社刊)など多数。