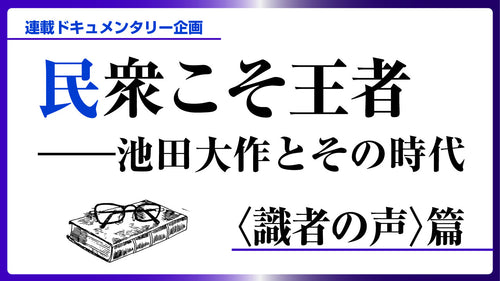てきてき 浪華のおなご医師と緒方洪庵 ためし読み
2025/04/24人気シリーズ「お江戸やすらぎ飯」の鷹井伶による最新刊!大坂が舞台の医療時代小説!!
発売を記念して冒頭部分を抜粋してご紹介します。
******
――適々【てきてき】
自らの心が適(たの)しみとするところを適しむべきである。(荘子の教えより)
幕末、緒方洪庵は大坂で医師を開業、同時に若者たちに蘭学を教えるための塾を開いた。
塾の名は洪庵の号から適々斎塾、略して適塾。
のちに、福澤諭吉をはじめ数多くの偉人を輩出し、大阪大学医学部の源流となった熱気あふれる学びの場であった。
序
「先生ぇ、おなご先生ぇ、亜弥先生ぇ」
亜弥の朝はいつもこんな声で叩き起こされる。
病に苦しむ人にとって、朝も夜もない。
一刻も早く、診てもらいたい。薬が欲しい。治して欲しい――その心に添うべく、常に心掛けているつもりだが、さすがに今朝は身体が重い。
というのも、三カ月前に発行された「なにわ名医鑑」(相撲の番付に見立てた医師番付)に、内科医として、亜弥の名前が出たおかげだ。
名前が出たといっても、末席も末席。小さく載っただけだが、女の医者はまだ少ない上に、それも産科ではなく蘭方の内科医という物珍しさもあってか、新しい患者が増え、夜遅くまで診ても追いつかない。
昨夜も夕食を満足に摂る暇もなく、急患に対応していた。
十年近く前の開業当初は閑古鳥が鳴いていたことを思えば、雲泥の差で、ありがたいことだし、人の役に立てる喜びもあるが、三十半ばになった身には、正直つらい。
「先生ぇ」
と、また声がして、表戸が強く叩かれた。
いつもなら、住み込みで助手を務めてくれている菊枝が出てくれるはずだが、動き出す気配がない。
「菊枝さん……、菊枝さん」
声をかけてみたが、返事のかわりに、ぐわぁっといびきが聞こえて来た。
可哀そうに、彼女も疲れが溜まっているのだ。
通いで飯炊きをお願いしているお粂さんも今日は昼からにして欲しいと言っていたことを思い出す。
「先生ぇ」
表はかなり焦った声を上げている。
「ふ、ふはぁい」
今度は菊枝の寝ぼけた声がした。あの調子ではまた寝てしまうだろう。
「はい、ただ今。少々お待ちを」
亜弥は苦笑を浮かべつつ、大声で返事をしたが、続いてあくびが出た。「あと半時、寝ていたかったのに」と呟いてすぐにいやいやと首を振る。
亜弥は眠気を吹き飛ばすために自ら両頰をパンパンと叩いてから、気合を入れようと、恩師緒方洪庵からの教えを唱えた。
「医の世に生活するは人のためのみ、おのれがためにあらず。ただおのれをすてて人を救わんことをねがうべし……」
洪庵は昨年、幕府奥医師に任じられ、今は江戸にいる。
江戸城では、将軍家茂の正室和の宮や先代将軍の正室天璋院に気に入られ、西洋医学所の頭取も兼務となり、相当な激務のはずだが、亜弥が番付に名前が載ったことを知らせる手紙を出すと、すぐに返事をくれた。
医師番付には、洪庵は三十一歳のときから何度も登場している。
手紙からは、祝いと同時に、多忙になるだろうからと、亜弥の身を案じる言葉が並び、うれしさが倍増した。最後は「必ず、道のため人のために力を尽くすように」と結ばれてあり、改めて、先生の教えに報いるためにも頑張らねばと気持ちを引き締めたものであった。
「はい、お待たせしました。どうされました? あれ、佐吉どん」
急いで身支度を整え、にこやかな笑顔で表戸を開けると、そこに立っていたのは、適塾で使用人をしている佐吉であった。
「へぇ、すんません。朝早うから。江戸から早飛脚が来まして。嬢(いと)さんが皆さんにもお知らせをとおっしゃるもんで回っておりますのや」
佐吉が嬢さんと言ったのは、洪庵の娘八千代のことだ。
適塾は洪庵が江戸に出る際、八千代と塾生だった拙斎が婚姻し跡を継いだ。本当なら若奥さま、ご寮人(りょん)さんと呼ぶべきだろうが、まだ婚姻して間がないのと慌てているせいだろう。
「江戸から急ぎの? もしや洪庵先生に何かあったの」
「へぇ、洪庵先生がどえらいことで……詳しいことはこれをお読みに。ほなごめんやして」
佐吉は、書付を亜弥に押し付けるように渡して、朝靄の中を走り去っていった。
「どえらいことって、どういうこと……」
訳がわからぬままに、亜弥は書付を慌てて広げた。
「六月十日、父洪庵が亡くなったとのこと」の文字が目に飛び込んでくる。
八千代が慌てて書いたのだろうか。字が乱れている。血を吐いて倒れ、そのまま息を引き取ったとある。
「先生が……どうして……そんな……」
亜弥は書付を目にしても信じられず、しばらく茫然とその場に立ち尽くしていた。
佐吉が慌てているのも無理はない。知らせに回らないといけない所は数多い。
それにしても八千代はもっと混乱していることだろうに、よくぞ、すぐに知らせをと頭が回ったことに、亜弥は感心した。伝聞間違いがないように書面にしたのもさすがだ。
八千代はしっかり者と見込まれたので婿養子を取り、跡を任されたわけだが、それでもまだ確か十三か、十四歳になったばかりではなかったか。
すぐに適塾に駆けつけるべきであろうか。それとも江戸へ。
いや、十日といえばもう四日前のことになる。この暑い盛りのことだ。既に葬儀は終わっているだろう。
江戸へ今から駆け付けたとしても、ご遺体に会うことはかなわない。それに洪庵先生なら、患者を放り出して何をしているとお叱りを受けるかもしれない――。
亜弥は洪庵を偲びながら、江戸のある東の空を仰ぎ見た。
「そなたの適は何かな」
洪庵の穏やかな笑顔と声が蘇って来る。
初めて洪庵に会ったのは、天保十二(一八四一)年のこと。亜弥は今の八千代と同じ年頃、十三歳になったばかりの春だった。
あれから二十二年、洪庵の言葉に導かれて来た。
「先生……」
その眼差しの向こう、亜弥の道を照らすように、朝の清々しく眩しい光が降り注いでいた。
一 来る者は拒まず
「……そうおっしゃられましても」
緒方洪庵はどう返答しようかと曖昧に笑みを浮かべた。
「あら、そんな難しいことではないでしょ、三平さん」
定(さだ)の目は洪庵をまっすぐに捉えて離さない。
まいった。そういう風に見つめられると、言葉に詰まる。しかも、三平さんと呼ばれると、はいと頷くしかなくなるではないか。
早いもので洪庵が大坂に適塾を開いて三年、評判を呼んで大坂近辺はもちろん、全国各地から学びたいと多くの者がやってくるようになった。また、医師としての評価も高く、大坂での医師番付にも選ばれるほどの人気を得ていた。
洪庵はそれらの報告を兼ねて、恩師の家へ年始伺いに訪れたわけだが、こんな厄介なことを言い出されるとは思ってもいなかった。
「適塾は来る者は拒まずなんでしょ。多くの優秀な方がいらしているとか」
「いや、それはその、確かにそうなのですが……」
洪庵がなかなか承諾できずにいるのは、定の頼みというのが、若い娘を適塾に入塾させて欲しいというものだからだ。定には、その娘にいずれ自分のような医者になってもらい、息子の嫁として手助けをさせたいという目論見があるようだ。
さて、どうしたものか─。
三十二という、世間的には十分に立派な歳になった洪庵だが、苦手なものがいくつかある。その筆頭がこの定だ。
定は洪庵にとって、大恩ある師、中天游の妻である。三平と名乗っていた十七歳の頃から世話になった、いわば母親のような存在だ。しかも、定は日本初の蘭和辞典を完成させた海上随鴎(稲村三伯)の娘であり、彼女自身、蘭学にも医学にも通じ、長年医師として稼ぐことで、学究肌の夫、天游を支え続けた。
つまり、洪庵にとって、医師としても蘭学者としても大先輩にあたる。
六年前に夫の天游が亡くなったので、定は隠居の身だと自嘲気味に笑うが、はつらつとした姿はとても五十近いとは思えない。
天游先生が亡くなった当初はかなり気落ちされていたが、今は前よりも若返った気がする。
だいたい、定は目力が凄いのだ。
黒目がちの大きな目で見つめられ、「三平さん」と呼ばれると、十七、十八の頃にしでかしたあれやこれやが走馬灯のように蘇ってきて、どうにも尻がむずがゆい。
「三平さん、いえ、違った。洪庵先生を見込んでの頼みなのよ」
「……その先生はお止めを」
「あら、そうお。……じゃあ、洪庵さん、どう? 通わせてよいかしら」
よいはずがない。
だいたいが適塾にいるのは血気盛んな若い男ばかりなのだ。そんなところで若い娘が一緒に学ぶなど、できるはずがあろうか。
「……それこそ、私などより、定さまがお教えになれば」
「何を言うの。私などもう駄目です。蘭語のいろはぐらいは教えられても、学問知識、とくに医学は新しいものでなければ。今や大坂で、いえ日本広しといえども、適塾の右に出るところはありませんよ」
「そう言っていただくのは、誠に光栄ではありますが、男ばかりのむさくるしい塾でして、若いおなごにはちと……」
上目遣いで見ると、定はにっこりと微笑みながらこう告げた。
「……まさか、女に学問は不要だとおっしゃりたいわけじゃないわよね」
「ま、まさか」
定に向かって、「はい、そうです」などと答えられるわけがない。
「そうだわよね。本人はとても聡い子よ。遠縁の娘でね、この春、江戸から来たの。
ああ、江戸と言っても下総の生まれでね。ともかく挨拶させましょう。その方が早いわ。亜弥さん、亜弥さ~ん、来てちょうだい」
洪庵の困惑などお構いなしに、定は娘を呼びつけた。
「はい」
と少し甲高い声がして、すぐに若い娘が部屋に入って来た。いや、まだ娘と呼ぶには早い。蘭学を学ぶよりは、ままごとでもしている方が似合いの子供に見える。
「この子ですか……」
定はいずれ息子耕介の嫁にするつもりだと言ったのではなかったか。戸惑っている洪庵をよそに娘はきちんと作法通りに三つ指をつき、はきはきと挨拶した。
「洪庵先生、お目にかかれて光栄に存じます。守内亜弥と申します。よろしゅうお願い申し上げます」
くるくると愛らしい目をしている。聡明そうな澄んだ目でひたと洪庵を見てくる。
人見知りはしないたちのようだ。
「うむ……おいくつかな」
「歳は十三にございます」
見た目よりは年上だ。
「おお、さようか。……学問は好きなのか」
「はい」と、亜弥は元気よく返事をする。
「幼い時から本を読むのが好きでございます。四書五経は家で習いました」
四書(「大学」「論語」「孟子」「中庸」)五経(「易経」「書経」「詩経」「礼記」「春秋」)は、中国から伝わった儒教の基礎的書物である。徳川幕府は儒教を基にした朱子学を奨励していたため、寺子屋や藩校に通うようになった子供は、まず初めにこれらを教科書として学ぶ。
「ほぉ、父上は学者か」
「いえ、そうではありません。学者になりたかったそうですが、父は商いをしております。私は兄たちが諳んじているのを幼い頃から見て育ったのです」
「この子の生家は下総の古河で薬種を商っているのですよ」
と、定が横から口を添えた。
「古河といえば、土井さまの」
「はい。父は蘭学好きで、読めもしないのに本を手に入れたりしておりました」
「ほうぉ」
洪庵は思わず顔がほころんだ。同じ本好きとしてわからぬことはない。それに古河の藩内では蘭学が盛んだという話はよく耳にしていたからだ。
下総の古河藩は江戸の北に位置している。藩主は土井利位(としつら)。
利位は大坂城代、京都所司代を歴任後、今は老中として幕政の中心にあるが、その一方、蘭癖(蘭学好き)としても有名で、雪の結晶を日本で初めて顕微鏡で観察し「雪華図説」を出版したことで知られていた。
「ですからね、この子は本草のこともよく知っているのですよ」
と、定は亜弥に目をやった。
「ひと通りは覚えてございます。父の手伝いをしておりましたので、陰陽五行など本道の基本も教えてもらいました」
本草とは薬草のことで、本道とは漢方内科のことである。
「ほぉ……では一つ訊いてもよいかな」
「はい、何なりと」と、すぐに言った割には、亜弥の顔に緊張が走った。何を訊かれるのか、不安なのだろう。
「高熱を出している者がいるとしよう。さて、熱を下げる役目を持つ薬草として一番に上げるなら、何であろう」
亜弥は一瞬、困った顔になった。
「わからぬかな」
「いえ、そうではなく……証を立てずに薬草を出してはならぬと父が……」
おっ、賢い娘だと洪庵は思った。
ひと言に熱と言っても、漢方ではその患者の症状をよく調べて検討しないと、薬草を決めることはない。これを「証を立てる」という言い方をする。
「どのような熱でございましょう。急に熱が出たということでしょうか」
急な病と持病から来る熱では、処方する薬草はおのずと変わって来る。このことも亜弥にはわかっているらしい。
「ああ、そうだ。昨日までは元気だったのに、ぶるぶる震えるほど悪寒が走り、急に熱が出てきた。節々が痛み、汗は出てないということにしようか」
「……はい。でしたら、麻黄(まおう)や桂枝(けいし)がよろしゅうございます」
「うむ。では逆に悪寒はなく、喉のどの痛みや腫れがある場合は」
「そのときは、連翹(れんぎょう)や薄荷(はっか)を用いるのが、よろしいかと……」
「ほぉ……」
洪庵が合っているとも合っていないとも答えないでいると、亜弥は少し自信なげな顔になって、定を仰ぎ見た。
定は大丈夫だというように頷いている。
「ねぇ、洪庵さん、よく知っておりますでしょ」
「え、ええ。そのようで……ああ、すまぬ、すまぬ。合っているよ」
洪庵がそう言うと、亜弥はうれしそうにはにかんだ。
「で、どうです? 入れていただけますか」
定が洪庵に催促をした。だが、洪庵はすぐには答えず、もう一度、亜弥に向き直った。
「そなたはどうだ? まこと適塾に入りたいのかな」
「は、はい」
「それはなぜかな。なぜ、適塾に入りたい? なぜ蘭学を学びたいのかな」
重ねて尋ねると、亜弥は再び少し困った顔になった。
「それは……」
と、呟いたが、なかなか話そうとしない。
「難しいかな。では、蘭方の医師になりたいという夢があるのか。それとも蘭学を身につけることで他にしたいことがあるのかな」
亜弥はまだ答えに迷っているのか、定にちらりと目をやった。
「蘭方の医師になりたいのでしょ。そう言うてよいのよ」
定がそう言うと、どこか曖昧に亜弥は頷く。
「責めているのではない。そなたの想いを知りたい。どのような夢でもよい。こんなことをしてみたいというのでもよい。今思っていることをそのまま言うてごらん」
洪庵は優しく亜弥を促した。すると、亜弥は小さく「はい」と頷いてから、洪庵をひたと見た。
「……何になれるか、何になりたいか、正直、まだよくわかりませぬ。ただ……蘭学を学びたいのは、知らぬ国のことを知りたいからです」
「うむ」
洪庵が頷くと、さらに亜弥は続けた。
「父は蘭学の本を抱えて、よくこう言っていました。『これが読めれば、もっといろんなことを知ることができるのに』と。そう言ってため息をつきました」
「では父上のためにか」
洪庵の尋ねに亜弥は首を振った。
「いいえ、違います。私は……」
言いかけて亜弥は少し考えをまとめるかのように一度息をついた。
「私はため息をつきたくはないのです。まだ見ぬこと、知らぬことが世の中にはいっぱいあるのに、知らぬままいたくはないのです。したかったのにできなかったとため息をつくのではなく、やってみたいのです。できるか、できぬかはわかりませぬが、できぬと決めてかかるのが嫌なのです」
一気にまくし立てるように言ってから、亜弥は急にはっとしたように口を押さえ、目を伏せた。言い過ぎたと思ったのだろうか。それから、そっと洪庵をうかがい見た。
「……それではいけませぬか」
その言い方があまりに愛らしく、洪庵は思わず笑みをこぼした。
「……いや、良い。構わぬ。そなたにとって、蘭学を学ぶことが、今やってみたいことなのだな」
「はい」
今度は、亜弥は洪庵の目を真っ直ぐに見て返事をした。
この少女がしっかりと自らの言葉で伝えようとしたことに、洪庵は満足していた。学びたいという意欲は感じられる。
「では、この子を通わせてもよいのですね」
定の念押しに洪庵は「はい」と頷いてみせた。
亜弥の顔がぱーっとほころぶ。
「ありがとう存じます」
「ただ、周りは男ばかりだ。気の荒い者もいる。大丈夫か」
「はい」
「勉強は難しいぞ。おなごだからといって、手加減はせぬ。みな夜も寝ずに勉学に励む者ばかりだ。ついて来るのは大変だぞ」
「わかっております」
「それと……」
「まだあるのですか」
と、定が尋ねた。
「ええ、一つ、守ってもらいたいことがあります。いや、守るというより、そなたが通うに際しての私からの頼みだな。よいか」
洪庵は亜弥の目を見た。
「……はい、何なりと」
「大したことではないが、これだけは聞いてもらいたい」
と、洪庵は少し微笑み、こう告げたのであった。
「すまぬが、男のなりで通って欲しい」
「……さてさて、どうしたものかしらね」
洪庵を玄関まで見送った定は、思案顔でそう呟いたが、すぐに「ま、なんとかなるでしょ」と振り返り、亜弥に微笑んだ。
洪庵から、「男のなりで」と言われた瞬間、亜弥は何を言われたのか一瞬わからなかった。
定も一瞬、意外なことを聞いたとでも言いたげな顔になったが、特に反論することもなく、「それでよいなら」と頷き、亜弥の適塾通いが決まったわけだ。
「亜弥さん、ちょっとこっちに来てちょうだい。……あ、お竹さん、手が空いていたらちょっとお願い」
と、定は女中の竹を呼び、亜弥と共に自分の部屋へと促した。
竹は昔から定が家事全般を任せていただけあって、裁縫も料理も掃除も得意だ。亜弥がここに来てからも、身の回りの世話をよくみてくれている。歳は定より若く、四十ぐらいか。夫とは若い頃死別し、ここに住み込んでいる。
定は竹に手伝わせながら、箪笥から着物を包んだたとう紙をいくつか取り出し、亜弥の前に置いた。そうして、中から次々と着物を広げ、亜弥の身体にあて始めた。
「こっちの方がいいかしら……いえ、こちらかしら」
どれも茶ちゃ鼠ねずや濃紺など渋い色の着物ばかりだ。
「あの……」
「あ、これがいいわね」
と、定は茄子紺のお召しを選び出した。
「ちょっと羽織って見て……う~ん、いいわ。顔移りがいい。そうね。丈は端折ればなんとかなるにしても、裄は少し直した方がいいわね。何日でできるかしら」
「これぐらいすぐに直せます。一枚でよろしいんで」
「そうね、洗い替えもあった方がいいかしら」
「あの、定さま」
「あ、これはね、夫のものなの。耕介が着ればいいと思って取っておいてよかった。これなら、いいでしょ?」
「そんな、勿体のう存じます」
「いいのよ。そうそう、袴も用意しなくてはね。お竹さん、押し入れの行李見てくれる」
「へぇ、帯はどないしはります?」
あれよあれよという間に、男物の着物一式が用意されていく。
髪を解かれ、後頭部の高い所で一つに束ねた総髪にすると、最後に脇差を腰帯に差し込み、定は「これでいい」と満足げに頷いた。
促されるまま姿見鏡の前に立つと、男姿に戸惑っている自分が映っていた。
「……ん? どうしたの。男のなりは嫌?」
定が亜弥の様子がおかしいことにやっと気づいてくれた。
嫌かと問われれば、嫌だ。
頷いたものの、亜弥は「いえ、それよりも……」と定を見た。
「なぜ、男のなりなら通ってよいと洪庵先生はおっしゃったのですか」
「それはね……思うに、ほんにつまらぬことなのよ」
「ほんにつまらぬ?」
「ええ。亜弥さんがいることがみなの勉強の妨げになってはならぬと、たぶん、そうお考えになったのだと思う」
「私が他の方の妨げ?」
「だから、つまらぬことなのよ。おなごがいるだけで浮つく輩が出るかもしれぬと。その程度で勉強が出来ぬのなら、そんな者は大した男ではないと思うけれど、ねぇ」
と、定は竹に向かって同意を求めた。
「へぇ、そうですわ。けど、若い男はんばっかりやったら、変なんも一人や二人おるかもしれませんやろ。亜弥さんはべっぴんやし」
と、竹は亜弥を見る。
「まぁ、塾の人がということではなくても、外に出かけたときに何かあっては困るから、この着物で守ってもらいましょう」
「へぇ、それがよろしゅうおます。だんさんのお着物やったら、ええ虫除けですわ」
竹は調子よく合わせる。
「あ、そうだ。勉強をするときは、書斎を使えばいいわ。あそこは一番明るくて過ごしやすいから」
「でも……」
書斎は定の亡き夫で、蘭学者として有名だった天游が使っていた部屋である。
「遠慮せずしっかりと勉強してちょうだい、ね」
定に促されるままに、亜弥は書斎に足を踏み入れた。
明かり取りの障子の前に文机と本棚が置かれていて、壁には異国のものと思われる地図が貼られてあった。その脇には本棚に入りきらない本が何十冊と積まれてあり、なんとも懐かしい心地がするのは、その古い本独特の匂いのせいだろう。
父の部屋にも本がたくさんあった。
亜弥の生家は、先ほど定が洪庵に話したように古河の城下で手広く薬種を商っている。殿さまから、守内という名字を戴き、帯刀も許され、城へ品物も卸している家だ。
その四代目の父は本人曰く、幼い頃にはよく熱を出し、家の者はこの子は成人できぬかもしれないと覚悟したこともあったという。長じてからは元気になったが、外に出るよりは家で本を読むのを好むようになった。
「身体さえ強かったら、江戸や長崎へ行きたかったんやがな」というのが父の口癖でその代わりと、珍しい本があるとすぐ買い求める。本だけではない。オランダもの、舶来ものと聞くとすぐ手を出そうとする。
今はしっかり者の母がついているから、商売は何とか回っているが、父の新しい物好き、珍しい物好きは年を重ねるごとに強くなっていて、母がよくこぼしていた。
兄弟は、六つ上の長兄、四つ上の次兄、三つ上の姉、亜弥、そして生まれたばかりの弟の五人である。
その亜弥の家に、遠縁の中家との縁談が持ち込まれたのは半年前のことになる。
相手は大坂の高名な蘭学者の息子で今は遊学中の秀才。その母も医師で学問一家という触れ込みで、最初は亜弥ではなく、姉の雅代はどうかという話だった。
「大坂にいる親戚が息子の嫁を探している。大変立派なお医者さまで、いくらでも勉学させるから勉学好きな人がよいという。大事にすると言っているし、どうだろうか」
仲人としてやってきた父のまたいとこはそう言って、雅代を望んだ。
亜弥の目から見ても姉は聡明で器量も良く、親戚中がみな口を揃えて適任だと言った。だが、彼女は頑として首を縦に振らなかった。
「江戸ならともかく、箱根を越えて大坂など、怖ろしくていけない」
普段、親の言うことに口答えなどしたことのない娘が泣いて嫌がるのを見て、両親は非常に驚き、困惑していた。
亜弥も正直びっくりしていた。だがすぐに「私に任せて」と両親に告げた。
実はこの時、亜弥は姉が羨ましくてしょうがなかったのだ。
幼い頃から本好きで、本で読んだ江戸や京大坂の町をこの目で見てみたいと願っていた亜弥にとって、この縁談は夢のような話であった。しかもいくらでも勉強させてくれるという。
両親は姉娘が大坂に嫁ぐのであれば、亜弥には古河の近場にいて欲しいと願っていた。つまり、もうこの近辺から出ていけないことになる。よその土地を全く知ることなく、一生を終えるなんて、亜弥には考えたくもない話であった。
「姉さまが行かぬのなら、大坂へは私が行く」
姉は仰天し、可愛い妹に身代わりなどさせられないと言ったが、亜弥は「私が行きたいの。お願い、どうしても、私に行かせて」と言い張った。
生まれ育った場所で一生暮らすなど堪えられない。喜んで行くという亜弥に両親はこれまた驚き、目を丸くした。
だがやがて、父は「亜弥の方が適任かもしれぬな」と呟いた。
兄弟たちの中では亜弥が一番本好きで学問に興味を示すのも早かった。それに気が強いのも一番だ。口喧嘩なら大の男相手でも負けていない。いくら女らしくしろと叱りつけたところで、言いたいことははっきりと口にする。そんな物おじしないところが、亜弥の短所であり長所でもあった。
母は母で、そんな亜弥で務まるのか不安そうだったが、「一度言い出したら、この子はきかない」と、諦め顔になった。
姉は最後まで申し訳ないと泣いていたが、亜弥の心は既に大坂へと飛んでいた。
そうして、年が明けてすぐ、亜弥は仲人に連れられて大坂にやって来たというわけだ。本当は父が一緒に来るはずだったが、直前に身体の調子を崩し、代わりに長兄がついて来てくれた。
ところが、亜弥と同じで一度は京大坂を見たかったと言っていた長兄だが、ほんの数日いただけで、郷里へ戻っていった。
どうやら、上方は彼の期待していたような場所ではなかったようだ。
長兄からは心配そうな顔で「いくら気の強いお前でも、こんなところに残していくのはしのびない。お前も嫌なら一緒に帰るか」とまで言われた。けれど、亜弥は首を横に振った。なぜそんなことを言うのか、不思議ですらあった。
中家の人たちは定をはじめ、使用人のお竹もとても親切で、亜弥のことを歓迎してくれている。意地悪をされているわけではないし、不自由など感じない。
ただ、確かに兄が言うように、町や人の風情は郷里の古河とはかなり異なっている。
郷里の古河は城が渡良瀬川の河畔にあり、南には雄大な利根川もあり、自然豊かな土地だ。大坂も水都と言われるだけあって、川も多く立派な橋もかかっていて、人馬の往来が激しいが、少々うるさいというか、賑やかだ。誰もがせかせかと急ぎ足で歩き、聞きなれぬ言葉をとても早口で話すので、落ち着かない。
たとえば、大坂見物にと、雑喉場という魚市場に行ったときのことだ。
大坂は天下の台所と言われるだけあって、問屋が何軒も軒を連ね、これまで見たこともないような大きな市場であった。
近隣はもちろん、遠く九州、四国、紀州からも荷が届くらしく、まだぴちぴち跳ねるような生魚から乾干魚(からぼしうお)、塩漬け等の海産物が大量に売り買いされ、もろ肌脱いだ男たちの大声が飛び交っていた。
「どいて、どいて、危ないで」
ゆっくり見物しようとしていたら、後ろから大八車を引いた車夫に怒鳴られた。
「どないせぇいうねん」
「せやからちょっとやなぁ」
「あかん、あかん」
「そこを何とか」
「これ以上、まけられん。買うんか、買わんのか」
「わかった、それで手打つわ」
こんなやりとりを初めて聞いたときには喧嘩しているのかと思ったが、どうやらそうではないらしい。その証拠に、当人同士は笑顔だ。
食べ物も郷里の味付けとは違う。
特に汁物や煮物の色は薄く、最初はこちらでは味つけをしないのかと驚いた。
しかし、食べてみると、これまで味わったことのない味が口の中に広がり驚嘆したと、同時に、それが昆布から出る旨味なのだと教えられた。
初めて人形浄瑠璃を観たときも感激した。太夫の語りに合わせて、まるで生きているかのように人形は動き、物語の世界が広がっていく。
いつしか亜弥は話に心奪われ、涙を流していた。
町を歩くと女たちの着物は華やかで、柔らかい色遣いが多いし、簪や小物も繊細で美しい。それに、武家が少ないせいだろうか。大通りを歩いていても、目立つのは商人や職人たちだ。
とにかく、亜弥にとって、見るもの聞くもの何もかもが珍しくて面白くてならないのだ。
それに蘭学が好き、医師になりたいと言えば、定はたいそう喜んでくれた。
だから、定が「そうだ。適塾に通えるようにしましょう」と言い出したときも、
「はい、お願いします」と、亜弥は即座に頷いた。
蘭学に興味があるのは事実だが、適塾というところがどういうところか、今ひとつよくはわかっていなかったし、正直、女の身で蘭方医になれるとは思っていなかった。
でも、噓をついたつもりはない。
そう言うことが、定を喜ばすことだと思えたからだ。
それに、医者を辞めてからも町の人から「先生、先生」と尊敬されている定を見ていると、あんなふうになれればいいなぁという漠然とした憧れのようなものが芽生え始めていた。
だが、どうしてだろう。
洪庵に面と向かい、「なぜ蘭学を学びたいのか」と問われた途端、亜弥は答えに詰まった。
瘦せすぎで秀でた額と高い鼻の洪庵は、見るからに学者然としていて頭がよさそうだ。それに、多くの病人を診てきたからだろうか、眼差しはとても穏やかで優しい。
この先生なら治してくれる――そう思わせる何かがあると亜弥は感じた。
亜弥にも経験があるのだが、医師には大きく二通りある。
厳しく叱りつけ、病になったのは自分が悪いと思わせる人と、目の前にいるだけで気が楽になり、病が治った気になる人だ。前者の方が多く、定は叱りつけることはないにせよ、前者に近い。だが、洪庵はまさしく後者であった。
洪庵の眼差しは深く、亜弥は身体、いや心の隅々まで診られている心地がする。
だからだろうか。余計に医師になりたいと軽々しく言ってはいけないようなそんな心持ちになったのだ。
「今思っていることをそのまま言うてごらん」
そう優しく促されると、洪庵に気に入られるための受け答えではなく、今、心にあることを正直に言うことこそが肝要で、洪庵もまたそれを望んでいるような、そんな気がした。
そうして思っていることを口にしているうちに、自分でも驚くほどに止まらなくなってしまった。
――私はため息をつきたくはないのです。まだ見ぬこと、知らぬことが世の中にはいっぱいあるのに、知らぬままいたくはないのです。したかったのにできなかったとため息をつくのではなく、やってみたいのです。できるか、できぬかはわかりませぬが、できぬと決めてかかるのが嫌なのです――
そうだ、自分はため息をつくのが嫌なのだ。
できぬと決めてかかるのが嫌なのだ。
はしたないと叱られるかと思ったが、幸い、洪庵はあきれることもなく、それでよいと頷いてくれた。
この先生の元で学びたい――。
そんな風に思える人と出会えたことが、亜弥はとてもうれしかったのである。
(ためし読みここまで)
******
「私、みなを救うお医者になりたい。」
人気シリーズ「お江戸やすらぎ飯」の著者による最新刊!大坂が舞台の医療時代小説!!
江戸から単身、大坂へーー男たちの中で、ただひとり適塾の門を叩いた少女の物語。
潮文庫『てきてき』ご購入はコチラ
作家
鷹井 伶(たかい・れい)
兵庫県出身。2013年より小説を上梓。主な著書に「家康さまの薬師」シリーズ(潮文庫)、「お江戸やすらぎ飯」シリーズ、「わたしのお殿さま」シリーズ、『おとめ長屋 女やもめに花が咲く』(以上、角川文庫)、『天下小僧壱之助 五宝争奪』(ハヤカワ時代ミステリ文庫)など。本作は、漢方養生指導士・薬物学マスターの資格を活かして執筆したものである。趣味は料理、演劇鑑賞、フラメンコ。