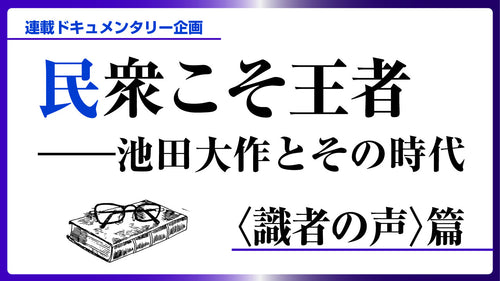池田SGI会長との忘れ得ぬ出会い(人物写真家・齋藤康一さん)
2024/01/25日本を代表する人物写真家の齋藤康一さん。
長く池田大作SGI(創価学会インタナショナル)会長をカメラに収めてきたことでも知られています。
亡き池田会長との親交の思い出や、今のお気持ちを語っていただきました。
(パンプキン2024年1月号より転載。取材・文=鳥飼新市、撮影=富本真之)
************************

中国で高まっていた創価学会への関心
失礼な言い方になるかもしれませんが、池田先生が亡くなられてやっぱり寂しい。僕は、僕なりの勝手な寂しさを感じております。
先生との出会いは1966年の暮れでした。もう60年近く前です。ある月刊誌の企画で先生の写真を撮ることになったのです。以来、不思議なご縁で、先生を撮り続け、先生関連の写真集を3冊、上梓することができました。初めてお会いしたときから、先生は僕のことを「齋藤さん」と名前で呼び、親しげに語りかけてくださいました。撮影の要望にも、いつも気さくに応えてくださるのです。
だれに対しても真心で接し、態度を変えない。僕は学会員ではありませんが、「齋藤さんはそのままでいいんだよ」と声をかけていただいたことがあります。そんな姿に接するにつれ、“ああ、池田先生は気づかいの名人なんだな”と、いつしか僕も敬愛を込めて「先生」と呼ぶようになったのです。
その前年の65年秋、僕は文化交流団の一員として国交樹立前の中国を訪れました。滞在中に何度も「創価学会とはどんな団体なんですか」と聞かれ、不勉強な僕は答えに困りました。中国はすでに創価学会に注目していたのです。そんな話を先生にすると、先生は机の引き出しを指先で叩き、「まだ推敲中ですが、中国について発表する原稿が入っているんです」と言われました。それが68年の学生部総会(9月8日)での「日中国交正常化提言」だったのです。
総会当日、僕は中央通路の真ん中に座ってカメラを構えていたのですが、先生は少しも力むことなく普段通りの態度でこの先見的な提言を発表されました。
先生の気づかいで撮れたご夫妻のツーショット
そのころの写真で印象に残っているものに、雪の日、先生の自宅の玄関で撮ったご夫妻の写真があります。玄関を出た先生に、香峯子夫人が笑顔でそっと傘を差し掛けている写真です。お二人の姿が微笑ましく、思わずシャッターを切りました。しかしよく考えると、これも偶然ではなく、外で待っている僕を先生が気づかって作ってくださったシャッターチャンスなのでは、と思えてくるのです。
先生の平和旅に同行させていただき、世界各地に行きました。なかでも忘れられないのは、72年5月、73年5月と2回にわたるロンドンでの先生とトインビー博士との対談に同行して、写真を撮らせていただいたことです。
撮影に許された時間は、毎回、対談の最初の5分間だけでした。与えられた時間に撮影を済ませると、外に出て待機するのです。カメラマンとしては、どうにも消化不良になります。もっと博士の日常をカメラに収めたいという思いが募るのです。
休憩時間に外に散策に出られたトインビー博士の後をついていき緑豊かな公園を歩く姿や、レストランに向かう先生と博士のツーショットを撮ったりしました。しかし、僕にはどうしても撮りたいシーンがあったのです。書斎で仕事をなさる博士の姿です。博士は、仕事中はご家族も書斎に入らせないと聞いていました。それでも研究に人生をかけてこられた碩学の写真に書斎でのショットがないなど考えられません。
僕は一芝居打つことにしました。正確な日付は忘れましたが、わざと愛用のカメラを博士の家に置いてきたのです。その日の対談が終わったあと、その“忘れ物のカメラ”を取りに博士のお宅に戻りました。
そして「書斎で撮らせていただけませんか」とお願いしたのです。博士は微笑んで了承してくださいました。書斎は6畳ほどだったと思います。暖炉の前に立っていただいたり、机に向かっていただいたり、僕の願いに快く応じてくださったのです。
先生の写真の魅力は自然な作為のなさ
73年。2回目の対談が終わったときは、ロンドンからフランスに向かいました。パリ郊外のロワールの宿舎で、夜中まで先生と歓談したことがありました。夜、2階の広々とした踊り場のテーブルに腰掛けて、自然に先生と写真の話を始めたのです。
話すうちに、先生と同じ地域で生まれ育ったことがわかりました。先生が大田区蒲田の糀谷で、僕は品川区の大井町。蒲田と大井町は2駅しか離れていないのです。
先生は、宿舎の便せんに、真ん中にある大森駅周辺の詳しい地図を書き始めました。ここが六郷川で、ここに友だちがいて、ここには親戚がいたな……と話が止まらなくなりました。夫人が来られて「まだ、お話しされていたんですか。そろそろ時間ですよ」と言われるまで、時が経つのを忘れて話し込んでしまったのです。時計を見ると、もう夜中の12時ちかい。いっぺんに我に返りました。本当に楽しい時間でした。
夫人は、場の雰囲気を壊さず、とても上手に僕たちを現実に引き戻してくださったのです。この夫人ありて、先生ありだな――。そんなことを思ったものでした。
先生が亡くなる数日前に、潮出版社から先生の『忘れ得ぬ旅 太陽の心で』の最新刊(7巻)を贈っていただいていました。
手にとると、先生のエッセーを写真が飾っている美しい本です。
先生はファインダーを覗かずに、じつに自然にシャッターを切ります。僕たちプロはどうしてもファインダーを覗いて画角を決めないとシャッターを切れないのです。
先生の写真の魅力は、その自然な作為のなさだと僕は思っています。上手く撮ろうなんて思わず、感じたままの美しさを撮ろうとされている。そこに先生にしか出せない作品の味わいが出るのです。
こうした写真やエッセーを通してでしか、もう先生に会えないのかと思うと、なおさら寂しさが募ります。
****************
齋藤康一(さいとう・こういち)
1935年東京都生まれ。 1959年日本大学芸術学部写真学科卒業。在学中より林忠彦氏、秋山庄太郎氏の助手を務め、その後フリーランスに。雑誌などに数多くの人物写真や、ルポルタージュを発表。 1965年第1回日中青年大交流に参加、以後、約80回中国各地を訪問・取材する。日本写真家協会名誉会員。日本写真協会監事。作品集に『蘇州にて』『1965中国にて』『昭和の肖像』など多数。