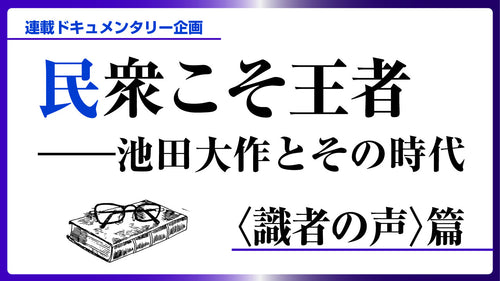新連載小説「ナースツリー」第2話
2024/08/20滝山大学に通う高階優美(たかしな ゆうみ)は看護学部の4年生。希望に胸を膨らませて入学したものの、看護をめぐる現実に不安や葛藤を募らせていた。ある日、大学近くの美術館の前で倒れた老爺を介抱した優美は、彼のパナマ帽を手渡したひとりの男子学生に、なぜか心惹かれるのだった。
第1話全文はこちら▶新連載小説「ナースツリー」第1話
優美(ゆうみ)が十四歳だった夏のことを思い出す。
八つ年下の琴美が潰瘍性大腸炎を発症した。
症状は下痢からはじまった。
暑さの厳しい時期でもあり、最初は食あたりかと家族のだれもが思ったが、それはなかなか治まらず、便に血が混じるにいたって総合病院に駆け込んだのだった。
ただ、保育士としての経験が長い母の武子(たけこ)は、似た症状の病気を抱える子どもを受けもった経験があり、病院で診てもらう以前にはもう、琴美の病気について薄々わかっていたらしい。
琴美が入院すると、平凡な四人家族の生活は大きく変わった。武子は入院することになった琴美につき添うため、保育士の仕事をあっさりと手放した。
父の孝介(こうすけ)は、米子に工場をもつ大手製紙会社の勤務だったから、武子が専業主婦になっても、一家の生活にさほどの影響はなかった。
ただ、生きがいとも、はたから見ても天職ともいうべき仕事を武子から取り上げるのは、忍びなかったに違いない。
中肉中背よりはやや小太りといった体形の武子は、その筋肉のなかに、子どもたちを全力で受けとめるだけのエネルギーを溜め込んでいるように見えた。
そして頬のふっくらとした丸顔は、いつも愉快なことを思い浮かべているような明るい印象を与えた。
保育園での出来事や、子どもたちの様子について嬉々として話す武子の姿は、一家の活力の源でもあった。
「せっかく好きな仕事ができていたのに、辞めるなんてもったいないよ。仕事をただ生活のため、いやいやじゃなくてできるなんて、とっても恵まれたことだと思う」
優美の言葉に、武子は珍しく真剣な表情で答えた。
「たくさんの子どものために尽くすことと、ひとりの子どものために尽くすことのなにが違うん?」
そしていつもの柔和な笑顔になって、
「それに、もう齢だがあ。前と違って疲れやすくなっとるだけん、ちょっとゆっくりしとうなった」
武子のなかでは、運命のようなものにあらがう気持ちはなく、むしろ進んで受け入れる覚悟が固まっていたようだった。
アイスティーを飲み終わり、優美は立ち上がった。そのとき、入り口の自動扉が開いて、砂川杏菜(すながわ あんな)が入ってきた。
お互いに片手を上げて合図をしながらも、やっぱり目を引くな、と思う。ハーフに間違えられることもあるという杏菜は九州の出身で、一年生のときに同じ寮で暮らし、学部もまた同じだった。
肌が光を受けたように輝いているうえに、目、鼻、唇、ひとつひとつが愛らしく整っている。とり澄ましたような美人ではないところもまた、人を惹きつけるのだった。
そして三年生のときにはダンス部の部長も務めており、とにかく目立つ存在だった。

「久しぶりだね。ときどきは大学にきてるの?」
優美が問いかけると、杏菜はごく自然に、これ以上ないというほど形の良い笑顔を見せた。
「今日はダンス部へ顔を出しに行ったの。それに、まだ最後の実習が残っているから、ちゃんとやらなくちゃね。単位を取らないと卒業できないもんね」
優美はできるだけぎこちなく見えないように気をつけながら、明るい表情を作って言った。
「就職おめでとう。聞いたよ。テレビ局だって?すごいね」
「あ、でも地方の、だけどね」
杏菜は謙遜して言ったが、一年生の実習が終わったときすでに、進路の変更を決めていた。
そして、看護師国家試験は受けないことを周囲に言ってはばからなかった。
看護学部に在籍しながらも、着々と新しい進路への準備を積みかさねてきた。にもかかわらず、学部での成績は優秀で、器用な杏菜は看護技術の習得も人一倍早かった。
そのことに対して、だれしもが複雑な感情を抱いている。杏菜はオールラウンダーだな、と仰ぎ見るような思いを抱く半面、不器用に実直に看護の道を志す自分たちを馬鹿にされているような気がするときもある。
さらには、もっと落ち込んでいるときや自信のなさに心が揺らいでいるときには、杏菜のようにきっぱり、ナースになるという選択を捨ててしまいたいと思うことだってある。
「いいなあ。国家試験を受けないんだから、卒業まで好きなことをして過ごせるじゃない」
「まあね。でも、みんなのこと、ほんとうに、心の底から応援してるんだよ」
杏菜が強い語調で言う。
「わかっているよ」
優美は笑顔を返し、じゃあ、と手を振ってドアへ向かった。
「琴美は安定しているから安心しないや。来年二月だがあ、国家試験は」
四階建ての学生ホールの壁に貼られたドライビングスクールのポスターが、木漏れ日を受けてまだらな影を作っている。
ホール前の広場でガーデンテーブルに座り、スマートフォンを耳に当てたまま、涼しげな日陰を作っている樹のいただきを見上げて言った。
「その前に、最後の実習もあるし、卒論も書かなきゃいけないし。まだまだいくつも山はあるんだよ」
そげかあ、と武子の明るい返事が耳元で響いた。
優美はふいに琴美が幼かったころのひとつのシーンを思い出した。
家の近くにあるドラッグストアの駐車場。開店前に自転車の練習をする男の子と、その介助をする孝介の姿があった。男の子は、近所のアパートに住む母子家庭の子どもだった。
「もうちょんぼし頑張らいや。先を走るポケモンを追いかけるつもりでペダルを踏むだで。それ、思い切って。ポケモンを逃がすな」
「わかった。やってみる」
男の子が笑顔で立ち上がる。
二人の姿を見ていた琴美がやきもちを焼き、ねえ、琴美も自転車の練習したい、したい、と駄々をこねた。琴美のねっとりとした掌の柔かさと、ゆがんだ顔で優美を見上げる泣き出しそうな顔。
あのときに、病気の萌芽はあったのだろうか。
優美が子どものころ、孝介はよく近所の子どもたちと遊んであげていた。孝介はノリがよくひょうきんで、ゲーム機片手に公園の隅で座り込んでいる少年などを見かけると、気軽にキャッチボールをしようと声をかける。
両親を早くに亡くし、親戚のもとで育った孝介は、新聞奨学生をしながら苦労して大学を卒業した。
「そういえば」
電話の向こうで、武子が心配そうに声をひそめる。
「綾ちゃんとは会っとるん?
綾ちゃんのお母さんが、近ごろ電話をかけてもなかなか出てくれんって言っとんなってなあ」

綾乃(あやの)は実家も近所で、中学生のときには同じバドミントン部の一年後輩でもあった。
そして優美のあとを追うように、大学都市と言われる同じ市内の別の大学に進学した。
上京した当時はお互いのアパートを行き来して頻繁に会っていたが、綾乃が大学生活に慣れるにしたがって、それぞれの生活や新しくできた友人を優先するようになった。
顔を合わせなくなってずいぶんとたったころ、偶然、駅前で会った。けれど、そのときの服装は以前とはまったく違っていて、ひどく驚いた。
大きく胸元の開いた黒いブラウスに、丈の短いショッキングピンクのスカート。そして、頭のてっぺんから垂らしたボリュームのある巻き髪のポニーテール。
小柄な綾乃が自分自身を大きく見せようと、年齢や内面以上に大人びて見せようと無理をしているみたいに見えた。
真面目に勉強していないのかな。つき合っている男の人がいるのかな。もしかして、キャバクラでアルバイトでもしているのかな。
頭に浮かんだすべてを綾乃にぶつけてみたけれど、地元にいたときとは違って、ツンととり澄ましてはぐらかすばかりで、まともな会話ができなかった。
優美の知っている綾乃は、好奇心旺盛で、新しいことには真っ先に飛びつく行動力があり、思っていることは言葉や態度で表現せずにはいられない、危なっかしくもあり人を惹きつける魅力のある少女だった。
そして家族や友人に対しては、思いやりのある子だと思っていた。
面と向かって邪険にされて、優美は綾乃の変わりように、驚きや怒りよりも、憂慮する気持ちが膨らんだのだ。
「なんだか綾乃は大学で自分の世界ができちゃってるみたいで、わたしも疎遠になってるんだ。でも、またアパートを訪ねてみるね」
「よろしく頼んだがあ」
電話を切った。
前期の試験が終わった。
教室の外へと出ていく学生の流れに反して、優美は窓辺へ身を寄せる。
窓の外には、乳白色の雲が浮かぶ広い空があった。じっと見ていると、雲はなんだかヒトの臓器に見えてきた。
小腸の、空腸と回腸が折りかさなって、もこもこしたあの感じ、そうだ、と思いひとり微笑む。
看護学部棟のこの大教室と同じフロアにある、専門図書館。千帆(ちほ)と二人、小声で会話しながら、消化器系の本を抜き出してはパラパラとページをめくり、必要な個所をコピーしていった。
複写申込書を書き終えた千帆は顔を上げ、試験が終わったら最後の実習が待っているねと、緊張の面持ちで言った。
普段はあまり物事を深刻にとらえない千帆のひとことが、過去と未来の重みを如実に物語っていて、そのとき優美は胸を衝かれたのだった。
卒業は否応なくやってくるんだなあ、と声に出してつぶやいてみる。

いつのまにか楕円形のグラウンドの周囲を、コンプレッションウエアを着た学生が二人、並んで駆けている。ここ数年活躍の著しい駅伝部の選手が自主練習を行っているのだった。
そぎ落とされた身体。動きに無駄のない走りのフォームは、サバンナで生きる野生動物を思わせた。
優美たちが、開学して半世紀がたつ大学の、新設された看護学部の一期生として入学してきた年。駅伝部は創部から二十年以上たって、ようやく初の予選会を勝ち上がった。
そして年が明けた一月二日、選手たちは箱根路を駆け抜けた。後方を淡々と、襷をつなげなかった悔しさを噛みしめながら。冷たい向かい風のなか。
あれから三年、まだシード権は取れないものの予選会から勝ち上がり出場しつづけている。
五階建ての学生センターの陰に消えた選手たちが、もうグラウンドの正面に戻ってきた。
「優美、お昼ごはん食べよう。ロワール食堂に行かない?」
教室の入り口に千帆が立っていた。明るい茶色に染めた髪をゆるく巻いて、春の花のような雰囲気をまとっている。
「ごめん、門永(かどなが)先生と、メインタワーの十三階で食べる約束をしてるの」
「小児の門永先生?いいなあ。違うゼミの子たちも門永先生に個人的なことを相談してるもんね」
「人格者であり、あったかいお母さんのようでもあり。看護の姿勢に関してはどこまでも峻厳で一流であることを求め、それでいて学生の様子に細かく気づいて声をかけてくれる」
優美が頬を紅潮させて一気に言い終えると、千帆は深い満足の表情を浮かべる。そしてはたと気づいて言った。
「……あれ、門永先生って、今年度を最後に定年退職されるんじゃなかった?」
「そう、学部創設の準備から入られて、わたしたちを育てて、わたしたちと一緒に卒業されるの」
「門永先生も卒業生?」と言って笑う。
それじゃあ、と手を振り、千帆は教室を離れた。
グラウンドの向こう側のグローバルタワーから滝山門まで、モミジバフウの並木がつづき、あと数か月すれば美しいグラデーションの紅葉を見ることができる。
そしてグラウンドの手前側、看護学部棟の入り口には一本の白樺の樹があった。
優美は白樺の樹が、時に激しく、なにかを訴えかけているように思えることがあった。
そんなときは決まって、気持ちが揺れて逡巡しているのだ。
手術実習のあともそうだった。恐怖に心を奪われ、人間の体のすさまじさにたじろいだ。見たくないとも思った。もう、一切をかなぐり捨てて、辞めてしまいたいと――。
(つづく)
作家
絹谷朱美(きぬたに・あけみ)
鳥取県生まれ。創価大学卒業。2014年「四重奏」で第17回長塚節文学賞短編小説部門大賞受賞。18年「光路」で第4回林芙美子文学賞佳作受賞。大学図書館のスタッフとして勤務するかたわら、執筆活動に臨んでいる。