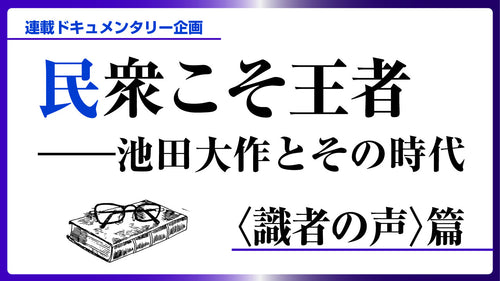連載小説「1+1」(ワン プラス ワン)
第3回 ラプサンスーチョンとダイジェスティブビスケット
2023/08/19
7月号からスタートした井上荒野さんの新連載小説「1+1」(ワン プラス ワン)。大好評につき、第3回目となる「ラプサンスーチョンとダイジェスティブビスケット」を潮プラスで特別公開します。
(イラストレーション=進藤恵子)
***********************

茜の家にはオーブンはなかった(ほかにもいろいろとないものがある)。だから父のキッチンを借りることにした。もちろん、父は快く貸してくれるだろう。問題は、茜がこれまで、料理には無縁だったこと、父もそれをよく知っているということだ。
「何作るんだ。っていうか、何事だ?」
電話の向こうの父は、早々に面白がっているようだった。
「ちょっと……ビスケットを作らなきゃならなくて」
「芝居に使うとか? ビスケット名人の婆さんの役でももらったのか?」
「役とかじゃないけど」
「ほほーん」
父がどんな顔をしているか見えるようだった。この種のことには察しがいい。そのうえで、しつこく詮索しないでくれる人であるのはありがたい。日曜日の午後に父の家に行くことにした。俺はそのときいたほうがいいのか、いないほうがいいのかと聞かれたので、できればいないほうがいいと正直に言ったら、じゃあ俺は朝から遥子さんとドライブでも行こうかな、と父はのたもうた。
というわけで、その日曜日の午後一時、茜はスーツケースを引っ張って父の部屋に到着した。スーツケースの中には買い揃えたもの――今夜のための装い一式と、ビスケット作りの材料と道具が入っていた。
道具は持ってくる必要がなかった。父のキッチンにはオーブンだけでなく、大小のボウルはもちろん、ヘラも泡立て器もクッキングシートも、ケーキクーラーもあった。目につくところに揃えて置いてあったのは、茜のためにわざわざ買ってくれたものもありそうだったけれど。茜はエプロンを装着し、準備に取りかかった。シンク横のオープン棚にふと目が留まり、あっと思った。中程の一段にいろんな瓶詰や缶詰がぎっしり並んでいるのだが、その中にラプサンスーチョンの缶があったからだ。
まさか、これまでお見通し? いやいや、いくら千里眼の父でも、そんなことはありえない。ほかのもの同様にお茶にも趣味がある人だから、当然のようにこのお茶も味わっているのだろう。それにしても、ここでこのお茶に再会するとは。吉兆だ、と茜は考えることにした。
ラプサンスーチョン。
その名前を知ったのは二週間ほど前だった。教えてくれたのは桃子さん。幸福な記憶。三十一年生きてきた中で最高に素敵な夜だった。
桃子さんは、茜が所属する劇団「楡(にれ)」の先輩だった。 二年前、茜がこの劇団の芝居に感動して入団して以来、憧れの人だった。 そもそも芝居に感動したのは、主演が桃子さんだったからなのだろう。
桃子さんは「楡」の看板女優で、 みんなから慕われていて、もちろん茜にもやさしくしてくれるけれど、茜は恋愛感情があるぶん、ほかの女性団員たちのように無邪気にまとわりつくことができなかった。 ある日、稽古場に行くと、更衣室には桃子さんひとりで、ジャージィのワンピースを脱ごうとしているところだった。
「悪いけどちょっと手伝ってくれる? ファスナーが噛んじゃって」
茜はドキドキしながら桃子さんの背後に回った。シャンプーなのかボディクリームの類なのか、甘い匂いを吸い込みながらファスナーと格闘し、どうにか生地を破かずに下げると桃子さんはくるりと振り返り、「ありがと!」と微笑んだ。
「素敵ですね、このワンピース」
茜は頬の熱さをごまかすためにそう言った――実際のところ、桃子さんはセンスが良くて、そのワンピースも素敵だったのだけれど。
「ほんと? 嬉しい。最近気に入ってるセレクトショップで買ったの。置いてあるもの全部素敵で、そんなに高くないのよ。今度一緒に行かない?」
それで、その夢のような一日が実現したのだった。 吉祥寺で待ち合わせてショッピング。互いの服を見立てたり、きゃあきゃあ言いながら試着したり。桃子さんが案内してくれたその小さな店は、たしかに素敵でリーズナブルな品揃えだったが、 それよりも茜にとっては、桃子さんとのはじめてのふたりきりの時間であるということが重要だった。
それから、戦利品を詰めた紙袋をガサガサさせながら――茜は、桃子さんが選んでくれたドット柄のブラウスと、小さな虎のチャームがついたブレスレットを買った――、やっぱり桃子さんおすすめのビストロに行った。劇団の拠点は西荻だから、吉祥寺は隣町で、打ち上げなんかもよくこの町でするのに、そんな洒落たお店があることすら知らなかった。古い店で、桃子さんがこの街の大学に通っていた頃からあるのだという。私にとってはとくべつな、大事な店なのよ。そういう店に自分を連れてきてくれたのだと、茜は有頂天になった。
桃子さんが選んだ料理と白、赤、 一本ずつのワインとで、夜が更けるまでお喋りした。それほど踏み込んだ話はしなかったけれど、茜より九歳年上の桃子さんが、未婚であることは聞き出した。茜ちゃんはいい人いないの? と聞かれて、好きな人はいます、と答えるのが茜の精一杯だった。わあ、まさか劇団の人? と桃子さんにさらに聞かれたときには、まったくふがいないことに、いやいや、と首を振ってしまった。
たらふく食べて飲んで、デザートはもう入らないけどお茶だけ飲もう、ということになり、桃子さんがラプサンスーチョンを選んだから、茜も倣ったのだった。運ばれてきたそれは、ちょっと漢方薬みたいな香りがする紅茶だった。セイロガンティーって呼んでるのよ、と桃子さんは笑った。中国産の紅茶で、松の葉の燻香がつけてあるらしい。
「好き嫌いが分かれる香りだと思うんだけど、私は大好きなの、茜ちゃんはどう?」
「おいしい」
茜は頷いた。桃子さんが大好きなものならなんだって大好きになれる自信があったが、それとはべつに、そのお茶はとても好きな味わいで、自分がそう感じたことが茜は嬉しかった。
「ダイジェスティブビスケットってあるでしょ? チョコレートがかかったやつ。あれと妙に合うのよね、これ」
「へえ、そうなんだ」
「でもあのビスケット、今手に入らないのよ。ライセンス切れとかで、販売停止になっちゃったの」
「へえ……」
そういうわけで、茜は今、そのビスケットを手作りしようとしているのだった。
数日前に、桃子さんから電話をもらった。日曜日にうちに夕食食べに来ない? という誘いだった。ショッピングの日のビストロで、ふたりとも食べることが好きだとわかって盛り上がっていた。でも料理はからきしなんです、と茜が打ち明けると、自分は結構得意だと桃子さんは言い、今度手料理ご馳走するね、という話になっていた。リップサービスかもしれないと思っていたのに、こんなに早く実現したのだ。
手土産に、ラプサンスーチョンとダイジェスティブビスケットを持って行くつもりだった。 紅茶は、桃子さんは常備しているかもしれないけれど、 万一切らしていたときのために。ビスケットはもう売っていないということだから、手作りで。きっとびっくりして、喜んでくれるだろう。
「ダイジェスティブビスケット 手作り」でググったら、一発でレシピにヒットした。十工程あり、やったことのない作業ばかりだけれど、やってやれないことはないだろう。茜は必死で泡立て器を動かした。
結論から言えば、苦戦した。とくに最後から二つ目の工程で、さらっと書かれていた「チョコレートは湯せんにする」にやられた。湯せんって、どうやるの。そこでまた検索。それでもどうにか完成した。爪楊枝で、ダイジェスティブビスケットっぽい格子柄もちゃんとつけた。ひとつかじってみたら、形はともかく、味はちゃんとおいしかった。本物よりおいしいかもしれない。
冷ましている間に後片付けをし、化粧をし、髪を整え、服を着替えた――もちろん先日のドット柄のブラウスと、ブレスレットを身につけた。そうして、チョコレートのコーティングがべたつかなくなったビスケットを、センス良くラッピングすると――もちろんこれもググった――、用意は万端だった。桃子さんに会いに行ける。桃子さんが私を待っていてくれる。
七階建てマンションの七階の右端。
高円寺駅で降り、暑さというより緊張で噴き出してくるような汗をハンカチで押さえながら環七通りを歩いていくと、間もなくその建物の、目指す窓が見えてきた。その窓に灯っている明かりが、ほかのどの窓よりも明るく見える。
築三十年越えのボロマンションよ、と桃子さんは言っていた。オートロックなどはなく、正面ドアを入って、煤(すす)けたドアのエレベーターに乗った。ゴトゴトという振動と胸の鼓動が重なった。七〇一号室の前に立ち、大きく深呼吸してから、インターフォンを押す。「はーい」という桃子さんのあかるい、やわらかな声がすぐに応じた。「開いてるから入ってきて。今、手が離せないの」
茜はドアを開けた。
みんながいた。劇団のみんなが。え? と思うまもなく、クラッカーの音と、拍手と歓声が炸裂した。
「誕生日おめでとう!」
桃子さんはうしろのほうにいた。ニコニコ笑いながら手を叩いている。何が起きているのか次第にわかってきた。サプライズだったのだ。茜の誕生日は一週間先だった。そういえば先日のビストロで、星座の話になって、誕生日を口にしていた。でもそのときは、桃子さんの誕生日(二月四日)と星座(水瓶座)を知ることができた嬉しさだけで心がいっぱいだったし、もちろん、桃子さんは私の誕生日を覚えてくれただろうか、とはちらりと考えたけれど、まだ一週間先だし、こんなふうになるなんて――。
「めちゃくちゃびっくりしてるなあ」
団員のひとりが言った。それで茜は、自分が呆然としすぎていることに気がついて、慌てて笑顔を作った。部屋の中に招き入れられると、ベランダに面したリビングに、本を積み上げて板を渡したテーブルが設えられて、料理を盛りつけた大皿が並んでいた。劇団員は全員ではなくて、桃子さんを入れて女性三人、男性は二人の計五人だった。そういえば、よく桃子さんと一緒に帰ったり、親しげにしていたりして、いいなあと茜が思っていたのがこの人たちだった。「お誕生日席」である、ひとつだけある座椅子に案内され、配られた缶ビールで乾杯した。
「何かと理由をつけて、飲んだり食べたりしてる人たちなの。だから茜ちゃんとも、気が合うんじゃないかと思って」
と桃子さんが言った。それが今日のサプライズの理由ということのようだった。「茜さんって、なんか孤高の人ってイメージがあって」「もっと喋ってみたかった」 「今日、一緒に飲めて嬉しい」などと、ほかのメンバーたちも続けた。どうやら二年前に入団して以来、茜が劇団にあまり馴染めずにいるのではないかと心配されていたらしい――茜にしてみれば、自分の性的指向を自覚した十代の頃から、必然的に身につけてきた人間関係における慎重さを発揮していたということだったのだが。更衣室で茜が「素敵ですね、このワンピース」と言ったのが、ひとつのきっかけになったのだろう。もしかするとあの発言は、このメンバーたちの中で悪意なく共有されているのかもしれない。
茜は、喜ぶべきなのか悲しむべきなのかわからなかった。いや、実際のところはわかっていた。喜ぶべきなのだと決めて、実際のところは、うまくやろう、と思っていた。この夜を乗り切ろう。スーツケースは父の家に置いて、ラフィアのトートバッグの中にビスケットと紅茶を入れて持ってきていた。手で持ってこなくてよかった。誰にも気づかれなくて幸いだ。 手作りのビスケットなんてこの場で出せるわけがない。ラプサンスーチョンだけあとで、 あ、そういえば、というふうに出して見せようか。
でも、結局それも取り出さなかった。食事が終盤になり――桃子さんの手料理はどれも本当においしかった――、まだアルコールを飲んでいる人もいたけれど、お茶を所望する人もいて、彼らのために桃子さんが運んできたのはもちろん、漢方薬の匂いが漂う紅茶ポットだった。そのうえ、ダイジェスティブビスケットが載った小皿もあった。
「それって……」
茜は思わず声を上げた。ああこれ、と桃子さんはニッコリ笑った。
「とっくに再販されてたらしいの。旬くんが持ってきてくれたのよ」
「桃子さん、ググれば一発ですよ。調べましょうよ、ちゃんと」
ダイジェスティブビスケットを持ってきた青年が笑い、みんなも笑い、もちろん茜も笑った。ザクザクした香ばしい生地とチョコレートの風味と、薬湯めいたお茶の香りの組み合わせは、たしかに素敵だった。甘くて、少し奇妙で、互いに差しのべた手が、ゆっくりと絡み合っていくような。
ググり方が甘いのは、私と桃子さんの共通点だ。茜は思った。まだ何も終わっていないし、はじまってもいない。そう考えた。

▶︎第一話はコチラ
▶︎第二話はコチラ
****************
作家
井上荒野(いのうえ・あれの)
東京都生まれ。1989年「わたしのヌレエフ」でフェミナ賞、2008年『切羽へ』で直木賞、11年『そこへ行くな』で中央公論文芸賞、18年『その話は今日はやめておきましょう』で織田作之助賞受賞。著書に『リストランテ アモーレ』『あなたならどうする』『あたしたち、海へ』『あちらにいる鬼』『荒野の胃袋』ほか多数。