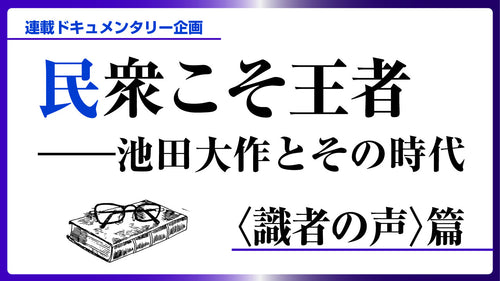【アスリート列伝】岡田彰布―― 堅実な采配に徹してきた指揮官が最後に打った大博打。
2023/12/12いま、注目を浴びるスポーツ選手やコーチたちに迫るアスリート列伝。
今回は阪神タイガースを38年ぶりの日本一に導いた岡田彰布監督に迫る。
(『潮』2024年1月号より転載。 文=横尾弘一/野球ジャーナリスト)
*****************
全員が輪の中心を向いた胴上げ
阪神が9月14日の巨人戦に勝って18年ぶりのセ・リーグ優勝を決めた際、岡田彰布(おかだ・あきのぶ)監督の胴上げは実に美しかった。野球の聖地・甲子園球場だからか……、いや、選手やコーチら全員が輪の中心を向いているからだ。
最近の胴上げは、中継のカメラやスタンドのファンにアピールしようと輪の外を向く選手が増えていたが、阪神では優勝が確実視された頃から、選手たちが胴上げの形について話し合っていたという。
それは、岡田監督の「チームの姿」にこだわる姿勢が、ペナントレースの戦いを通して選手たちにも浸透していた何よりの証であり、野球人・岡田の真髄と言っていい――。
岡田のキャリアは華々しい。大阪の強豪・北陽高(現・関西大北陽高)で入学直後からレギュラーとなり、夏の甲子園で準々決勝へ進出。3年時には四番でエースを担い、早稲田大へ進学すると三塁手として攻守に大きく成長する。2年秋から5季連続でベストナインに選出され、4年間の通算打率3割7分9厘、81打点は現在でも東京六大学の最高記録だ。
卒業時、1979年のドラフトでは当然のように目玉となり、阪神のほかに西武、ヤクルト、南海(現・福岡ソフトバンク)、阪急(現・オリックス)、近鉄も1位で指名。当時の在阪4球団が競合したのは大きな話題となる中、父親が有力な後援者で、岡田自身も入団を熱望していた阪神が交渉権を獲得する。
ここまではスター街道を突き進んでいたが、入団後も順風満帆とはならなかった。何しろ、サードには本塁打王を手にした掛布雅之(かけふ・まさゆき)がいるのだ。それだけではない。ショートに真弓明信(まゆみ・あきのぶ)、ファーストには藤田平(ふじた・たいら)と鉄壁の布陣に加え、セカンドにもヤクルトから移籍したデーブ・ヒルトンが起用されることになっていた。
しかも、前年から指揮するドン・ブレイザー監督は「メジャー・リーグでは、新人はじっくり鍛えるものだ」と岡田の起用に消極的で、オープン戦ではライトを守るなど不本意な時間を過ごす。
並みのルーキーなら、スタートに躓いただけで野球人生を大きく狂わせてしまうものだ。しかし、岡田は「メジャーがどうかは知らないが、ここは日本なのだから関係ない」と、ブレイザー監督の方針とは別にやるべきことに取り組む。
すると、開幕直後に掛布が左膝を故障。その穴を埋め、5月中旬に掛布が戦列に戻ると、不振のヒルトンに代わってセカンドを守るようになる。
結局、シーズン途中でブレイザー監督とヒルトンは解雇され、岡田は打率2割9分、18本塁打、54打点をマークして新人王に選出される。
そうして、実力でセカンドの定位置をつかんだ岡田は、85年にはランディ・バース、掛布と強力なクリーンアップ・トリオを形成し、21年ぶりのセ・リーグ優勝と球団初となる日本一に貢献する。
その後、88年限りで掛布が現役を引退すると、四番サードで打線の中心に。だが、ポジションは目まぐるしく変わるようになり、それが打撃にも影響したか、次第に成績を落として93年のシーズンを終えると自由契約となる。
阪神という球団には、トレードされた江夏豊(えなつ・ゆたか)や田淵幸一(たぶち・こういち)をはじめ、ある時代を支えたスター選手が寂しくチームを去っていく流れがあったが、岡田も例外ではなかった。それでも、岡田が野球と向き合う姿勢を見ていた仰木彬(おおぎ・あきら)監督に声をかけられ、翌94年はオリックスへ移籍する。
そうして、阪神・淡路大震災に見舞われたもののオリックスがパ・リーグを制した95年限りで現役を退くと、翌春の阪神対オリックスのオープン戦で催された引退試合では、両チームの選手たちの手で胴上げされる。さらに、オリックスの二軍助監督兼打撃コーチとして、38歳で指導者の道に入る。
指導者としてのファーム担当の意味
98年には二軍助監督兼打撃コーチで阪神に復帰したが、指導者としての岡田は7年間にわたってファームを担当する。プロ野球では、一軍は日本一を目指して結果を求める集団、ファームは結果だけに囚われず次代の戦力を育成する機関と位置づけられている。
だが、コーチが一軍からファームに配置転換されると「降格」と表現され、選手と同様に指導者も一軍で仕事をすべきという風潮もある。実際、ファームへの配置転換を拒んだり、二軍ではユニフォームを着ないという指導者もいる。
岡田のようなかつてのスターが指導者に転じた時も、「なぜ二軍コーチに」という論調はあった。だが、岡田本人はそうした外野の声を一切気にしていなかった。
この頃の阪神は、85年に日本一に導いた吉田義男(よしだ・よしお) 、ヤクルトで日本一に輝いた野村克也(のむら・かつや)が指揮するも、4年連続で最下位になるなど苦しい時代にあった。
その一方で、ファームでは井川慶(いがわ・けい)、藤川球児(ふじかわ・きゅうじ)、関本賢太郎(せきもと・けんたろう)らのちに主力となる若手が頭角を現しており、彼らをいかに一人前にするかがチーム再建のポイントになっていた。岡田はそんな重責を担い、脇目も振らずに汗をかいていたのだ。
また、岡田のファーム担当には、もう一つ大きな意味があった。プロ野球界では「名選手、名監督にあらず」と言われることがある。それは、名選手は自己成長力が高く、ファームを経験したことがないため、試行錯誤する若手に寄り添えないのが大きな理由とされた。
福岡ソフトバンクの王貞治(おう・さだはる)会長も、「巨人で監督になった頃は、努力が足りない選手がファームにいるものだと感じたこともあった」と語っている。
反対に、中日に黄金時代を築いた落合博満(おちあい・ひろみつ)監督は、指導者として成功した理由を問われ、「プロ入りから2年間はファーム暮らしだった。だから、できる人、できない人、両方の気持ちがわかるのは武器になったかもしれない」と振り返っている。
星野仙一の後任で阪神の監督に就任
こうして、育成のノウハウを確立した岡田は2003年、星野仙一(ほしの・せんいち)監督に求められて一軍内野守備・走塁コーチに就き、三塁ベースコーチも担当する。今度は、ベンチから出されたサインを打者と走者に伝達しながら、対戦相手のチーム力も分析する役割だ。
果たして、セ・リーグ最少の65失策という堅実な守備に、圧倒的最多の115盗塁をマークするなど、攻守にプラスアルファをもたらした岡田の貢献もあって、阪神は18年ぶりにペナントレースを制する。
日本シリーズでは敗れるも、感動のシーズンを終えると、勇退する星野の後任として岡田は監督に就任する。奇しくも巨人は堀内恒夫(ほりうち・つねお)、中日は落合と、老舗3球団の監督がすべて交代。岡田は、特に落合と極上の頭脳戦を繰り広げ、04年からは阪神と中日が熾烈な優勝争いを繰り広げる。
岡田と落合には、いくつか共通項があった。まず、優勝へ向けた青写真をしっかりと描き、そのための戦力を万全に整備する。若手には徹底した競争を求め、実績のあるベテランには不安なくプレーできる環境を整えた。
そして、試合の勝敗に関する責任はすべて監督にあると明言し、ミスを恐れずに動く空気を醸成。采配は、自身の戦略に基づいて選手を動かすというよりも、試合展開を見ながら柔軟に手を打つ。
04年に中日が優勝すると、翌05年も開幕直後は中日が走ったが、セ・パ交流戦で首位に立った阪神は、その勢いを止めることなく、追いすがる中日を振り切って2年ぶりの優勝を果たす。7回からジェフ・ウィリアムス、藤川、久保田智之(くぼた・ともゆき)による継投は三人の頭文字をとって「JFKリレー」と呼ばれ、安定感ある戦いを支えた。
ところが、日本シリーズでは千葉ロッテにまさかの4連敗。優勝の喜びが吹き飛ぶような負け方に逆襲を誓うも、どうしてもペナントを奪還することはできず、巨人に大逆転で優勝をさらわれた08年を終えると、岡田は責任を取ってユニフォームを脱ぐ。
オリックスの監督をシーズン中に解雇
それでも、指導者生活を始めたオリックスから声がかかり、10年から監督に就く。当時のオリックスはBクラスの常連にまで落ちぶれていたが、岡田は平野佳寿(ひらの・よしひさ)を先発からリリーフへ転向させ、22歳の岡田貴弘(おかだ・たかひろ)に着目。公募によって登録名をT-岡田とし、四番に抜擢して本塁打王を獲得させる。それは、仰木監督が鈴木一朗の登録名をイチローに変えて大成させた再現のようだった。
そうやって戦力を着々と整備したが、なかなか勝ち星に結びつかない。ある時、思い通りに動かない選手たちに意見を求めると、「監督が怖くて委縮してしまう」という答えが返ってきた。
さらに、3年目の12年もBクラスが確定すると、シーズン途中で解雇通告を受ける。結果がすべての世界とはいえ、選手や球団フロントから自分が信頼されていなかったことにショックを受けた岡田は、自身の野球観をアップデートさせながら、野球人生の集大成として手腕を振るうチャンスを待っていたという。
縦縞のユニフォームに再び袖を通す
「05年から、まさか優勝できないとは。外から見ていて、何とかしたいという気持ちがあった。勝てるチームが勝てないので、歯痒さはあった」
22年10月15日、そう語って再び縦縞のユニフォームに袖を通した岡田は、就任会見で「守りの野球」を実践すると明言した。その上で、大山悠輔(おおやま・ゆうすけ)と佐藤輝明(さとう・てるあき)には打線の軸になってほしいと語る。さらに、前年にショートで18失策の中野拓夢(なかの・たくむ)をセカンドにコンバートし、ショートは若手を競争させる。
また、2年間で勝ち星のない村上頌樹(むらかみ・しょうき)、現役ドラフトで獲得した大竹耕太郎(おおたけ・こうたろう)を先発で起用。守備位置や打順を固定された大山や佐藤は安定感を高め、ショートの定位置をつかんだ木浪聖也(きなみ・せいや)はチームの勢いとなる。
投手陣では、先発の柱と見込んだ西勇輝(にし・ゆうき)と青柳晃洋(あおやぎ・こうよう)が8勝に終わるも、村上、大竹、伊藤将司(いとう・まさし)が二桁勝利で穴を埋める。打てない時は投手が踏ん張り、投手が打ち込まれれば打線が取り返すという展開から相互信頼が生まれ、際どい勝負もものにする。
どんなチームでも、負けが込めば選手は自分の成績だけを考えるようになる。反対に、勝利を積み上げればチームの勝利を優先したプレーに徹していく。
その中で、岡田自身もオリックス時代に気づけなかった選手との距離感にも気を配り、「自分を見ていてくれる」という安心感を与え、意気に感じる起用で求心力を高めた。
激闘を制し38年ぶりの日本一に
ともにクライマックス・シリーズを圧勝したオリックスとの日本シリーズは第7戦までもつれ、しかも第6戦まで23得点23失点と、まさに五分の激闘だった。
そんな紙一重の勝負を制することができたのは、常に堅実な試合運びに徹してきた岡田が、最大のピンチで打った大博打だろう。
阪神の1勝2敗で迎えた第4戦は、5回までに3対1とリードしたものの7回に同点とされる。さらに、8回表には2死一、三塁のピンチに。ここで岡田は、調子を崩して6月から登板のなかった湯浅京己(ゆあさ・あつき)を投入。中川圭太(なかがわ・けいた)を1球で二飛に打ち取り、9回裏のサヨナラ勝ちにつなげる。
失点すればオリックスに王手をかけられる瀬戸際を、「もう投げさせられない」とファームに落とした湯浅に託す。セオリーよりも選手の闘争本能にかけた一手は、オリックスに傾いた流れを一気に引き戻したと言っていい。
*
――11月5日、オリックスとの死闘を制して38年ぶりの日本一を達成した時も、選手たちは輪の中心を向いて岡田監督を胴上げする。そこには「これが阪神タイガースの姿だ」という気概が感じられた。そして、祝勝会で挨拶に立った岡田監督はこう言った。
「今日は選手、コーチ、スタッフも含めてみんなが主役。成績は問いません。みんなの頑張りでここまで来られた。おめでとうございます。3月に開幕して、まさかこの日が来るとは思っていなかったので……」
最後のセリフを聞いた選手たちは、痛烈なブーイングを浴びせる。だが、誰もが飛び切りの笑顔だった。(文中敬称略)
*****************
岡田彰布(おかだ・あきのぶ)
1957年大阪府生まれ。北陽高、早稲田大学を経て阪神タイガースに入団。オリックスに移籍し現役引退。オリックスの二軍助監督兼打撃コーチを経て、阪神の監督に就任。その後、オリックスの監督を務め、2023年に再び阪神の監督に就任する。