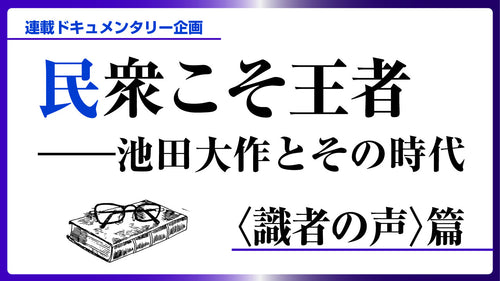迷いに迷って最後に選ぶのは「好き嫌い」ですね。(羽生善治×芦沢 央 特別対談)
2023/12/14「伝統と革新を愉しむ」と題した特別企画。
棋士で日本将棋連盟会長の羽生善治氏と、『神の悪手』で将棋ペンクラブ大賞文芸部門優秀賞を受賞した芦沢央氏がご登場。将棋をテーマにしながら、伝統と革新の融合の可能性を探る対談となりました。
(月刊『潮』2023年12月号より転載)
******************
将棋連盟会長に就任してわかったこと
芦沢 このたびは日本将棋連盟会長就任、おめでとうございます。
お会いするのは、藤井聡太王将と対局された王将戦の観戦記を書かせていただいて以来ですね。
羽生 そうでしたね。その節はお世話になりました。
芦沢 こちらこそ、(将棋を題材にした短編集)『神の悪手』を発表した際に「推薦の辞」をいただき、ありがとうございました。
会長に就任されてから数カ月経ちますが、いかがですか。
羽生 実は就任の翌日にここ (対談会場=駒テラス西参道)のこけら落としに参加したんです。ですから詳しく知らないままテープカットをして、挨拶をして……と。
芦沢 それは就任の最初から大仕事でしたね。私は今日、初めて来たんですが、落ち着いた雰囲気のとてもいい場所だと思いました。
羽生 棋士になってもう40年近くになりますから、将棋界のことは一通り知っているつもりでいました。ただ、会長として会議や決め事に携わる立場になると初めて知ることや見えてくるものがたくさんありますね。連盟役員などを経験しないまま、いきなりマネジメント側になったので周囲の方々には日々助けてもらっています。心配されていたのか、前会長の佐藤康光九段からは大量の引き継ぎ書類をいただきました。(笑)
それと、将棋の世界を応援してくださっている方――ファンという意味だけではなく、関係者として支えてくださっている方々がこんなにも多いのかと改めて実感しました。この駒テラス西参道も、渋谷区の行政や町内会の皆様に関わっていただいてできあがりました。そうした方々が、何千人という単位でいらっしゃる。「会長」の肩書を入れた名刺を大量に作ってもらったのですが、すごい速さで減っていきます。
奨励会を描きたいと思った理由
羽生 芦沢先生は棋歴のほうは?
芦沢 私は基本的には「観る将」(みるしょう/将棋を観て楽しむファン)です。祖父と兄が将棋好きで、子どものころから、二人が将棋を指す姿を横でじっと観ていました。
羽生 当時から「観る将」だったんですね。
芦沢 いつも冗談ばかり言っていた祖父が、兄と将棋を指すときだけはすごく真剣な顔になったんですね。兄と祖父は年齢が60くらい離れているのに、将棋のときだけはまったく対等な感じで向き合っていた。その姿を見て「将棋っていいな」と思ったことが、好きになったきっかけでした。
羽生 将棋の小説を描こうと思われた理由は何かあるんですか。
芦沢 私は高校生のときに小説家を志したのですが、デビューまでに12年もかかりました。毎年賞に応募しても落選つづきで、でも夢の諦め方がわからなくて、「このままでは夢に人生を食いつぶされそうだ」と恐怖を感じていた時期が長かったんです。
幸いデビューはできたんですが、今度は化け物みたいなすごい能力を持った同業者たちに囲まれるなかで、自分の凡庸さと向き合わざるを得なくなってきました。小説そのものに人生を食いつぶされていく感覚が強くなり、将棋の奨励会(新進棋士奨励会=日本将棋連盟の棋士養成機関)に興味を抱くようになりました。
羽生 そして生まれたのが『神の悪手』の表題作だった、と。
芦沢 ええ。ですから、将棋の楽しさより、むしろ棋士の世界の残酷さに関心を抱いたのがきっかけかもしれません。
羽生 たしかに、いまの奨励会には年齢制限があって厳しいように見えますね。でも、昔の奨励会には年齢制限がなくて、30歳になっても40歳になっても居つづける人がいました。その年齢から別の世界で生きていくのも大変なので、いまのルールになったと経緯がありました。
芦沢 年齢制限がなくて、ずっと夢を諦められないほうが、むしろ残酷な面もあるわけですね。
羽生 そうですね。実際、年齢制限ができてからのほうが、プロを諦める見切りは早くなっています。とはいえ、夢を諦める姿にはやはり感じ入るものがありますね。私は12歳で奨励会に入ったのですが、先輩方や同期が毎月のようにやめていきました。入会の際、プロの世界がいかに厳しいかを講話の形で教わるんですが、そうした言葉よりも、最後の挨拶をして去っていく姿を見るほうが、ずっと心に響きました。
ミステリー小説と詰将棋は似ている?
芦沢 奨励会を描きたいという思いから将棋の世界を描き始めたんですが、そのために将棋教室に通ったり取材したりするうちに、楽しさや奥深さも少しずつわかってきました。たとえば(将棋の駒を作る)駒師の方を取材させていただいたらお話がすごく面白くて、「これでもう一作書きたい」と思ったり。
羽生 『神の悪手』には対局前検分(タイトル戦などの前に、対局者が対局室を訪れ、空調・照明・駒・座布団などの環境を確認する)を舞台にした作品も収録されていますね。
芦沢 多くの人にとっては対局がクライマックスですが、駒師にとっては前日の対局前検分こそがクライマックスになるんですよね。
あと、私は将棋を指すほうはへっぽこですが、詰将棋を解くのが好きなんです。伏線があって、それが回収されると、作者が封じ込めていた世界を共有できる感じとか、私がずっと書いてきたミステリー小説に似ている気がします。原稿の合間に始めたら全然解けなくて、なかなか執筆に戻れなかったり……。
羽生 なんだか腹が立って意地になってしまいますよね。(笑)
芦沢 はい(笑)。『神の悪手』ではそうした将棋の世界をミステリーの形式で5編描いたのですが、それだけでは将棋の魅力を書き足りないと思って、いまミステリーではない将棋小説にも挑戦中です。
羽生 それはとても楽しみです。
棋士のトップを走りつづける源泉
芦沢 40年近くも棋士のトップランナーでありつづけるというのは大変なことですが、どうやってモチベーションを維持しておられるのですか。
羽生 同じレベルのモチベーションを維持するのは、難しいというか不可能ですね。ある程度の浮き沈みがあることは織り込んだうえで、調子が悪いときにも「そこそこの将棋」――満点ではなくても60点の将棋が指せるように習慣化していくことが必要なんだと思います。そのためには、勝ちにも負けにも耐性をつけることが大切になってきます。
芦沢 「耐性」というと?
羽生 負けたことも勝ったことも、心の中に引きずらないことと言いますか。対局に向かうメンタルの状態として、何も偏りがないフラットな状態であることがいちばん理想的なんです。負けや勝ちが残像として心に残っていると、次の対局にいい影響を及ぼさないですから。
その点、年齢を重ねると忘れっぽくなるせいか、勝ち負けに対する耐性はつきますね。フラットな心で対局に臨めるようになってきます。棋士という仕事が長くつづけられる一つの要因は、そこにある気がします。
第一線の棋士たちにメソッドなどない
芦沢 私はプロになって12年目なのですが、最近書きたい物語に自分の能力が追いつかないと感じることが増えてきました。書ききるためにはいろんな能力の水準を上げないといけない。新しい力を手に入れるためには、いままで積み重ねてきたものを一度壊さなければならない。膨大な「やるべきこと」の前で途方に暮れているところで……。
失礼なことをうかがってしまいますが、羽生先生はそういう気持ちになることはありませんか。
羽生 あります。たとえば将棋の初心者が「アマチュア5級になりたい」と思ったら、そのためのメソッド(方法)って山ほどあるんです。しかし、棋士として七段くらいになった、これからタイトルを目指そうという人から、「何をすればいいですか?」と聞かれても、私には答えられません。そのレベルになったら、もう誰にでも当てはまるメソッドなんてないからです。そこまで行ったら、その人自身が「これならいいかもしれない」と思う新しい挑戦の試みを、賭けてやってみるしかないんです。
芦沢 上手くいく保証なんてどこにもないなかで、それでも挑戦してみるしかないんですね。
羽生 そうですね。将棋は一日で客観的な結果が出ますから切り替えはしやすいと思います。新しい試みをやってみると、最初はだいたい負けます。でも、新しい試みにまったく挑戦しないとジリ貧になっていくことが経験知としてわかっているので、多くの棋士が挑戦を積み重ねています。
また、一つの技術が伸びると、別の力は逆に落ちる場合もあります。たとえば、早指しの練習を積み重ねていくと、瞬間的に正しい手を選ぶ力は伸びますが、時間をかけていい手を探していく力は逆に衰える。もともと持っている総合的な力を落とさずに、一つのスキルを伸ばしていくことはけっこう難しいのです。
AIの活用と、進化をつづける将棋
芦沢 近年はAI(人工知能)が棋士の世界にも大きな影響を及ぼしていますが、羽生先生はAIをどう活用されていますか。
羽生 まだ結論の出ていない難解な局面を深掘りして調べたりしています。あと、AIだけでなく、棋譜のデータベース化も進んでいて、他の棋士が最近どういう試みをしているかとか、ある棋形にどんな歴史的背景があるかとかを調べることもよく行っていますね。
芦沢 最先端の情報や流行を追っていないと、棋士の世界でも取り残されていく感じになってしまうんでしょうか。
羽生 実はそうでもなくて、「俺はAIも流行りも関係ない。わが道を行く」というスタンスの棋士も多いですよ。私自身は最先端のものも取り入れていくスタンスですけれど。
芦沢 若手棋士のほうが最先端の動きに敏感なのかなという印象がありますが、実際のところどうなんでしょう?
羽生 その傾向はあります。ただ、それは年齢的なものというより、棋士としてキャリアを重ねるほどしがらみや雑用が増えて、新しいことに目を向ける時間がないという理由が大きい気がします。
芦沢 たしかに、新しい動きについていこうとしたら、すごく時間がかかりますもんね。
羽生 もう一つは、長くやってきた人ほど、一つの形に対する思い入れが強いということがあります。「この形はもう時代遅れだ」となっても、「若いころから研鑽したのに、いまさら捨てられない」と考えてしまいやすい。
芦沢 そう言えば、「矢倉(将棋の代表的戦法の一つ)は終わった」とか「終わらない」とか……。
羽生 それは典型的な例で、私自身が10代のころから一生懸命勉強してきた古い矢倉の形は、いまはもう一ミリも役に立ちません。将棋にはそういう残酷さがあって、画期的な一手の登場によって、過去何十年分もの蓄積が全否定されてしまうこともあるんです。
棋士は着物を着て和室で対局するので、伝統的な世界だと思われがちですが、盤上でやっていることは基本的にテクノロジーの世界なので、新しいものをどんどん取り入れて、古いものは駆逐されていきます。その意味では、一般的な伝統文化のイメージとは大きく違うと思っています。
いま「正しい」と信じるものを貫く
芦沢 積み上げてきたものが否定されてしまう怖さは小説家として私も感じています。小説作品は発表からずっと後年まで残ります。その一方、社会的な正しさの基準は変わってしまうこともある。いまの正しさを基準に小説を書いても、10年後には糾弾されて、私自身も自分が許せなくなるかもしれない、と。そういった意味で、「間違うこと」を怖れる気持ちはありますか。
羽生 私のデビュー当時の棋譜をいま見直してみると、間違いだらけなんですよ。でも、当時はそのことに気づけませんでした。これは将棋AIですら起こることなんです。いま将棋AIは人間よりはるかに強くて正しいように見えますが、1年ぐらい後に出た最新AIと対戦させると7~8割くらい負けてしまう。つまり、最初AIが「正しい」といっていたことも1年後には「間違い」になる。ですから、私たちは、いま「これが正しい」と信じているものをつづけるしかないのかなと思います。
芦沢 過去の間違いを後悔することはないのですか。
羽生 いや、たくさんありますよ。後悔だらけです。でも、そのことも含めて「仕方ない」と思っています。人間って難しい選択をしたときには、どちらを選んでも後悔するようにできていると思うんです。
芦沢 たしかに、私も執筆中には何度も改稿するんですが、95パーセントくらいまでは直せば直すほど良くなっていく実感があっても、残りの5パーセントはどちらを選んでもそれぞれ生きるものと損なわれるものがあるので、毎回かなり悩みます。
羽生 私の場合、長考で迷いに迷って最後に選ぶ基準は「好き嫌い」ですね。(笑)
編集部 将棋が普及、継承されていくためにはどんなことが大事になってくるでしょうか。
羽生 社会に対して良い影響を与えられるような存在でありつづけることではないでしょうか。将棋のようなゲームが時代を経るにつれて社会から消えてしまったという例は少なからずあります。来年(※2024年)、将棋連盟が創立100年を迎えますが、だからといって安泰だという訳では決してありません。
ですから、伝統的な歴史とか文化という固有性を継承していくことも大事にしつつ、社会や人々の生活の変化にも柔軟に応えていくしかないのかなと思っています。
芦沢 私は将棋と出合って、人生が何倍も楽しくなりました! 棋戦が気になって原稿が進まないことも……(笑)。だから、これからの連盟の取り組みや棋界がますます楽しみです。
******************
棋士・日本将棋連盟会長
羽生善治(はぶ・よしはる)
1970年生まれ。小学1年生で将棋を始める。82年に奨励会入会。85年に四段、プロデビュー。89年、19歳3カ月で初タイトルの竜王位を獲得。96年、史上初の七冠を達成。2017年、史上初の永世七冠の資格を取得。18年、国民栄誉賞受賞。23年6月より現職。
作家
芦沢 央(あしざわ・よう)
1984年生まれ。2012年、『罪の余白』で野性時代フロンティア文学賞を受賞しデビュー。22年『神の悪手』が将棋ペンクラブ大賞文芸部門優秀賞受賞。23年『夜の道標』が日本推理作家協会賞長編部門受賞。他の著書に『汚れた手をそこで拭かない』『許されようとは思いません』等がある。