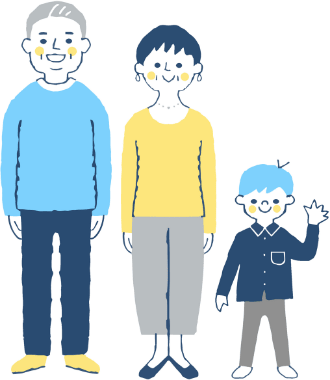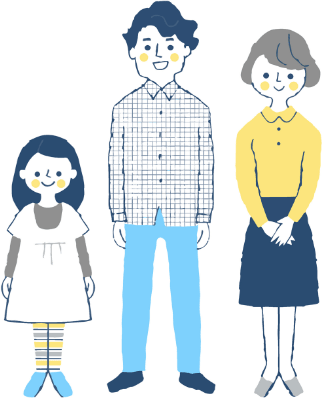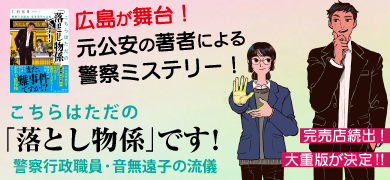1960(昭和35)年7月2日、月刊『潮』は産声をあげました。 以来六十星霜、通巻740号を超える歴史の中から、これまで誌面を彩った有識者、文学者、ジャーナリスト、芸能、スポーツなど、各界の豪華な顔ぶれに再度ご登場いただきます。
※本記事は2020年に刊行した創刊60周年記念特別冊子より抜粋しております。
被災地の皆さんとともに前へ
坂東眞理子(昭和女子大学学長)
未曾有の災害となった震災、津波、そして原発事故の放射能の恐怖。そんな苛酷な三重苦の状況下で、世界が驚くくらい被災地の方々が冷静に助け合って行動していらっしゃった。世界中のメディアが「日本の底力」に驚嘆するけれど、私もこうした被災地の皆さんの姿を通して、改めて日本人であることを誇りたい気持ちになりました。そんな被災地の方々に向かって「がんばって」という言葉は、他人事のようで到底言えるものではありません。皆さんを思い、私たちも今やるべきことをそれぞれの場で精一杯やります。ですから、一緒にがんばりましょう。そう伝えたいと思っています。(『潮』2011年6月号より抜粋)
戦後日本の大きな「分岐点」に立って
姜尚中(東京大学大学院情報学環教授)
政権交代を果たしたものの、その政府の体たらくは人々に無力感と虚脱感を覚えさせている。未曾有の事態に対し、あまりにも政治の対応が遅い。プライオリティが見えてこない。もちろん日本が戦前のような姿に戻ることはあり得ないし国際社会も当時とはまったく違うが、もはや国が頼りにならないのであれば、自分たちで自衛するかネットワークを作るしかないと考え始めている人々も少なくない。
(『潮』2011年10月号より抜粋)
時代の転換期に宗教がもつ意味
中沢新一(思想家・人類学者)
福島の原発事故によって戦後の経済的繁栄の意味が問い直されたわけだが、同時に、忘れかけていた海や大地とのつながりの大切さを、今回の震災によって我々は改めて痛感させられた。その二つの衝撃によって、いま日本は国のありよう、文明のありようの根本的見直しを迫られていると言える。そして、そのような時代の転換期にこそ、宗教が大きな意味をもつ。いま日本人の心の中に起きている潜在的変化、見えないうねりに形を与え、方向性を指し示していくのは、宗教の役割なのである。歴史を振り返っても、文明それ自体が大きな危機に直面したとき、政治などとは違う次元からその危機を突破する方法を見出してきたのは、宗教であった。たとえば、日蓮が鎌倉時代に成し遂げたのはまさにそういうことだったと思う。
(『潮』2011年10月号より抜粋)
いまこそ、宗教の力が試される
森 達也(作家・映画監督)
戦後の日本人は、とかく不安に満ち、あらゆるものに対する恐怖感が強い。僕はそんな印象を持っています。その一因として、確固たる宗教観を持たない人が多いということは言えるでしょう。「人智を超えた存在がある」という意識を持つか否かは、その人の心のありようを大きく左右する。拠って立つものが自分の心しかない場合は、生きることの根源的不安を抱えることに繋がってしまうことが多い。/宗教観も含めてもう少し強固な精神性を、もしも多くの日本人が持っていたら、物質至上主義社会にはならなかったかもしれません。
(『潮』2011年11月号より抜粋)
「聞く」ことの大切さ
阿川佐和子(作家)
河合隼雄さんは心理学者として患者の悩みを聞くことも数多くされてきていたから、私は「そういう人に対して、どのようにアドバイスなさるのか」とお尋ねしたのです。すると河合さんは「あ、僕はアドバイスはいっさいしません」とおっしゃいました。もう「あっ、そうですか。ではさようなら!」と言いたくなるくらいにあっさりと。じゃあ何をなさるのですかと問い直すと、「ただ聞くこと」とおっしゃるわけです。図々しいかもしれないけど、私は「やっぱりこれでよかったのだ」と一人で得心しました。
(『潮』2012年6月号より抜粋)
認知症をめぐる「現実」を語ろう
和田秀樹(精神科医) 安藤和津(エッセイスト)
和田 育児には子どもの成長という喜びがありますが、介護は頑張っても報われにくい。その上、認知症は罵声をあびたり、徘徊されたり、排泄物の世話など、見たくないものも見るので、うつになりやすいんですね。2000年4月の介護保険の導入により「介護は家族でする」という暗黙の了解ができてしまい、かえって女性の負担が増えてしまった。
安藤 私も母を在宅介護しましたが、遺言を書いて「私はどんなにボケても、娘たちの世話にはなりたくない」と伝えています。少なくとも、夫に私の介護はさせたくない。ボケて夫かどうかわからなくなって、なんか「ハンサムなあなた、ありがとうございました」と言えれば、それはそれで面白いでしょうが。(笑)
(『潮』2012年11月号より抜粋)
常識を打ち破った誠実と情熱
山中伸弥(京都大学iPS細胞研究所長)
――巨額の税金を使う研究は国民の理解が必要です。スーパーコンピューターについて「2番では駄目ですか」と疑問を呈した政治家がいました。ご研究も(世界の)トップでなければ駄目なのでしょうか。
山中 いえ、そんなことはありません。2番であっても3番であってもしっかり世の人の役に立てばいいと思っています。しかし、1番になるつもりでやらない限り、2番にもなれません。オリンピックでも、金メダルを目指すからこそ、やっと銀メダルに手が届くこともあるでしょう。やはり金メダルを取るような準備が必要だと思います。そうした視点をもって、最先端の科学研究を見ていただきたいですね。
※ノーベル賞受賞記念特別インタビューにて。(『潮』2012年12月号より抜粋)
「生きる力」を育む家庭と学校の使命
平尾誠二(神戸製鋼ラグビー部ゼネラルマネージャー兼総監督)
「ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン」を「一人は皆のために。皆は一人のために」と一般的には解釈しますが、私は「一人は皆のために。皆は一つのために頑張れ」だと思います。一つの目標のためだからこそ、皆が命を賭けるんだというのが「チームワーク論」として重要な考え方になるでしょうね。
※政治解説者・篠原文也氏との対談のなかで。(『潮』2014年4月号より抜粋)
誰かのために生きるとき人は「大人」になれる
伊集院 静(作家)
今の時代、誰もが「この生き方で本当にいいのか」ということを知りたがっている。それを確認したくて右往左往するのが、青春というものだ。人間が「大人になる」ためには、家を出なくてはならない。家を出て新しい友人と出会い、肉親とは違う愛情の温もりを感じることが、人間の肯定につながる。人と人とが友情で結ばれたとき、「生きるということは素晴らしい」と実感することができる。その意味で、友情とは恋愛よりも格が上だという気がする。「大人になる」ということは、自分のためだけではなく、誰かのために生きるということだ。それを続けていけば、面構えがいい男や、女振りがいい女になれる。
(『潮』2014年6月号より抜粋)
いま再びのフェミニスト宣言
上野千鶴子(社会学者) アグネス・チャン(歌手)
上野 女性の出生率と労働率を両方とも確実に上げるためには、三つの方法があります。まず第一に、労働時間を規制して男女ともに残業をなくす。第二に、年功序列によって決まる給与制と新卒一括採用をやめる。第三に、正社員もフレックスタイムで働く非正規雇用者も同一労働同一賃金にする。これら三つの政策パッケージはすでにできあがっているのですが、政治家は採用しようとしません。経団連も連合も反対するに決まっていますから、実現は難しいでしょう。
アグネス 私が政策として実現してほしいのは、女性だけでなく、男性も必ず育休を取るようにするということです。こういう法律ならば、実現は不可能ではありません。スウェーデンの例にならって、日本も法律によって強制的な育休を導入するべきだと思います。そうすれば、女性に対する就職差別も改善されるのではないでしょうか。
(『潮』2014年11月号より抜粋)