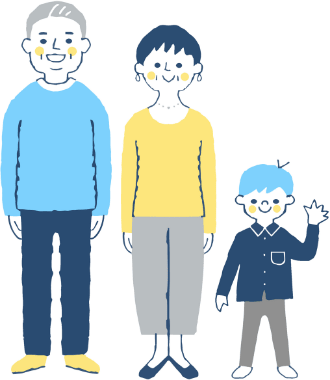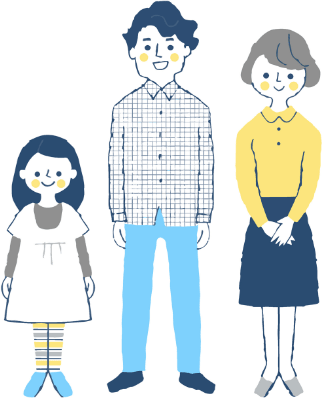フランス文学者・鹿島茂が、すでに失われてしまったかもしれない「核家族的叙情」を振り返り、21世紀的な光を当てることを試みる新連載「あの頃、心を潤す詩と」。第1回は丸山薫の「朝」を題材に、戦後の朝食風景に見る〈核家族的叙情〉と現在に至る家族の変容を解説します。
もう18年も前になりますが、私たち団塊の世代(1947- 49年生まれ)が中学生のとき(つまり昭和30年代後半)に読んだ国語教科書の詩を集めて、アンソロジーを編んだことがあります。『あの頃、あの詩を』(文春新書)というタイトルでした。
編者が国語教科書の詩に込めた、平和の願いと、核家族の抒情の尊さ
編纂の動機については要約すれば次のようになります。
①昭和30年代の国語教科書の実際の編者たちは大正生まれで、団塊世代の親の世代だった。青春期が十五年戦争と重なったこともあり、彼らが選んだ詩は親から子へのメッセージの代わりとなるものだった。
②選ばれた詩は、編者の世代が親しんでいた詩誌『四季』の同人、すなわち丸山薫、千家元麿、山村暮鳥、大木実、田中冬二、河井酔茗らの作品が多かった。
③では、編者たちは彼らの作品に何を見出だし、何を子世代である団塊の世代に伝えたかったのかというと、それは「二度と戦争をしてはならない」というメッセージであることはもちろんだが、さらに突き詰めていえば、核家族(父・母・子供)の生活感情がこの世で最も大切なものと捉えられていたことである。言い換えると、十五年戦争に青春を奪われた編者たちにとって核家族的な抒情こそが至高の価値を持つものであり、その価値観を後続世代に伝えたかったということになる。
さて、いきなり理屈っぽくなってしまいましたが、私がこの連載で試みようとするのは、もしかするとすでに失われてしまったかもしれないこの「核家族的抒情」を作品の中から抽出し、それに改めて21世紀的な光を当ててみることです。果たして、「核家族的抒情」はもう古臭くて捨ててしまっていいものなのか、それとも21世紀的にブラッシュ・アップしてもう一度価値を見出すべきものなのか、その点を考えてみたいと思います。
というわけで、最初に四季派の代表的詩人・丸山薫の「朝」をとりあげてみましょう。
| 朝 丸山 薫 お父さんが新聞をひらくと 新聞紙いつぱいに ぱつと朝日が射した 朝日の中で 刷りたての活字の匂いがする 活字の匂いはいいな ぼくにはよく言えないが ジヤムのような パンのような 食べたくなる匂いだ ―――『青い黒板』より |