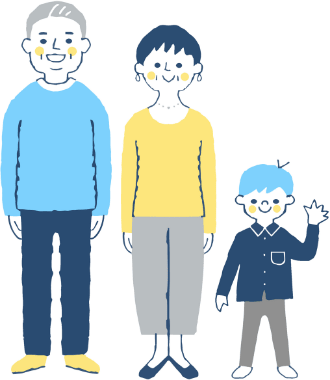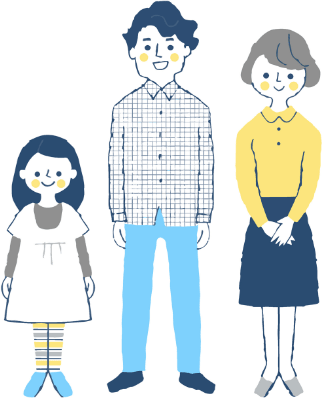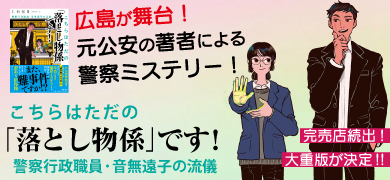人とは違う自分らしさやユーモアを武器に、人生を切り拓いてきた10名の女性たち。華やかな経歴の背景には、それぞれが悩み、葛藤しながらも乗り越えてきた「ガラスの天井」がありました。
鎌田實さんが女性ゲストの人生の軌跡を温かなまなざしで紐解いていく書籍『女の"変さ値"』から、阿川佐和子さんとの対談の一部を紹介します。
鎌田先生の診察を受けるような気分
その日、僕はいささか緊張していた。インタビューのプロフェッショナルに対してインタビューをすることになったからだ。
"その人"は週刊誌で30年以上にわたって人の話を聞くことを仕事にしており、著書の『聞く力』(文藝春秋)は大ベストセラーになっている。"その人"とは阿川佐和子さんだ。
お会いする1週間前からは、阿川さんの著書を熟読する日々を送り、すっかりサワコ・ワールドに浸ることになった。阿川さんからは過去に何度かインタビューを受けたことこそあるものの、その逆は今回が初めてだ。
僕も少し緊張していたが、それはどうやら阿川さんのほうも同じだった。「ちょっと心配。なんだか鎌田先生の診察を受けるような気分です」――。インタビューはそんな阿川さんの一言からスタートした。
阿川さんの本をまとめて読んでみて気が付いたのだけど、彼女の文章にはいつも"ひと捻り"がある。エッセーを書き始めたのはテレビの仕事を始めた1980年代のこと。大文士・阿川弘之の娘ともなれば、若い頃から名文を書いていたのだろうと思いきや、話を聞くとどうもそうではなかったようだ。
本人の言葉を借りると、若い頃の阿川さんは「小説家の娘のくせに漢字は読めないし、書けない。常識も知らない。世界のことが何も分からない。新聞も分からない」という感じだったそうだ。
父から教わった基本中の基本
父娘の貴重なエピソードがある。1983年に阿川さんはある雑誌から原稿執筆の依頼を受ける。父親について原稿用紙7枚を埋める仕事だった。依頼書を父親に見せると「ふーん、俺のいまの連載よりも原稿料がいい。なんなんだこれは」と、むっとした様子だった。
立派なことを書ける気がせずに断るつもりだったが、大作家よりも素人の原稿料が高いことが面白くて、友人にその話をした。すると「立派な文章なんて誰も望んでないんだから書いてみたら?」と背中を押され、それが決め手となって書くことにしたそうだ。
原稿にはいつも友だちに話していた父親の悪口を書いた。ところが原稿を提出するために家を出るタイミングで、運悪く父親に見つかり、原稿のチェックを受けることになる。意外にも、内容のことには触れられなかった。
タイトルや氏名を書く位置などの原稿用紙の書き方や、語尾や「てにをは」の重複など、作文の基本中の基本に対する指摘だけだったのだ。
「『だった』が三回続くと『安機関銃じゃないんだから』、『に』が重複すると『ニイニイゼミじゃないんだから』って。ただ、ある程度直したら『これ以上直すと、俺の文章になってしまうから、適当に清書して持っていきなさい』と。
内容について指摘しなかったのは、自分も散々家族のことを書いてたから、負い目があったんじゃないですかね。私たち家族は本当に酷い目に遭ってましたから」
父の添削は、阿川さんが雑誌で連載を持つようになってからも続いた。「流行り言葉を使うとすぐに腐る」「作文に慣れてきたら筆に流されるから気を付けろ」「常に目上の人がお読みになると思って書け」――。指摘はいつも具体的だった。
阿川さんがスランプに陥ったときのこと。書くことがなくなり、担当編集者からはっきりと「最近の阿川さんの文章は面白くないですね」と言われ、すっかり落ち込んでいた。そのとき、弘之さんからは意外な言葉をかけられたそうだ。「そういうことはある。書けなくなることはある。野球だって、好打者でも三割三分だ」と。
父の文章に関するさまざまな指摘は、いまも阿川さんの耳朶に残っている。僕が「弘之さんの指摘が阿川佐和子の文章をつくってるんだね」と言うと、彼女は肯定も否定もせず、こう言って笑った。
「目上の方に読まれたら、呆れられることばかり書いてますけどね」