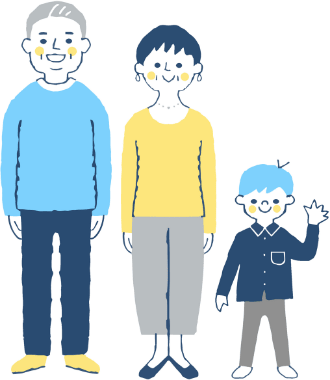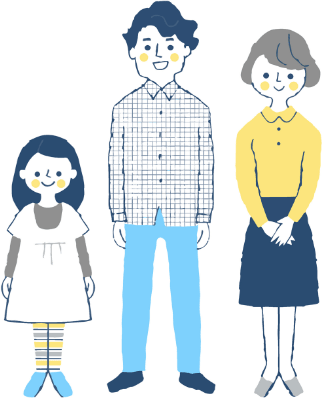澤田瞳子最新作!直木賞受賞後、初の長編連載が待望の単行本化!
八世紀の奈良、欲望渦巻く平城京に投げ出された異邦人と浮浪者たちーー。
争いの渦の中でもがき生きる彼らの姿を稀代の作家が精緻な筆致で描く、衝撃のデビュー作『孤鷹の天』へと続く物語。
第一章 異郷
木の葉は温かい。 大きな葉に小さな葉。丸い葉、細長い葉、とげとげした葉。形も色も様々だが、いずれもかき集めてもぐり込めば、凍えた手足が次第にぬくもってゆく。手足や襟元がちくちくし、時折、蟷螂や芋虫が顔を出すのも、三方を山に囲まれた寧楽(奈良)の秋冬の寒さの前には、大したことではない。 起きていれば、腹が空く。腹が空けば、風の冷たさが身に染みる。帰る場所のない心細さや、この先どうやって暮らせばいいのかとの不安が、ようやく膨らみ始めたばかりの狭虫の胸を大きく揺らす。だから何もかもを忘れるためにも、身を丸めて眠ってしまうのが一番なのだ。 もっとも狭虫のような浮浪児が枯れ葉を臥所に休むには、よくよく場所を選ばねばならない。町並みから遠く離れた秋篠の山々や佐保川の河原では腹を空かせた野犬に食われてしまうし、さりとて高い築地塀が続く大路沿いでは、上つ方の屋敷を守る門番や衛士(警備員)にすぐさま追っ払われるためだ。 「六条大路か七条大路あたりの路地裏が一番いいんだ。市や酒家(飲食店)があたりにあるおかげで残飯にありつきやすいし、酒を飲んだ帰り道の奴らの後をつけ、銭袋をひったくりもできるしさ」 そう話していた三歳年上の真鳶は、平城京を吹き通る風が冷たくなり始めた秋の半ば、薬師寺裏の小道で寝ていたところに火を放たれ、丸二日、火傷で苦しんだ末に亡くなった。近くの溝まで小便に行っていたために命拾いをした狗尾は、黒衣禿頭の男たちが薬師寺の裏門を入っていくところを見たと言う。だが家も親もおらぬ浮浪児の言葉に耳を傾ける者は、誰もいない。 社寺がすっぽり収まりそうなほど広い朱雀大路。真っ赤な柱と緑色の瓦で彩られた大小の屋敷。手輿に乗って行き交うきらびやかな衣をまとった貴人も、忙しげに行き交う人々も、真鳶の亡骸を囲んでうなだれる狭虫たちの姿なぞ、誰ひとり振り返ろうともしない。 とはいえ、人のことは言えぬのだ。真鳶の骸を、狗尾や駒売とともにかわるがわる担いで生駒山に運びながらも、狭虫の頭は空腹で霞み、怒りや哀しみといった感情よりも、今日は食い物にありつけるだろうかという不安ばかりがたゆたっていたのだから。 応遵の寺にいた時に十人いた仲間たちは、これでついに三人になった。その上間もなく、寺を追い出されてから二度目の冬が来る。どれだけ駒売たちと身を寄せ合っても寒風が吹き付ける季節は、家も親もない身には、仲間の死よりもなお恐ろしかった。