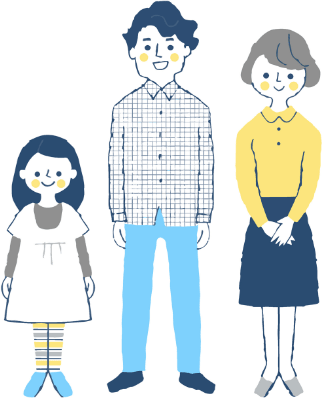「よおし、この辺りでいいだろう。埋めるぞ」 寧楽の西に峰々を連ねる生駒山は、古くからの葬地。同じく空腹に足をもつれさせているくせに、わざわざ都を離れたこんな山中まで真鳶を運ぼうと言い出したのは、三人の中でもっとも年上の狗尾であった。 「馬鹿みたい。どうせ犬に食われちゃうのは同じだってのに、わざわざこんなところまで運ぶだなんて」 駒売が荒い息とともに毒づいて、その場に座り込む。年は狭虫より二つ下のはずだが、どれだけ空腹が続いても不思議に丸みを失わぬ頰と嗄れぎみの声のために、十一歳という実際の年齢より大人びて見える。 狗尾はそれには答えぬまま、厚く降り積もった枯れ葉をかき分け、適当な木切れで地面を掘り始めた。お前らも、と促されて駒売とともにしゃがみ込めば、昨日降った雨のせいか、黒い土は柔らかい。それをいいことに二尺(約六十センチ)ほども地面を掘ってから、狗尾は狭虫たちを振り返った。 「もっと深く掘るぞ。犬なんぞに、真鳶を食わせてなるもんか」 「やってらんないわよ、もう」 駒売がいきなり、棒を捨てて立ち上がる。穴の底から這い上がるや、きっと目を吊り上げて狗尾を睨み下ろした。 「真鳶は死んだのよ。そんな奴のために手間暇かけるより、今日の食い物を探す方が大事じゃない。あたしは帰るわ。東市の入り口で哀しい顔をして座っていれば、粥や蒸し飯を食べさせてくれる人が一人ぐらいいるはずだもの。邪魔になるだけだから、二人ともついて来ないでよ」 言うが早いか駆け出す背が、見る見る小さくなる。狗尾は日焼けした頰を強張らせてそれを見送っていたが、やがて太い息をついて、穴の底にしゃがんだままの狭虫を顧みた。 「狭虫、何ならお前も帰れ。駒売と並んで物乞いをすれば、何か食わせてもらえるだろ」 「いいよ、あたいは。駒売も嫌がるだろうし」 分かっている。同じ場所で物乞いをしても、狭虫と駒売ではもらえる食い物の量が格段に異なる。狭虫の姿を見かけるや、「また来たのか。この餓鬼が」と笞を振り上げる市司の役人も、駒売が相手となると、「腹を空かせているんだな。気の毒に」と目を細める。ともに垢にまみれ、蓬髪を藁しべで結わえていても、狭虫と駒売では人々から向けられる眼差しが最初から違うのだ。 それだけに下手に狭虫がついて行くより、駒売一人で物乞いをさせた方がもらいは多い。駒売は今日もきっと最後には、食いきれなかった結び飯などを懐に押し込んで、市から引き上げてくるはずだ。万事要領が悪く、駒売ほどには愛らしくもない狭虫には、そのおこぼれだけで十分であった。 「……なんでこんな風になっちまったんだろうな。まるでいつの間にか、遠い遠い知らねえ地に迷い込んだみてえな気分だ」
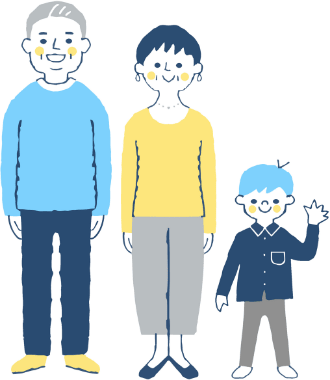
ログイン
ログインを完了しました。