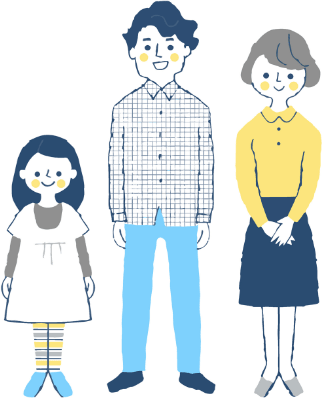低い呻きに顔を上げれば、地面に寝かせていた真鳶の亡骸を狗尾が穴の底に引きずり下ろそうとしている。あわててそれを手伝いながら、狭虫は斜面の果てに広がる都の町並みにふと目を向けた。 (――それ、美しかろう。日本広しといえど、これほどに条坊相整った地は他にはないぞよ) 東西南北に整然と走る大路の果て、長い築地塀の中で秋陽に甍を輝かせる大小の建物は、この国を治める帝のおわす宮城。白砂が光る中庭は、官人たちが政務を執る朝堂院。その南北にそびえ立つひときわ巨大な建物は、大極殿に朱雀門。 いつだっただろう。応遵が寺で養っていた子どもたちを引き連れ、この生駒の山にやって来たことがあった。眼下にはるばると広がる平城京を見下ろし、都のあれこれを教えてくれた穏やかな声はまだ耳の底に残っているのに、あの時とは何もかもが違う。 都の町並みが、水をくぐったかのように滲む。組み合わせた両手は自分のものとは思えぬほどに冷え切っており、こみ上げる涙の熱さをますます際立たせた。 狭虫も駒売も狗尾も、自分たちがどこの生まれで、父母は何者かを知らない。ただ一つだけ分かるのは、己が幼くして捨てられ、都の外れ、羅城門にほど近い破れ寺に暮らす応遵に拾われた事実だけだ。 狭虫が物心ついた時、すでに応遵は六十過ぎ。一日じゅう都を歩き回って托鉢をしては、子どもたちの食い物を集めて来る、穏やかな老僧だった。狗尾と真鳶を筆頭とする少年たちは、そんな育ての親を少しでも助けるべく、近隣の家々の手伝いに励み、狭虫や駒売たち女児は寺の掃除やつくろいものに精を出した。 応遵によれば、狭虫が生まれた年は畿内一円に天変地異が相次ぎ、即位したばかりの若き帝・首(聖武天皇)はすべては自分が至らぬからだと詫びる詔を出したという。食い詰めた人々が本貫(本籍地)を離れて流民となり、荒れ果てた農地だけとなった郷が、諸国に数え切れぬほど残された。 (おぬしらの父御母御はどうにも食うていくことができず、幼きおぬしらを路傍に捨てたのだろう。されどかような境遇を恨むではないぞ。生きてさえいれば、必ずや良きことはあろうからな) そんな貧しくとも温かな日々が一変したのは、昨夏の終わり。応遵が托鉢先で倒れて、そのまま目を覚まさぬまま、帰らぬ人となった。直後、応遵の遠縁と称する男が寺に乗り込んできて、十人いた養い子たちを叩き出しにかかったのである。 狗尾や真鳶たちは無論抵抗したが、大人相手に敵うわけがない。しかも庶民が僧侶になるためには、役所の許可を得、正式な手続きを踏む必要があるらしいが、親類の男によれば、応遵はどうやら勝手に得度を果たした私度僧だったらしい。 それが租庸調を始めとする税逃れのためだったのか、他の理由があったのか、もはや確かめるすべはない。ただ一つ明らかなのは、応遵が私度僧だったと知れ渡った途端、それまで子どもたちに親切だった近隣の家々がみな、掌を返すが如く関わり合いを拒んだことだけだ。
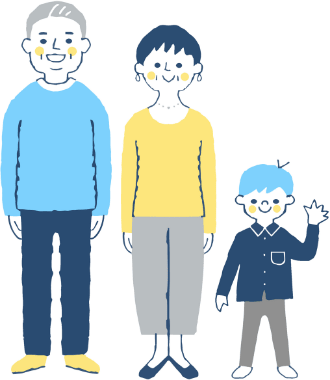
ログイン
ログインを完了しました。