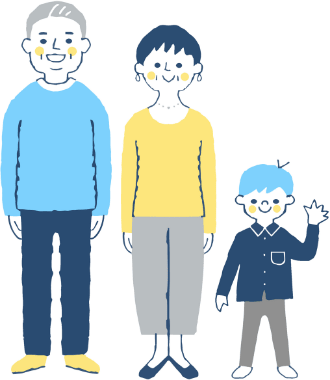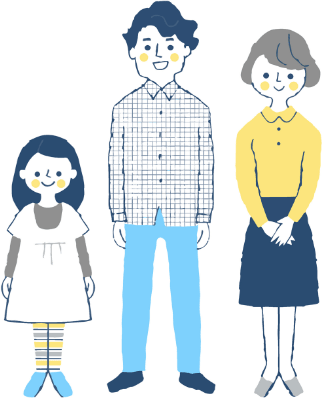遣唐使は大使が乗り込む第一船、副使が乗り込む第二船、次官二人がそれぞれ乗り込む第三・第四船の合計四船で海を渡る。すでに船出間近とあって、それぞれの船の甲板では知乗船事(船長)と思しき赤銅色に日焼けした男が水子たちを塩辛声で𠮟り飛ばし、船匠が弟子たちと共に最後の確認とばかり、船内を走り回っていた。 そのけたたましさに度肝を抜かれた晋卿を他所に、玄昉はまっすぐ船底に向かった。船尾近く、菰に包まれた膨大な荷の隙間に腰を下ろし、「どうだ」と昼とは思えぬほど薄暗い船倉を晴れがましげに見回した。 「そちらの木箱の中身は、長安の内外で買い求めた諸仏の御像。壁際の菰荷は諸州を経巡って集めた経論章疏約五千巻。これほど多くの仏典仏具が一度に日本に請来された例はかつてない。無事にこの船が日本にたどり着けば、わが国の仏教は大きく変わるぞ」 「――お待ちなされ、玄昉。自慢を始めるのは、まだ早いですよ」 きいきいと鍋を磨くに似た声に振り返れば、骨と皮ばかりに瘦せた四十男が船梁につかえそうな丈長の身体を屈め、窮屈そうにこちらを見下ろしている。 「この船はまだ、湊すら出ておらぬのですよ。航海がうまく行ったとしても、大唐から日本までは約十日。その間に何が起きるかは、もはや我らの手の及ぶところではありません」 と、なぜか流暢な唐語で続けたのは、鴻臚寺やここまでの道中でたびたび姿を見かけた留学生・下道真備であった。 「なあに、心配はいらんぞ、真備。余人ならともかく、この船には拙僧が乗っているのだ。東海におわす龍王も、この船のためとあらば海を凪がせ、この身をつつがなく日本に帰り着かせるに相違ない」 「やれやれ、そのお気楽さの半分でもわたくしにありましたらねえ。あなたの肝の太さが、わたくしはつくづくうらやましいですよ」 「おぬしが集めた『唐礼』百巻を始めとする書物や種々の道具類も、どうせこの船に乗るのだろう。ならば仏神の御加護のおこぼれに、おぬしも与れる道理だ。心配はいらん」 玄昉はこの真備と心安いと見え、ここまでの道中も頻繁に軽口を浴びせ付けていた。 もっとも真備からすれば、万事、自慢たらしい玄昉の態度がいささか鼻に付くのだろう。 「百巻ではありません。わたくしが買い付けた『唐礼』は、全部で百三十巻です。勘違いしないでいただきたい」 と生真面目な口調で訂正して、晋卿にちらりと目を走らせた。 「それにしても、そちらの若者は唐人でしょう。異国の者を勝手に船に乗せたりして、大使さまに𠮟られても知りませんよ」 「ふん、また小言か。拙僧が無事にこれらの経典を請来できるのも、この晋卿の働きあればこそだ。その恩義に報いんとして何が悪い」 「まあ、こたびの帰国の船には、いつになく外国の衆が多いですから。ご出家であれば、大福先寺にお住まいだった道璿さま、婆羅門僧の菩提僊那さまに林邑僧の仏哲さま。阿倍仲麻呂さまの従者であった羽栗吉麻呂は唐の女に生ませた息子二人を連れてこの船に乗り込むそうですし、第二船には遣唐副使さまがぜひにと見込んで連れ帰られる姉弟の楽師(音楽奏者)もいるとか」 万一、見咎められたら、そのいずれかの従者だとでも言い訳するのですね、と言い置いて、真備が踵を返す。まるで板を差し込んだかの如くまっすぐな背を見つめ、「そんなに大勢が」と晋卿は思った。 日本が大唐の学問の摂取に熱心とは、玄昉の挙動からだけでも推測できた。ただ留学生・留学僧に勉学を命じ、多くの書物を集めさせるだけでは飽き足らず、唐人の僧侶や楽師たちを生きた知識そのものとして連れ帰るとは。 日本とはどんな国なのだ。その都城や法典が大唐のそれを引き写して拵えられているのは、話に聞いている。ならばかの地に暮らす人々はどのような衣服をまとい、どんなものを食べているのだ。 (――見たい) 青年らしい単純な疑問は、胸底に湧いた途端、己でも驚くほど激しい渇望へと変わった。 まるでそんな晋卿の胸裏を汲んだかのように、玄昉が胡坐をかいた膝を小さく揺すった。 「わが国では、本邦に来た民にはちゃんと食糧を与え、当人が望むのであれば寛かなる地に住まわせよとの法令があってなあ」 と、ひとりごちる口調で続けた。 「これは大唐の法令を引き写したものらしいが、だからといって一度、日本に来た者は決して故国に帰ってはならぬという意味ではない。日本で名籍(戸籍)を賜ってもなお、帰りたければいつでも大唐に帰っていい。唐人の御坊衆や羽栗吉麻呂の倅どもも、そう分かっていればこそ気軽に船に乗り込むのだろうな」 「帰りたければ、いつでも――」 「おお、そうとも。何ならおぬしもこのまま、共に来るか。わが国の西、大唐にもほど近い筑紫国(現在の福岡県)には那ノ津(博多)という本邦一の大湊がある。そこには唐や新羅の商人が出店を構え、ひんぱんな行き来をしているゆえ、奴らの船に乗り込めば、いつでも長安には戻れるだろうよ」 このままこの船に乗り込み、何千里もの海山を隔てた異国に渡る。それはあまりに途方もないがゆえに、どこか現とは思えぬ甘美な誘いであった。 思えば晋卿には、長安で特にやるべきことはない。義母は異母弟が生まれて以来、あからさまに自分を邪魔にしているし、父もまたそんな妻と晋卿双方の顔色をいつもおろおろとうかがっている。 見事、太学に入学が叶えば、寮での生活を始められるが、今の晋卿の学力ではそもそも合格できるかがまず怪しい。ならばいっそ日本とやらに渡り、かの国で見聞を広めて来れば――そうすれば帰国後はかの晁衡の如く、異国好きの皇帝のもとで出仕が叶うかもしれない。 「本当に……いつでも帰れるのですね」 語尾がわずかに震えたのは、満々たる大海を渡る恐怖ゆえではない。 自分の前にはいま、思いもよらなかった未来が延べられようとしている。こんな途方もない機会を手放しては、必ずや後悔する。かっと火照った頭の中で、まだ見ぬ日本の地がうっすらと形を成し始めていた。 「おお、帰れるとも。先ほども聞いていただろうが。拙僧さえ共におれば、東海龍王は必ずや海原を鏡の如く凪がせ、風伯(風神)は船帆いっぱいに順風を送って、この船を瞬くうちに日本の湊に送り届けるはずだ」 玄昉の言葉をすべて信じたわけではない。だが自信たっぷりに胸を張るこの僧侶であれば、という都合のいい期待が晋卿を励ましたのも事実であった。 (ためし読みここまで)
******
異邦人×浮浪児
八世紀の奈良、欲望渦巻く平城京に投げ出された異邦人と浮浪者たち――。
国家の秘事に巻き込まれて唐から来朝し、不安と孤独な生活を強いられた袁晋卿(えんしんけい)は、浮浪児と出会い、心を通わせていく。
争いの渦の中でもがき生きる彼らの姿を稀代の作家が精緻な筆致で描く、衝撃のデビュー作『孤鷹の天』へと続く物語。
『梧桐に眠る』のご購入はコチラ