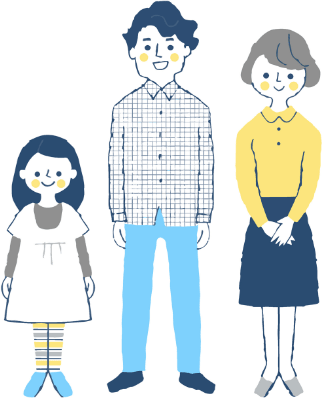晋卿の父は、長安の官営市場を運営する役所・市署の下級役人。そんな父が晋卿が生まれた年、つまり開元五年(七一七)に唐にやってきた遣唐留学僧・玄昉と顔見知りとなったのは、玄昉が入唐直後から暇さえあれば市の書肆(書店)に足を運び、時にはまだ覚束ない唐語で値引きの交渉まで始める変わり者だったためと聞く。 なにせ大唐の都・長安は、東海の果ての日本を始め、半島の新羅、北方の渤海(中国東北部)・契丹(モンゴル高原東部)、南方の安南(ベトナム北中部)や林邑(ベトナム南部)といった周辺諸国から朝貢を受ける大国。そのため長安の大路ではしばしば、目の色も髪の色も異なる人々が見かけられたが、彼らは外国の使者たちの官舎・鴻臚寺での居住が定められ、勝手な街歩きは許されない。外出の際は必ず列を成し、彼らの応対に当たる典客署の官人や訳語(通訳)をぞろぞろと引き連れて大路を行くのが慣例であった。 それだけに今から十九年前、単身、市を訪れる日本人僧の姿は否応なしに目立ち、すぐさま市署と典客署の官人が駆け付けて、彼を鴻臚寺に連れ戻す騒ぎとなった。だがその僧侶は幾度掴まえても、数日後には再びけろりとした顔で市に現れるため、とうとう根負けした典客署が市署の役人を監視に付けてよいならば、という条件で、市への出入りを許した。すると僧侶は待っていたとばかり、共に鴻臚寺に滞在する日本人を幾人も市に誘い出し、わが物顔で広い市を闊歩するようになった。 大唐への諸外国からの朝貢の使者は、おおむね四、五年に一度やってくる。だが日本からの使者は荒れ狂う大海を隔てていることもあって、原則、二十年に一度の到来と決まっている。このため学問を積むべく入唐した日本の留学生・留学僧は、次の船が来るまでの膨大な歳月を勉学に捧げねばならない。そんな彼らにとって、約二里(約一キロメートル)四方の敷地にさまざまな店舗が立ち並ぶ市は、さぞ楽しい息抜きの場だったのだろう。 あれはかれこれ十年以上昔、まだ少年だった晋卿が父を訪ねて市に出かけると、ほぼ必ずと言っていいほど、四、五人の異国人が酒家で飲んだくれていた。そのほとんどが夕刻になってもなお酒卓に突っ伏し、晋卿には理解できぬ異語で管を巻く中、もっとも大柄な僧形の一人だけは、いつも途中で酒杯を投げ捨てて立ち上がり、よろめく足で酒家の向かいの書肆へと入って行った。そして店の者の迷惑顔にもお構いなしに積み上げられている書物をひっかきまわし、時には小脇に数本の巻子を抱えて、よろよろと市門を出ていくのであった。 諸外国からの留学生・留学僧の中でも、特別に長期の滞在を強いられる日本の彼らは、勉学の途中で行方を晦ます者が多い。いつ来るか分からぬ郷里の船を待ちながら、ただただ異国で学問だけを続けねばならぬ境遇が、彼らに道を踏み外させるのだろう。晋卿が大きくなるにつれて、酒家にたむろしていた異国人たちは一人また一人と姿を消した。彼らの記憶も薄らぎかけた頃、長安城の南の城門・安化門の近くに集まる物乞いの中に、かつて酒家にいた男そっくりの者を見かけたこともあるが、本当にそれが当人だったかはよく分からない。 「陋巷に身を隠し、物乞いに落ちぶれるなぞ、まだましな方でな。中には盗賊の群れに身を投じた末に捕らわれ、斬刑に処せられた者すらおるのだぞ」 と、父はいつぞや、小声で語っていた。 それだけに一昨年の夏、「存知よりの日本人僧が人手を欲している。おぬし、小遣い稼ぎにどうだ」との父の誘いに応じて鴻臚寺に出向いた時、十八歳の晋卿は目を疑った。かつてより四肢に肉はついたものの、あの酔っ払いの僧侶がうず高く積み上げられた経典の山の中に、四角四面な顔で座っていたからだ。 「拙僧は玄昉と申す。先月、長安に到着なさった日本の使節に従って、この年の暮れにも都を離れる。その際に持ち帰る書物の整理を手伝ってほしいのだ。よろしく頼むぞ」 聞けば玄昉は十余年前に長安を離れ、国内諸州を巡り歩いたのち雍州・竜興寺にて勉学を積んでいたという。長年の研鑽の結果だろう。いざ言葉を交わせば、玄昉は会話が巧みで、訛り一つない唐語で、時には冗談さえ交えながら的確な指示を出す。 晋卿はもともと内気な質。加えて、早くに連れ合いを亡くした父が後妻を迎え、そちらの腹に異母弟が生まれてからというもの、どうにも家に居場所がない。一日も早く仕事を探して家を出るか、一念発起して官吏の養成機関である太学への入学を目指すか。いずれにしても己の口は己で養わねばと考え始めていた矢先だけに、二十年近い研鑽の日々を終え、晴れて祖国に帰る玄昉の姿は眩しく見えた。 鴻臚寺のそこここでは、つい先日長安に着いた日本の使者と長年の留学を今まさに終えんとしている男たちが、賑やかに久闊を叙し合っている。 「あそこで不機嫌そうな面で書物の整頓をしておるのは、わしと同じ船で来てこのたび共に帰る下道真備。あちらで大使さまと典客署の役人との間で訳語を務めておるのは、こたびの船を見送って、引き続き長安に留まる阿倍仲麻呂じゃ。――ああ、唐の者には、晁衡と申した方が分かりやすいのか」 晋卿は驚いて、玄昉と晁衡の顔を見比べた。 日本は五十年ほど前までは、倭という蔑称で呼ばれていた東夷。そんな辺境から、二十歳の若き留学生として入唐し、太学を経て、官吏の登用試験である科挙に及第した天才・晁衡の名は、長安では広く知られている。 しかも晁衡は唐人でも合格が難しい科挙を一度で突破したばかりか、皇帝・玄宗のお気に入りとして出世を果たし、現在は三十七歳の若さで皇帝の側近・左補闕に任ぜられていると聞く。いわば今日の長安において、立身出世の権化として仰ぎ見られている男が、晁衡であった。 間近にすれば晁衡は猪首で、いささか猫背気味の姿勢とあいまって、およそ秀才然としたところが見つからない。そんな凡庸な風貌がかえって晋卿に、自分がただならぬ場に居合わせているのだと痛感させた。 目の前の男たちはこれから各々の使命に従って、あるいは国に戻り、あるいはこの長安で更なる研鑽を積もうとしている。そんな彼らが眩しければ眩しいほど、まだ何者でもない己が情けなくてならなかった。 そんな晋卿の内奥を敏感に感じ取ったのだろう。皇帝への謁見を済ませた使節がいよいよ長安を離れる前夜、玄昉は最後の荷を検めながら、「よかったらおぬし、揚州の湊まで付いて来るか」と、明朝の朝餉は何かと訊くようなさりげない口調で晋卿に言った。 「二年ほど滞在したことがあるが、揚州は実に面白い地だぞ。海が近いせいで、巨大な運河の流れる街辻を、潮風が朝夕を問わず吹きしきっていてな。港には大小の船がずらりと並び、紅の日輪が東海から昇る朝なぞは、まるで夢の如き美しさ。おぬしは生まれも育ちも長安だろう。見物に行くだけでも、損はないと思うがなあ」 そそのかすような物言いに、不審を覚えなかったわけではない。だが固辞するには、玄昉の弁舌はあまりに巧みであった。その前日、義母からまだ幼い弟の面倒を巡って𠮟責を喰らった苛立ちも、晋卿の背を強く押した。 大唐一の交易の地たる揚州には、長安に出店を持つ商人が大勢いる。帰路は必ずや身元の正しい商人に頼んで、晋卿を長安に送り届けると玄昉は請け合った。しかしいざ揚州にたどり着けば、沖に浮かぶ遣唐使船には高く帆が上がり、桟橋に山積みにされた荷を艀船がせっせと積み込んでいる。 「船出はしあさってだそうだ。どうせなら、それまでの間、我らが乗る船も見物してゆけ」
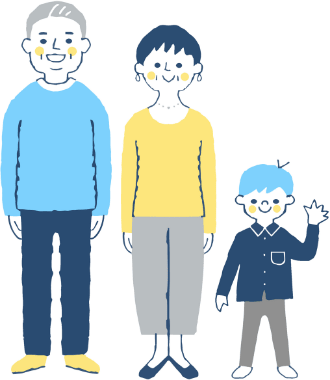
ログイン
ログインを完了しました。