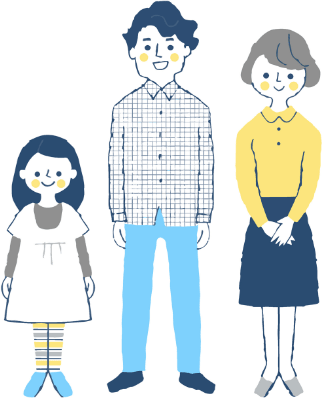ぎぎ、と鈍い軋みを上げて朱雀門の脇門が開くとともに、夜風が鋭い音を立てて辺りを吹き過ぎる。長い朱雀大路を渡ってきたせいか、まだ秋とは思えぬほど凍てたそれに、微醺に火照っていた頰が一度に覚める。袁晋卿はぶるっと身体を震わせた。 「――」 門を開けてくれた衛士が何やら話しかけてくるが、日本の地を初めて踏んでから、まだひと月。晋卿にはまだ、この国の言葉がほとんど分からない。幸い、中臣名代を始め、船中で一緒だった日本の官人たちはみな読み書きに漢字を使っていたため、筆談をすれば大概の意思は通じた。だが会話となると、長安(現在の中国・陝西省西安市)育ちの晋卿にとって、この国の言葉はまるで鳥の鳴き交わしのように間延びして聞こえ、怒っているのか喜んでいるのかすら判然としない。 「まったく、えらいところに来てしまったものだ」 と唐語で呟くと、後にしてきた郷里の遠さが身に染みる。こればかりは長安とよく似た大路の広さが、ひどく恨めしかった。 「おおい、晋卿。ちょっと待て」 妙に発音のよい唐語の呼びかけに振り返れば、擦り切れた袈裟をかけた四十がらみの僧侶がこちらに向かって駆けてくる。 鉢の広い禿頭を衛士の焚く篝火に光らせながら、「住まいまでの道は分かるよな。内裏に参入する前に教えた通り、朱雀大路をまっすぐ南に下がって、三本目の道を左だぞ」と肉付きのいい腕で南東の方角を指した。赤銅色に日焼けした顔とずんぐりとした体躯は、僧形でさえなければ、どこかの武官と間違えそうな逞しさだった。 「そこまで言うなら、玄昉どのが案内してくださいよ。わたしはまだこの国を一度も一人歩きしたことがないんですから。いきなり、自分の家に一人で行けって言われても」 「まあまあ、そう文句を言うな。本日より、おぬしはめでたくこの日本の民。本貫地もこれより向かう左京五条二坊十六町の地に定められ、民部省の戸籍にも袁晋卿との名が記されたのだ。そんな日本の民が夜の都を歩けぬ道理がなかろうが」 ははははと高笑いをして、玄昉が乱暴に晋卿の背を叩く。席が遠かったために確信が持てなかったのだが、先ほどの宴席で玄昉が酒杯を口にしていたように見えたのはどうやら間違いではなかったらしい。 (まったく、えらいところに来てしまった) 胸の中でそう繰り返していると、「なんだ、なんだ、その面は」と玄昉がこちらの顔をのぞき込む。 「そんなに夜道が案じられるのなら、衛士でも付けてもらうか。まったく気弱な男だなあ」 「そういうわけではありません。ただ、わたしにとってこの国は、何から何まで未知の地なのですよ。それをいきなり宴には引っ張り出される、今後の住まいは勝手に決められる。果てはおぬしは日本の民だ、さあ、喜べと言われて、それでうきうきとできるわけがないでしょう」 まくし立てるうちに舌がもつれる。「喜べとまでは言うておらぬはずだがな」との玄昉の平然とした呟きが、腹の底に押し込めていた苛立ちと不安を一度に大きく膨らませた。 「だいたい、わたしは日本に来るつもりなんぞなかったのですよ。それがそなたさまの書物の整理の手伝いをしている間に、あれよあれよと言いくるめられおだてられ、はたと気が付くとこんな東の地に」 長安を離れる羽目になって、間もなく二年。国を出た不安なぞ、とうに忘れたつもりだった。そもそも長安を辞す遣唐使一行に加わって都を離れ、揚州から帰路につく彼らの船に乗り込んだのは、他ならぬ自分の意志だ。 とはいえ先ほど宴席が終わるのを待たず、それぞれの自宅に嬉しそうにこっそり引き上げてゆく水子(水夫)や官人たちを見送った後だけに、後にしてきた郷里への思いが急に胸の底からこみ上げて来る。未知の異郷に対する興奮や興味は針で突かれた革袋の如くしぼみ、玄昉に促されるまま日本に来てしまった愚かさに、指先までがしんと冷え始めていた。 だが玄昉はめんどくさそうに溜息をつくばかりで、まったく動じる気配がない。 「ちょっと、聞いているのですか」 と詰め寄る晋卿に、「ふん、嫌でも聞こえているさ」と舌打ちをした。 「けどなんだ、その言いざまは。申しておくが、拙僧はおぬしを力ずくで長安から連れ出したわけじゃないぞ。一昨年の夏、おぬしを拙僧の手伝いに寄越したのは、他ならぬおぬしの父御だ。その上、拙僧たちが十六年ぶりに来た大使さまの船で長安を去ると決まった時も、揚州からいよいよ船出となった折も、ほいほいと一行に付いてきたのはおぬしだろうが」 睨み合う晋卿と玄昉に、矛を手にした衛士たちが仲裁すべきかと顔を見合わせている。去れ、と彼らに手を振ってから、玄昉は四角い顎を傲岸に上げた。 「どうだ、間違っているか」 父子ほど年下の晋卿を相手にしているとは思えぬほど、大人げない態度であった。
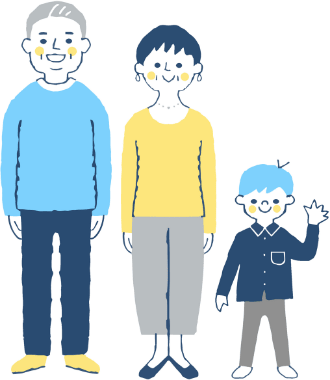
ログイン
ログインを完了しました。