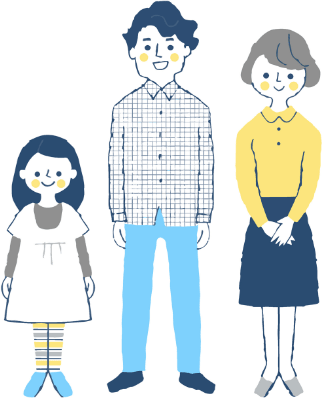日本から唐国へと送られる使者は、四隻の船団のうち一隻が無事に帰国すれば成功と言われている。それだけに第三船・第四船はいまだ帰着していないとしても、大使の乗った第一船、副使の乗った第二船が帰りついただけで、今回の遣使は喜ぶべき結果を収めたことになるのだろう。天皇は本日、副使一行を自ら労う宴を設け、それは夜半まで続く予定という。 「それがどうしたってんだ。俺たちに大事なのはそんな宴じゃなくて、今日の飯だろうが」 声を荒らげた狗尾を、駒売は小馬鹿にしたように見つめた。のみならず、「頭が悪いのねえ」と舌打ちをして、大路の果てにそびえ立つ巨大な朱雀門を目で指した。 「宴があるってことは、外国の奴らが自分の家に帰るのは、辺りが真っ暗になってからってことじゃない。都に来て日が浅いとなれば、そいつらは右も左も分からないはずよ。もちろん都の大路小路にも詳しくないでしょうし、いきなり物盗りに遭ったって、追いかけもできないんじゃないかしら」 「駒売、おめえ――」 狗尾が細い目を瞠る。駒売はようやく分かったかとばかり、にっこり笑って首を傾げた。 「宴の帰りとなれば、帝から何かいただきものをしてるかもしれないわよ。少なくとも空手ってことはないでしょうし、うまく行けば数日は食うに困らずに済むんじゃない?」 「馬鹿ぬかせ。相手は遠い海のむこうから来た奴らだぞ。身体だって都の衆よりずっと逞しいかもしれないし、万一失敗した日にはひでえ目に遭わされるかも」 「大丈夫よ。確かに応遵さまと同じ禿頭の奴らは身体も大きくて、見るからに厳めしかったけど。一人だけ、ようやく根付いた柳の木みたいにひょろひょろな奴がいたの。年もおそらく、狗尾とあんまり変わらないんじゃないかしら」 あいつなら簡単に襲えるはずよ、と迷いのない口調で告げて、駒売は狭虫と狗尾を見比べた。 往来を行く者からのかっぱらいや市での盗みは、狭虫たちには今や、ごく当たり前の生業となっている。初めて市の店先から結び飯をかすめ取った時は、己がしていることの恐怖に、逃げる足がもつれた。だが物陰に転がり込むとともに食らいついた塩飯の旨さは、そんな怯えや後ろめたさを一瞬にして吹き飛ばした。 平城京内には田畑が乏しく、畑の生り物を奪って食いつなぐことは難しい。何も持たぬ自分たちが生きるためには、盗むか奪うしかないのだ。 激しい焔に肌を焼かれ、じゅくじゅくとした液体を染み出させながら冷たくなっていった真鳶の身体は、今ごろ真っ暗な土の中で蜈蚣や蟻に蝕まれ始めているのだろう。彼と同じようになりたくなければ、一日一日を生き抜くべく足掻かねばならない。それより他、自分たちにできることはないのだから。 「しかもありがたいことに、今日は半月。月の出は遅いし、顔を見られずに済むはずよ」 どう、と駒売に笑いかけられ、狭虫の腹が応えの代わりにぐうと鳴る。 すでに日は大きく西へと傾き、三人の長い影が薄汚れた市の築地塀に向かって伸びている。市の店々は早くも店じまいに取りかかり、買い物の人々も帰路につき始めた今、これから物乞いに取りかかったとて、三人分の飯を集められるかは甚だ怪しい。 「宴席の残り物も持っているかもしれないわよ。昔、応遵さまがどこかの宴に招かれた折は、油で揚げた煎餅や甘い粔米をどっさり持ち帰ってくださったわよねえ」 そそるような言い方に、なおさら腹の虫が激しく鳴る。 麦粉を練り、胡麻の油でからりと揚げたところに塩を振った煎餅や、煎り米に甘葛をたっぷりとかけた粔米。応遵がごく稀にそれらを持ち帰った折には、弾けるような歓声が狭い寺を揺らしたものだった。 「─―その一行は、もう宮城に入って行ったんだな。異国の奴らなら、確かにこっちもいつも以上に遠慮は要らないからありがたいな」 ごくりと生唾を飲み込んで、狗尾が問う。その震え声に心の弾みと哀しさを同時に覚えながら、狭虫は茜色を増し始めた夕日を仰いだ。 雲一つ見えぬ空に早くも夕星が明るく瞬き、今夜の風の冷たさをありありと物語っていた。
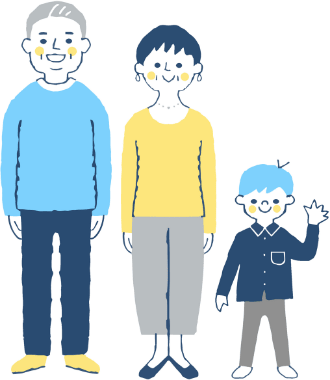
ログイン
ログインを完了しました。