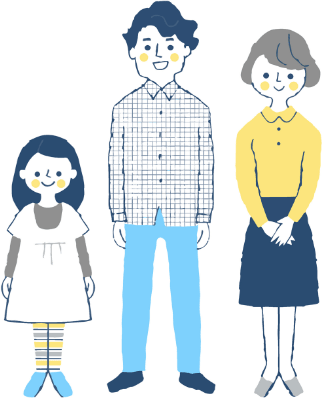うなずき合って山を下ると、二人はまず駒売を探そうと左京の東市に向かった。だが、夕刻前のひと時はもっとも混雑する時刻─すなわち物乞いをするにはもっとも稼ぎの多い時刻にもかかわらず、なぜか市門の前に駒売の姿は見当たらない。 買い物を終えて立ち去る人々、手押し車に積み上げた蔬菜を運び込む男、どこぞから大量の注文を受けたのか両手いっぱいに笊を抱えた物売りの女などが入り混じり、市門の前はいつもにも増して騒がしい。買い物客が押し寄せれば、それを当て込んだ煮売り屋台が周囲に立つのが世の常で、粥売りがまとわりつかせる甘い湯気やじゅうじゅうと音を立てて焼かれる獣の肉の旨そうな匂いが、土埃と相まって顔を叩く。狭虫は口の中に湧く唾を飲み込んで、立ち並ぶ肆(店)から無理やり顔を背けた。 「まったく。あいつはどこに行っちまったんだ」 空きっ腹を抱えているのは、狗尾も同じ。忙しく四囲を見回すその眼差しもまた、何かを堪えるかのように潤んでいる。駒売への苛立ちと更に募る空腹を、狭虫が奥歯で噛みしめた時、駒売が行き交う人波をかき分けてこちらに駆けて来た。 「どこに行っていたんだ」 と、咎める狗尾と狭虫の腕を摑むや、市を囲む土塀際に二人を連れ込んだ。 塀のぐるりには、市内での営業が許されぬ立ち売りたちが集い、市からの帰り客目当ての商いに勤しんでいる。売られているのは市の価格に比べれば明らかに廉価な分、何の肉なのかよく分からぬ串焼き肉、目玉が映りそうなほど薄い粥……それでも案外、客は多いと見え、筵掛けの小屋のそこここには人の列が生じていた。 そんな彼らの間を縫って、道を北へ北へと向かいながら、「さっき、面白い一行が大路を進んでいくのを見かけたのよ」と駒売は声を上ずらせた。 狗尾の小言なぞ皆目耳に入っておらぬと見えて、黒々とした睫毛に縁どられた双眸が星を宿したかのように底光りしていた。 「唐の都から帰って来たお使者なんですって。それも、ただのお使いだけじゃないのよ。顔の色が妙に浅黒い奴や、ぞろりと長い袖に変な冠を着けた奴らが幾人も混じっていたの。都の衆が噂しているのを聞いたのだけど、お使者と一緒に外国の奴らもやって来て、内裏の帝にご挨拶に行くらしいの」 狗尾が狭虫を振り返る。口を尖らせて見せた狭虫に分かっているとばかりうなずいてから、「それはそれとしてよ」と駒売の腕を摑み返して、その場に足を踏ん張った。 「今日の飯はどうなったんだ。ねぐらも探さなきゃならねえし、ぐずぐずしている暇はないぞ」 「だから。その飯の種になりそうな奴らを見かけたって言ってるじゃない」 狗尾の腕を振り払い、駒売は苛立たしげに足を踏み鳴らした。なんだって、と目を剥く狗尾にふんと鼻を鳴らし、「あたし、ちゃんと耳をそばだてて聞いてきたんだから」と目を尖らせた。狭虫がつい目を奪われてしまうほど、自信に満ちた表情であった。 「今日、宮城に入って行った奴らが唐から都に帰って来たのは、もう十日も前。それから今日までの間、左京五条一坊の客館というところに暮らしていたんですって。帝への拝謁が終わったら、お使者とその従者たちはそれぞれの家に戻り、外国から来たお坊さまは大安寺に、それ以外の外国の奴らは客館の近くに家を与えられ、今後はこの都の者として生きていくそうよ」 大路の果て、巨大な官衙のただなかに暮らす天皇が、海山何千里も隔たった唐国なる異国に使いを派遣したことは、まだ健在だった頃の応遵から聞いたことがある。 駒売がかき集めてきた噂によれば、今回戻ってきた一行は、そんな遣唐使のうち副使・中臣名代に率いられた者たち。大使である多治比広成はすでに昨年の春に都に帰りついているが、中臣名代は帰路の船が難破して大使とはぐれたため、一旦、唐国に戻り、大使より一年以上も遅れて帰国を果たしたという。
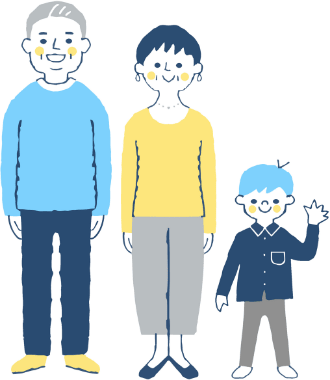
ログイン
ログインを完了しました。