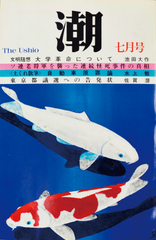ナルデッラ市長(イタリア・フィレンツェ市)が池田大作先生の追悼式で行った弔辞。
「道を開く人」「平和の建設者」と讃え、その遺志は青年の育成と祈り・対話・行動を通じて今も息づくと強調した。
『民衆こそ王者 池田大作とその時代』22巻から一部を抜粋してご紹介します。
******
2024年(令和6年)1月24日付の「聖教新聞」に、次の記事が載った。
〈イタリア・フィレンツェ市で池田先生をしのぶ追悼式/市庁舎ヴェッキオ宮殿で/ナルデッラ市長が弔辞「若き世代に啓発与えた平和の建設者」〉
〈イタリア・フィレンツェ市とイタリア創価学会の共催による池田大作先生の追悼式が20日、同市庁舎であるヴェッキオ宮殿の五百人広間で執り行われ、トスカーナ州のエウジェニオ・ジャーニ知事、同市のダリオ・ナルデッラ市長をはじめ、近隣の市長、宗教界関係者、欧州SGIとイタリア創価学会の代表ら約500人が参列した〉
追悼式はインターネットで中継された。クリスティーナはフィレンツェの学会員を代表して、追悼のスピーチを引き受けた。
池田のイタリア初訪問は1961年(昭和36年)のローマだったこと。それは「私たちの運動の夜明けであり、会員の数はごくわずかだった」こと。草創期は学生が多かったこと――。
「人生の経験が浅い若者ばかりでした。当時は、私たち青年にとって暗黒の時代でした。テロリズムに特徴づけられ、イタリアの多くの都市で暴力事件が発生し、友人の多くが麻薬中毒に陥っていました」
そして81年のフィレンツェ。
「池田先生は、その人間味あふれた温かい振る舞いで、私たちに仏法の原理を話し、仏道修行に真剣に取り組むよう励ましてくださいました。仏道修行は遊びではない、仏道修行は真剣なのだ、と。そして、根気よく続けることで、誰にでも具わっている計り知れない潜在能力を発揮することができると語られました。
信心によって、内面の深い変革が可能となり、家族や地域社会、さらにはイタリア全体の運命の変革へとつながり、人生の旅路で必ず遭遇するであろうさまざまな困難や苦悩を乗り越えていけることを教えてくださいました」
「まだ人生経験の浅い私たちは、これほど人間的で生命力にあふれた人に出会ったこともなければ、大人からこれほど真摯で深い信頼の配慮を受けたこともなく、文字どおり『雷に打たれた』のでした」
「それまでの私たちの活動は、家庭からの逃避であったり、ただ友人たちと一緒にいるためだけの集まりでしたが、1981年に池田先生がイタリアを訪れて以来、私たちにとって仏法への信仰は、自分自身の未熟な人生に、深い意味と使命を見いだす、とても大切な礎となりました」
さらに、池田の訪問後、イタリアで初めてフィレンツェに会館ができたこと。大人たちもその輪に加わり始めたこと。そして――、「私たち自身も大人になっていきました。1981年当時は約300人だったメンバーも、今では十万人に達する勢いです。
私たち全員が心に抱いている共通の体験。それは、この仏法と、自分の生命や身近な人々の生命から最高の可能性を発揮する方法を教えてくれた素晴らしい師匠にめぐりあえたことへの、深い感謝の気持ちです。
私の娘に、43年間の信心と、イタリア創価学会の中で歩んできた道のりを語る時、私はただ、これ以上素晴らしい人生の生き方はないと言う以外に思い浮かばないのです」
ひとたび私と縁した以上、なんとしても宿命転換させてあげたい
81年の数々の励ましのなか、同行スタッフたちの心にひときわ残る出会いがあった。
ミルヴィア・ムーラは前年、母を亡くしていた。自ら選んだ死だった。ミルヴィアはすでに学会に入っていたが、自分も母と同じ道をたどるのではないか――その恐怖が消えず、鬱々としていた。
「私は23歳でした。同志たちに支えられ、励まされながら、フィレンツェに向かいました」
ミニ文化祭が始まろうとしていた。ミルヴィアは白蓮グループ(会合運営に携わる女子部のグループ)として、会場の裏口に立った。「池田先生が通るはずがないと思っていました。ところが先生はその門を通られたのです」。
驚きながら、挨拶を交わした。その日、もう一度、池田の前を通る機会があった。池田から「どこから来たの?」と声をかけられた。はるばる日本から来たこの人は、私のことを気にかけてくれている――そのことがうれしかった。
数日後、池田はミラノに向かった。2カ月に及ぶソ連(当時)・欧州・北米訪問の、半ばにさしかかっている。ソ連から西ドイツ、ブルガリア、オーストリア、そしてイタリアへ……学会員であるなしを問わず、何千人と会い、励ますなかで、ミルヴィアの様子が気にかかった。同行のスタッフから、彼女が母を亡くしたことや、今の状況を聞いた。池田は、ジェノバに住んでいるメンバーとともに、ミルヴィアや彼女の親友もミラノの会合に招いた。
時間を縫って、池田は懇談の機会を持った。「私は母のことを話しました。先生は、私の話を注意深く、愛情深く聞かれ、そしてこのようにおっしゃいました。〝心配しなくていいよ、私もあなたのお母さんのことを思い続けるからね〞。それから、私の親友には"いつも彼女(ミルヴィア)のそばにいてあげてください"と。私は感動しました」。
数日後、フランスの研修会にもミルヴィアは招かれた。池田の妻の香峯子とも話した。
「トレッツでも、先生は多くの時間を費やして、私を励まし、私の質問にすべて答えてくださいました。私は自分の未来についても話しました。音楽が好きなこと。化学者として働いていきたいこと。
先生は、イタリアの若者に流行っていたハシシ(大麻の一種)には手を出してはいけないと言われました。そして、これから2カ月で状況はよくなる、自分にふさわしい仕事を見つけるために、題目を唱えよう、と言われました。それはまさに私が聞きたかった言葉でした。
先生は堅苦しくなく、いつも私を安心させ、冗談をおっしゃいました。それが私には心地よかったのです。"あなたがここにいるのは、真実を求めているからだよ"とも言われました」
*
池田のヨーロッパ訪問から2カ月が経とうとしていた。友人や同志のサポートもあり、ミルヴィアを襲っていた抑うつの症状は徐々におさまった。「当時は夢物語だと片づけられていた、環境保護のために働く、という目標を定めたのも、このころでした」(ミルヴィア・ムーラ)。
日本に戻った池田は、イタリアのリーダーたちが来日するたびに、ミルヴィアの様子を尋ね、記念の品や伝言を託した。彼らは池田の配慮に接するたびに、「創価学会の指導者とは、ここまで細かく学会員に尽くすものなのか」と襟を正した。ミルヴィアは東京の池田に宛てて何度か近況を綴った。国境を超えた励ましは続いた。3年が過ぎたころ、池田から「もう大丈夫だね」と伝言が届いた。
81年の海外訪問に同行したスタッフの一人は、「池田先生は、彼女が死魔と懸命に闘っていることをわかっておられました。"ひとたび私と縁した以上、なんとしても宿命転換させてあげたい"という一念を、ひしひしと感じました」と述懐する。
ミルヴィアは今、リグーリア州の環境保護局(ARPAL)で、化学技術者として水質保護の分野で働いている。「先生はいつも私の心の中におられます」と語る。
「道を開く人」と後継の「平和の建設者」たち
最後に、フィレンツェの追悼式で挨拶に立ったフィレンツェ市長、ダリオ・ナルデッラのスピーチを紹介しておきたい。
ナルデッラは冒頭、「私にとって今日は、単なる一日ではありません。私や今日お集まりの市長の皆さんたちにとっても、よくあるような式典ではありません」と語り始めた。
その20分を超えるスピーチは、日本から始まった一人の「道を開く人」の生涯が、海を越えてどう受け止められているのかの一例である。
「池田先生を偲ぶということは、偉大な思想家、哲学者、師匠、精神的指導者を偲ぶということだけでなく、平和を進めるために具体的かつ全面的に献身された人物を偲ぶということであり……日本、イタリア、そして世界中の創価学会の運動全体において、力強い、不変のものなのです」
「池田大作氏は、創価学会インタナショナルの創立者であり会長として、その精力的な活動を通して、1200万人以上の活動家を巻き込んでこられました。
私は彼らを"平和の建設者"と呼びたい。
活動家という言葉では言い表せないほど、彼らは毎日、毎時間、祈り、対話し、具体的かつ精神的、物質的な行動を通して、平和を建設しています」
「創価の学び舎の青年たちは、平和と人間主義の哲理に触発され、60を超える戦争が世界で起きている今日、最も凶悪な二つの戦争が、ウクライナと中東という私たちの大陸の目の前で起きている中で、国を超えた友愛の精神を育みながら人生を生きています」
「親愛なる友人の皆さん、私が最も心を打たれるのは、幼児から大学生まで、未来の主役である若い世代に対する彼の偉大な尽力と先見性です。それは、彼の著作やスピーチの中に読み取ることができます。
それは、池田大作氏がこの世を去ったからといって終わるものではありません。
池田大作氏は、ここにいるのですから。
この偉大な運動に参加するすべての人々が、平和と対話と精神性のための祈りに、人生のわずかな時間、あるいは多くの時間を捧げる時、池田大作氏はあらゆる場所に、あらゆる瞬間、そこにいるのです。池田大作氏は、今日、かつてないほど、ここにいます」
*
「池田大作氏は、その生涯を通して、またその努力によって、ハイレベルの政治的交流の好循環を生み出し、例えば日中の国交を正常化へと導いてきました。実際、池田氏の行動は、宗教的・精神的なことにとどまらず……時間が経てば経つほど、やがて全世界にとってさらに重要であることが証明されるであろう一歩を踏み出したのです」
「気候変動の深刻さと環境保護の必要性に対する認識が、世の中に未だそれほど浸透していなかった時代に、環境保護に尽力した彼の先見的な知恵と感性の賜物を忘れてはならないのです。
偉大な指導者と凡人の違いは、理想的とも思えるほど大胆なビジョンを持っているかどうかにある、というのは事実であります。
私が記憶している池田氏のスピーチに、『人間と自然』との関係について述べたものがあります。これは、私たちカトリック教徒の立場から言えば、『人間と神が創造した天地』との関係の重要性を説いたものであり、偉大なスピーチであります。
それは、世界の偉大な政治指導者たちの公約、声明、宣言を先取りしたスピーチです。そして、私たちがまだ人間と自然との関係の核心について、うわの空だった時に、彼はそれを行ったのです。また、フィレンツェで開催された核廃絶の展示でも、核兵器に断固反対されていました。
池田氏は、国家間の均衡がやがて危うくなること、大量破壊兵器に頼る可能性を排除しなければならないことを、すでに認識していたのです」
さらにナルデッラは「違いの豊かさを認めなければ、人類の存在理由はない」との信条を語り、「異なることは大きな富です。この多様性を認識することは必要なことです。異なる者同士の対話を促進することが使命なのです」と訴えた。
「フィレンツェ市議会は、マンデラ氏がまだ南アフリカの獄中にあった時、名誉市民称号を授与しました。私は、マンデラ氏と池田氏の思想を結ぶ共通点を見出しました。それは、人類全体の平和のための革命は、私たち一人ひとりの革命から始まるということです。
池田氏は、平和を推進するためには、他の人を待っていてはいけないことを教えてくれました。偉大な運動は、一人の個人が成し遂げるのではなく、一人ひとりの行動の並外れた結集が、地球全体の運動の並外れた勢いにつながることを教えてくれました」
かつてないほど強い「人間主義の対話」を
五百人広間を擁するヴェッキオ宮殿は、建物自体が世界遺産である。かつてフィレンツェ市が池田に「平和の印章」を授与したのも、この広間だった。ヴァザーリの天井画や壁画に囲まれ、ナルデッラの声が響く。
「人類史上初めて死刑が取り消された都市がフィレンツェです。フィレンツェは、世界を美で照らす街であり、……争いを和らげ、どんな人間にも顔を上げ、平和と友情の感情を育む街であります。
フィレンツェは、池田大作氏の人生と著作と深く結びついており、それは永遠に続くでしょう」
「フィレンツェは池田氏を決して忘れることはありません。なぜなら、池田氏は今もなお、平和への関与は、私たち一人ひとりから始まることを教えてくれているからです」
「池田氏は、歴史における偉大な革命は、一人ひとりの心の革命から始まるのだと教えています。
そして何よりも池田大作氏が訴えたのは、人類の偉大な進展は最も危機的な瞬間、つまり希望が消えてしまいそうな時にもたらされるということです。
気候変動、戦争、宗教的対立、世界の多くの人々の孤独など、私たちがそのような瞬間を生きているのが事実だとすれば、私たちの人間主義の対話は、かつてないほどに強く、やめることや避けることはできないのです」
*
「もし私たちが、平和な人類という夢のために自らのすべてを捧げたこの人物にふさわしくありたいと願うなら、私たちは、普段の祈りや仕事、社会的関係において、そして家庭や地域で築きあげる願いにおいて、その時その瞬間に、自分自身から出発しなければならないのです」
「最後に、池田大作氏の名前を冠した通りを設置することで、池田大作氏の名前を永遠に残したいという、私と市議会の意向を表明して、私の挨拶とさせていただきます。
街は人間性と共に生まれます。(20世紀中盤にフィレンツェ市長を務めた)ラ・ピーラ市長の口癖は『王国は過ぎ去り、街は残る』でした。その通りだと思います」
「私たちは一緒に、先生の名を冠した通りに思いをめぐらせたいと思います。その通りを歩き、その名前に触れたすべての人が、池田大作とは誰だったのかと思い、その質問をした人の、隣の人が教えてくれることでしょう。そして、池田大作が誰であり、何を為した人であったかを語る人が、世界中に増えていくことでしょう」
追悼式から3カ月後の2024年(令和6年)4月、フィレンツェ市内に「池田大作広場」が誕生した。敷地内の銘板には、「仏法の師匠 平和の建設者」と刻まれている。
******
※当記事は『民衆こそ王者 池田大作とその時代』22巻から抜粋をしたものです。
続きが気になった方はこちらもご覧ください。
「人間主義」の連帯は、いかに国境を越えたのか。
1979年から1981年へ。反転攻勢の軌跡を辿る。
『民衆こそ王者 池田大作とその時代22 道を開く人篇』「池田大作とその時代」編纂委員会著、定価:1265円、発行年月:2025年10月、判型/頁数:四六並製/272ページ
購入はコチラ
【目次】
第1章 ともに苦楽を祈る日日――裏切りの嵐の中で
第2章 彼らは「人間」なのです――世界広布元年①
第3章 私は深く、熱く信じた――世界広布元年②
第4章 信仰の労作業を避けるな――世界広布元年③
第5章 ただ一つの尊い道――世界広布元年④
第6章 一人が立ち上がればよい――世界広布元年⑤
第7章 久遠元初の法を求めて――世界広布元年⑥
第8章 「池田大作はここにいる」――世界広布元年⑦